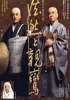五木寛之氏や津本陽氏の小説などで浄土真宗の開祖・親鸞(1173〜1262年)への関心が高まる中、日本宗教史の立場から松尾剛次(けんじ)・山形大教授が『親鸞再考』(NHKブックス)を著し、親鸞には最低2人の妻がいたことなど、通説と異なる驚くべき生涯を描き出している。
五木寛之氏や津本陽氏の小説などで浄土真宗の開祖・親鸞(1173〜1262年)への関心が高まる中、日本宗教史の立場から松尾剛次(けんじ)・山形大教授が『親鸞再考』(NHKブックス)を著し、親鸞には最低2人の妻がいたことなど、通説と異なる驚くべき生涯を描き出している。
松尾教授は浄土真宗の家に育ち、親鸞に親しみを覚えてきたが、歴史学者として実像を知りたいと考えた。そこで史料的価値が低いとして無視されてきた同宗高田専修寺派や仏光寺派に伝わる伝記に当たり、「あえて偽りの生涯を載せる理由もなく、史料として使える」と判断。そこから親鸞の生涯をたどり直した。
その結果、彼には有名な恵信尼(えしんに)を妻とする前に玉日姫(たまひひめ)というもう一人の妻がいたこと、さらに〈結婚しても極楽往生できる〉ことを示すため、師・法然の命令で妻帯したことなどが見えてきた。ほかにも、親鸞は童子の時に付き従った師・慈円の男色の対象だったことや、悪人こそ救われるという「悪人正機(あくにんしょうき)説」も親鸞の独創ではなく法然の教えだったと考えられることも、著書は伝えている。
偉大な思想家というイメージとは異なるが、教授は「親鸞はとにかく法然に絶対的に帰依しており、師の教えがなければ妻帯も悪人正機説も考えにくい。宗門の教えとは別に、実在としての親鸞を明らかにするのが歴史家の義務」と語る。
それでも、日本仏教の特徴である在家主義を生み出し、仏教を鎮護国家から個人救済の宗教に変えていった点で、「親鸞の革新性は何ら失われない」と教授は述べる。また、意外にも伝記研究は停滞しているといい、「この著書が前進のきっかけになれば」と話している。
植田滋 より 読売新聞 から