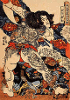明治以前の日本はこのように仏教一色だったので、何が仏教なのか、何がありがたいのかも分からなくなっていたと言える。今日では葬式法事仏事にきわめて限定されたものとしか見られない仏教だが、遙かに大きな広がりのある総合的なものとして捉える必要がある。では、なぜ今日のように仏教を限定的なものと捉えるようになってしまったのであろうか。
明治時代はある意味革命であり、世界の列強によって圧迫されていく世界情勢の中で日本の国が生き残りをかけて国力を集約する意味からも、また薩長による政権交代に権威付けする意味からも日本の国の伝統ある天皇の後ろ盾が必要であった。そこでそれまでの幕府の統制に荷担し民衆掌握のために国家の官吏の役割をはたしていた仏教を排除して、神道を国教化して、近代国家形成のために西欧の思想文化を採用していった。

だから仏教は、すぐれた宗教観念としての一神教ではない多神教であり、呪術にまつわれた野蛮な教えと貶められた。しかしはたして一神教とはいかなるものか。一神教には二つの捉え方があり、それは「一神多現教」と「排他的一神教」と表現できる。一神多現教とは、ヒンドゥー教などのように一つの原理、法の下に多くの神々が現れていると考える宗教であり、多くの神々が化身、または権現として現れるが、それらも大きくは一つの神と見る。
一方、排他的一神教とは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教などのように、唯一の神をたて他を排除する宗教をいう。しかしキリスト教は三位一体と言い、カトリックはマリア様などの多くの神を認めている。だからイスラム教徒はキリスト教は多神教であると考えている。神道は、明治時代初めには大教と言ったが、明治政府が他の宗教と違うものと認識させるために神道と言うようになった。しかし仏教を否定した明治政府も後にキリスト教が蔓延するとの懸念から限定的に仏教を認めていったのである。
http://blog.goo.ne.jp/zen9you より