贅沢三昧、放蕩三昧のように(例が悪いか?)、ナントカ三昧というと何かに没頭している、夢中になっている様子を表す時によく使われる言葉である。
もともと「三昧」とはサンスクリット語の「サマディ」を音写したもので、れっきとした仏教用語である。サマディとは「心を静めて一つの対象に集中し心を散らさぬ状態、あるいはその状態に至る修練」だそうで、その「一つの対象」が「贅沢」や「放蕩」(他にもっといい例はないのか?!)だったりすると冒頭の例になる。仏教の宗旨からは外れるが、言葉の使用法としては決してまちがってはいない。
正統的な仏教の三昧には例えばこんなものがある。
現在も比叡山で行われている「常座三昧」「常行三昧」という行がある。「常座三昧」とは、90日間、眠気を覚ますための歩行、食事、トイレ以外は結跏正座して堂に籠もる行であり、「常行三昧」とは90日間、堂に籠もり念仏を唱え、阿弥陀佛を廻り一日20時間以上歩き続ける。座臥することなく1メートル四方の縄床で2時間の仮眠のみ許される。
いずれも大変厳しい行であるが、それぞれ比叡山西塔の法華堂と常行堂で現在も実際に行われている。ちなみにこの2つの堂は、外見は同じくらいの大きさでよく似ており、渡り廊下で繋がっている。この廊下を持って弁慶が2つの堂を持ち上げたという伝説から「弁慶のにない堂」とも呼ばれる。
常座三昧は法華三昧の流れを組むもので、ひたすら座るところが、後の禅宗の元祖といえよう。常行三昧は「般舟三昧(はんじゅざんまい)」に由来すると思われ、浄土教の起源と言える。
「般舟三昧」はサンスクリット語の「プラティウトゥパンナ・ブッダ・サンムカ・アヴァスティタ・サマディ」の冒頭部の音写で「現在仏悉前立三昧」と訳される。十方諸仏(あらゆる仏)が行者の目の前に現れる三昧で、阿弥陀仏を念じ仏名を唱えながら上記のような行を行うことによって、あらゆる仏に見(まみ)えることを目的とする。
何ゆえ念ずる対象が阿弥陀仏なのかは、『般舟三昧経』がインドにおける阿弥陀信仰の成立と関係あるらしい、というほか明らかでないようだ。
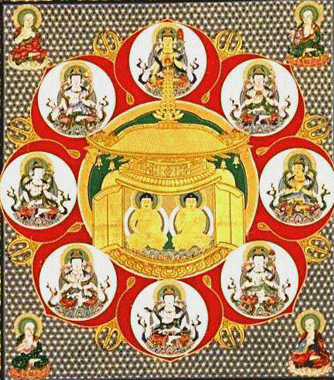
三昧そのものは、集中した結果心の動きが止まった状態を指し、したがって「三昧に入る」という表現が可能である。素人の感想ではあるが、三昧においては何かのビジョンを得ることが重要なモチベーションになっている。その辺が「無念無想」を目指す「禅」(こちらのサンスクリット語源は「ディヤーナ」)と異なるように見える。
ある対象を観想することをサンスクリット語で「ヴィパシャナー」といい、これは「観」と訳される。心の動きを止めて対象の観想に専念することを「止観」という。天台智

