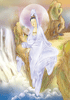「三昧(さんまい)」とはズバリ「葬儀」「墓地」のことである。あるいは墓地に付属した火葬施設をいふ。この名称は仏葬の民衆化とともに広まった。中世以降、正規の僧ではない半僧半俗の行者すなわち「聖(ひじり)」が国々を行脚した。
彼らは民衆に念仏や火葬(仏葬)を教えた。なかでも葬祭に専門的に携わるようになった聖を「三昧聖(さんまいひじり)」といった。三昧聖はまた「おんぼう」とも呼ばれ「隠坊」あるいは「隠亡」ともいわれた。三昧聖は多く墓地の一隅に定住し、聖でもあり賤でもある特殊な職業とされた。
なにゆえ三昧が墓地を意味するようになったか。それには次のような歴史がある。
古来より日本では人が死ぬと、遺骸を人気のない野山に捨て風化するにまかせる「風葬」を行っていた。火葬は仏教の習慣で、白鳳時代に最古の記録があるが、僧侶やあるいは天皇などの身分の高い人中心であり、一般の庶民はもとよりそれなりの身分の人までも風葬にするのが一般的だった。そこには死体を穢れとして遠ざける死生観があったことはいうまでもない。
平安時代中期、『往生要集』を著し浄土教(浄土宗ではない)を大成した恵心僧都源信は「二十五三昧会」という結社を作り、極楽往生のための実践的な活動を開始した。当時の上流貴族を中心とするこのメンバーは「十二箇条起請」というマニュアルを作成し、臨終の瞬間に極楽浄土のことを願っていられるように、日頃は心の準備ため念仏三昧し、いよいよ危なくなると「往生院」という堂に移し、阿弥陀仏像の前で念仏に専念させた。
というのは、死を迎える瞬間の想念が死後の運命を決定する、と考えられていたからである。死の瞬間に極楽浄土を願っていれば極楽に往ける。極楽に往く者は阿弥陀仏及び二十五菩薩の来迎を受けるので、死に顔は安らかで幸せそうになるはずである。「二十五三昧会」の25とは発起人の人数であるが「二十五菩薩」に因んだことは間違いあるまい。
臨終の瞬間の念を特に「正念」という。「正念場」という言葉はここから来ている。メンバーが臨終を迎えるとき、その人が「正念」を保てるように周りで念仏を唱え応援する。これを「助業」という。そうしながら「何が見えるか」死に往く人に尋ねるのも重要な仕事だった。「み仏の姿が見える」などと言いながら死んで往けば万々歳である。(この辺は禅宗と大違いである)

これも一つの三昧である。「念仏三昧」とは、本来こうして心に仏を念じ(「観想念仏」)極楽往生を願うことをいう。ただし仏の姿を観想するのは大変な集中力を要し、シロウトにはなかなか難しい作業である。後の法然は「口称念仏」を中心におき、念仏の易行化を図り浄土宗を開いた。
さて、重要なポイントは浄土教(源信の時点ではまだ「宗」ではない)が日本仏教で初めて、臨終と葬儀に積極的に係わるようになった点である。この「二十五三昧会」こそが三昧聖たちの伝道のモデルになるのである。
平安時代以降、数多くの念仏聖が民衆に念仏を教え、また死者を仏式で葬ることを教えた。こうした聖たちは行基系・空也系・時宗系・高野山系などいろいろな起源や拠点を持つが、民衆に念仏を教え葬祭を行う点では共通していた。仏葬(火葬)は彼らの手によって日本に広まっていった。
念仏聖たちは葬儀のモデルを二十五三昧においたので、民衆の間ではしだいに葬儀そのものを三昧と呼ぶようになっていった。現在でも墓地で行われる葬式を「三昧式」という。そして三昧に携わる聖を「三昧聖」と呼ぶようになったのである。また別称である「おんぼう」は本来「御坊」だったのではないか。「おんぼう」という言葉には、死の穢れを専門に扱う彼らへの畏怖と蔑視の両方がみてとれる。
かように「三昧」とは日本仏教の特殊性を象徴する言葉である。いささか説明不足ではあるが、三昧の持つ2つの意味がお解かりいただけただろうか。
geocities.jp/johannes_schiffberg/Samadhi.html から