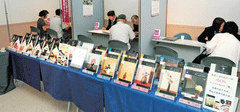 「葬儀費用は初め五十万円と聞いたのに、請求は百三十万円。増額分は『実費』だと言われた」葬儀の事前相談業「リリーフ」(川崎市)の市川愛代表は、同様の相談を何度も聞いてきた。葬儀費用トラブルの多くが、葬儀社の事前の提示額と実際の請求額の差に関することだという。
「葬儀費用は初め五十万円と聞いたのに、請求は百三十万円。増額分は『実費』だと言われた」葬儀の事前相談業「リリーフ」(川崎市)の市川愛代表は、同様の相談を何度も聞いてきた。葬儀費用トラブルの多くが、葬儀社の事前の提示額と実際の請求額の差に関することだという。
誤解を生む原因は、最初に提示される費用「葬儀一式」。祭壇や棺(ひつぎ)、人件費など葬儀社が用意するものの費用を、明細を示さず総額提示するという業界特有の慣行だ。
実際は他に通夜振る舞いなどの飲食費や会葬者への返礼品といった変動費、斎場使用料、火葬料、マイクロバス代などがかかる。これらは葬儀社が立て替え、後で上乗せ請求されるが、これも総額表示が基本だ。
二〇〇七年の日本消費者協会(日消協)の調査では、葬儀費用の全国平均は二百三十一万円。だが「特に上乗せ分の説明が足りない葬儀社が多く、大切な人を亡くしたばかりの遺族は費用の内容を把握し切れていないことも多い」と市川代表は言う。
最終的な請求額が最初の提示額の倍前後になるケースも多い。突然の高額請求に驚き、不信感を抱く遺族が後を絶たない。国民生活センターによると、〇九年度の葬儀サービスについての相談件数は五百四十四件で、十年前の約四倍。相談内容では「価格」がトップ。次が「説明不足」だった。
毎月一定額を前払いし、完納すれば支払額以上の費用の葬儀ができることをうたった冠婚葬祭互助会に関しても「説明と違う葬儀が行われ追加料金が発生した」「解約手数料が高すぎる」などの相談が寄せられている。日消協の調査では、葬儀社の社員が火葬場の職員や運転手らに手渡す「心づけ」も、「渡しました」と言われて請求されるが、実態は不明ととらえる人が多い。費用に関するトラブルの表面化に、ある葬儀社の社員は「高齢化で新規参入業者が増え、聖域だった費用も価格競争になった」と話す。低価格を打ち出す業者も現れ、費用に関心が集まったことが背景にあるようだ。市川代表も「葬儀社に『お任せします』ではなくなってきた。いい傾向だ」と指摘。事前に費用の見積もりを取る人もでてきて、明細を明示する葬儀社も増えている。「二、三社から見積もりを取れば、必ず一社はいいところが見つかる。消費者として選ぶ意識を忘れずに」と助言する。
もうひとつ分かりにくい出費が、仏式では僧侶への「お布施」だ。寺は「お気持ち」として金額を明確にしない。檀家(だんか)総代などに聞けない、地方から都市部に来て菩提(ぼだい)寺を持たない人たちは戸惑う。昨秋から葬儀社を仲介し利用者をサポートする事業を始めた流通大手イオンは、葬儀費用とともに戒名の“ランク”に応じた布施の金額の「目安」を公開した。
主な宗派でつくる全日本仏教会からは「お布施とは感謝を表明する宗教行為であり、対価関係にあるものではない」と反発がでた。イオンライフ事業部の広原章隆事業部長は「檀家ではない人から問い合わせがとにかく多かった。明朗会計を目指したあくまで目安」と話す。
(竹上順子)より
葬儀の費用工面や行い方、墓の準備は人生終盤の大事業だ。誰にも関係することなのに、葬祭は聖域化していて分からないことが多くある。八月のお盆を前に、今どきの葬送の事情を探った。
中日新聞 から

