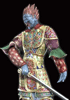天を突く怒髪、大きく開いた目と口。奈良市の新薬師寺本堂で邪悪なものから本尊の薬師如来坐(ざ)像を守るのは十二神将の伐折羅(ばさら)大将像だ。迫力たっぷりの姿は500円切手のデザインにも採用された。
だが、天平時代にこの像が造られた当初は、私たちが現在見ているのとはまったく違う姿だったことが、最近の研究でわかった。
東京の制作会社「キャドセンター」が2003年、大山明彦・奈良教育大准教授(絵画記録保存)とともに、像に残る顔料を丁寧に分析し、コンピューターグラフィックスで復元した。
天平時代の伐折羅大将像の髪は赤く、顔は青色。そでには紫色に金箔(きんぱく)のひし形があしらわれていた。前盾には宝相華(ほうそうげ)や唐草の文様が描かれて、色は赤や青のグラデーションが施されていた。
色が落ちた現在の像と比べて、さらに激しく、荒々しい憤怒の姿だ。長谷洋一・関西大教授(仏教彫刻史)は「天平の人々はその極彩色に驚き、信心を深めたのではないか」と想像する。

新薬師寺は、聖武天皇の病気平癒を願い、光明皇后が創建した。金堂や東西両塔が並び、大伽藍(がらん)を誇ったとされている。
現在はその一部しか残っていないが、08年、かつての隆盛ぶりをほうふつとさせる遺構が、現在の寺の約150メートル西の奈良教育大構内で見つかった。推定で東西68メートルと、現在の東大寺大仏殿も上回る規模の基壇跡が出土した。平安時代に大風で倒壊した金堂の跡と考えられる。
発掘を担当した同大学の金原正明教授(環境考古学)によると、記録などから金堂には37体の仏像が並んだという。7体の薬師如来像がそれぞれ日光、月光菩薩(ぼさつ)像を脇侍として従え、四天王像が周囲を守った。今の伐折羅大将像などは鎌倉時代以降に別の寺から移されたとされるが、別の十二神将像が安置されていたとみる。「薬師如来像は金色に輝き、日光、月光菩薩像や十二神将像は極彩色に彩られていたと考えられます。堂には多くの灯明が煌々(こうこう)とともされ、命の輝きに満ちていたはずです」と話す。
室町時代に確立したわび、さびという価値観の影響で、彩色を施していない仏像を見慣れている現代の日本人が見れば、驚嘆する空間だったはずだ。
朱や緑で彩られた堂塔が立ち並んだとされる平城京の寺院。極彩色に飾られた仏像に、向き合った天平人たちは「浄土の風景」を感じ、手を合わせたのではないだろうか。
佃拓幸 より
特別展から
「至宝の仏像」展に出品されている東大寺法華堂の金剛力士立像(奈良時代)は、背中や足回りなどに彩色が残っており、スポットライトで強調して展示されている。ほかに、浄瑠璃寺の馬頭観音菩薩立像(鎌倉時代)や東大寺公慶堂の地蔵菩薩立像(同)でも、鮮やかな色彩を鑑賞できる。
読売新聞 から