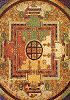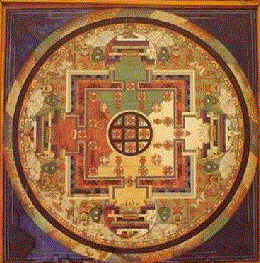 「日本の仏教」だけがそうなのではなくて、いわゆる「世界の仏教国」の大半で「仏教発生当時の姿」とは違ってしまっている…というのが歴史学的な常識になっているようです。
「日本の仏教」だけがそうなのではなくて、いわゆる「世界の仏教国」の大半で「仏教発生当時の姿」とは違ってしまっている…というのが歴史学的な常識になっているようです。
比較的釈迦の仏教を正確に伝えているといわれていた南伝仏教(タイや、スリランカあたりもそうなのかな?)についても、実はその根拠になる経典の成立は今日本に来ている大乗仏教の経典とほぼ同じ時期になるのではないかと推測されています。
日本の仏教は、ご存知の通り中国の影響を多分に受けています。特に「禅」は中国の思想をモロに取り込んだとも言われています。コレ、違和感を持って捉えられる方も多いでしょうが、調べてみるとわかりますよ。
更に、日本が仏教を吸収していた時代と、中国で仏教が(効能主義的に)受け入れられた時代とが合致し、宋であるが故に日本も「効能主義として」仏教を受容したというのが「日本の仏教」を形成するのに大きな意味を持っていたと思えます。
質問者さんは「一神教」的に捉えられていますが、日本の仏教はそんな理由から多分に「多神教」の様相を呈しています。
…そういわないと奈良時代の寺院の大半が薬師や観音を祀っている根拠が説明できない(笑)。
聖徳太子でさえ(最近は架空人物説も唱えられていますが)祀ったのは釈迦ではなく、薬師です。その聖徳太子を供養する(?)法隆寺には観音の影が多分に見えます。
ちょうどその「中国の仏教を真正面から受け入れていた」時代の最後に当たるのが空海と最澄。どちらも「密教」という思想を持って帰ってきています。空海は密教のために、最澄は「天台思想(法華経を中核にする思想)」を学びに行き、その帰途縁に恵まれて、それぞれ密教を持ち帰っています。空海の密教に関して言えば、それ自体は曼荼羅に構成される約1000もの仏らによって構成された多神教です。日本人はその「効能主義的な多神教」を好んで受け入れた(古代神道もどちらかというと多神教的な正確を持っているので、わかりやすかったのでしょう(笑))のが正直なところです。
初期の「経典」が成立した時点で、もうすでに仏教の変質は始まっていた…現在世界に残っている仏教を多面的に分析するとそういう答えが返ってくるようです。
それは、釈迦が「悟りの道」は直接の弟子に指し示したけど、それを更に多くの人に説く方法…つまりリーダーシップ論の指導をしなかったことに原因があるのではないかと考えています。
更に、釈迦の指導スタイルは「対機説法」と呼ばれています。つまり、がんばりすぎている人には「がんばるな」、怠けている人には「もっとがんばりなさい」という指導をし、それが教えを受けた人にマッチするように釈迦自身がアレンジをしていた…というものです。
したがって、釈迦の死語、弟子たちの中でも意見の食い違いが見られ、それらは一度集められて(「結集(けつじゅう)」といいます。2回ありました)経典として整理されましたが、それでも意見の統一までには至らなかったのです。
釈迦の仏教は残っていない…そう考えてしまうのは悲観論です。ボクもそう思ってしまってジレンマに落ちていたのですが、仏教学者で大学教授の中沢新一氏が、夢枕獏ほかと行った対談集「ブッダの箱舟」(中央公論新社)の中で、面白いことを言っています。
「釈迦って、触媒なんだよね、きっと」
釈迦自身が「自分を崇拝しろ」とは一言も言っていない以上、釈迦に原点を求めるのではなく、自分の内面に原点を求める。そのきっかけが釈迦なんだ…そんなないようだと思います。対談はもっとバカ話的に、でももっと高度なレベルで展開されますが(笑)。
いずれの宗派もその釈迦が起こした「仏教」を基点に、釈迦的な考え方を発展させて包摂していった経緯があるのですから、「なにが仏教で、なにが仏教でないか?」的な議論はもはや成立しえないのだと思います。
学者レベルの話をすれば、もう「日本の」「中国の」「韓国の」「チベットの」「インドの」というレベルでの仏教の解釈はしていないと思います。あくまでも「インドで釈迦が作り出し、それがどのような経緯で発展し、その過程でどのように変質して行ったか…というレベルで話が進められています。
「各国の仏教」は、その課程でどの時代のどの思想を受容したか…その問題でしかないのです。
往来が楽になったことで、日本に来た経典とチベット語訳、サンスクリット原典などの比較対象が研究されています。徐々にそういった知識が浸透していくと、もしかすると「国別の仏教」という考え方はナンセンスになるかもしれません。
以上、回答になっているかどうかわかりませんが…
okwave.jp/qa/q1321591.html から