陰陽の組合せにより神(天)の意志を知ろうとする思想。
易の起源は殷代(BC18c ~ BC12c)に亀甲を用いて行われた卜占にさかのぼる。周代(BC12c ~ BC3c)には亀甲の代わりに筮竹が使われるようになった。現在の易は一般に「周易」と呼ばれている。
陰(‐ -)か陽(―)の爻(こう)を重ねたものを卦(か)と呼ぶ。爻を三つ重ねたものは八通りの組合せ(乾・坤・震・巽・坎・離・艮・兌)をもつので八卦という。通常は八卦を二つ(つまり爻を六つ)重ねた六十四卦を使用する。
基本は陰陽二元論であるが、陰陽の関係は必ずしも対立ではなく、引き合い、助け合うものでもある。スイスの精神分析医ユングは、自己を知るための道具である易経が、意識と無意識、自我と自己との統合(個性化)をめざす自分の考えに役立つものであると考えた。彼の「共時性 synchronicity」という思想も、この易との関わりから生み出されたものである。
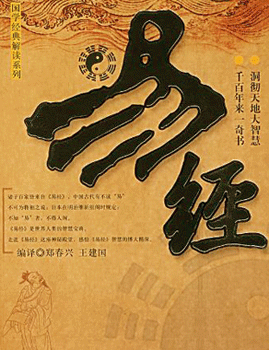
易経
儒教のテキスト「五経」の一つ。内容は直接儒教とは関係ないが、古代から伝えられてきたものを、儒教が、苦手とする抽象的議論に利用しようとしたもの。
『易経』の内容は「経」(本文)と「伝」(解説)とに分かれる。「経」は卦を説明する卦辞(彖(たん)辞)と、卦を構成する爻を説明する爻辞(象辞)からなり、「伝」は「経」部分の解釈および補助資料である十翼(翼は助けるという意味)からなる。十翼には、卦辞の解釈である彖伝、爻辞の解釈である象伝(小象)、易の哲学的解釈である繋(けい)辞伝などがある。
homepage3.nifty.com/juroujinn/eki.htm から

