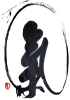気は万物の中を流れる一種のエネルギーであり、自然界にあまねく存在すると考えられた。
天の気の流れを読みとることができれば、世界の動きを知り、将来を予測することも可能となる。それが易や占星術の基礎となった。
地の気の流れを感知し生かそうとするのが風水である。
人は気が集合することにより誕生し、死ぬと気は離散する(『荘子』知北遊篇)。さらに、生きるためには気を体内に取り入れねばならない。気が人の体内を流れるときには経絡というルートを通り、気が集まる場所は丹田と呼ばれる。

インドやギリシャにも、それぞれプラーナ(Prana)やプネウマ(Pneuma)という気に似た概念が存在していた。例えばインドのヨーガでは、プラーナが気に、ナディ(Nadi)が経絡に、チャクラ(Chakra)が丹田に対応している。
人の気を制御する概念として、精、神、道などが考えられた。宋代以降においては、気と、性、理、心などとの関係が議論された。
「形は生の宿であり、気は生を充たし、神は生を制する」(『淮南子』原道訓)針灸、湯液などにより体内の気の流れを順調にし活性化しようとするのが中国医学であり、修行により気の性質をさらに純粋で良質のものにしようとするのが気功である。
homepage3.nifty.com/juroujinn/ki.htm から