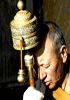1980年代以降の中国では、改革開放に伴い、民衆の宗教信仰心が抑圧された過去に反発する形でよみがえった。それに政府の宗教保護政策もこれらを支えているため、現在、中国の宗教信仰政策は種々の問題を抱えている。
1980年代以降の中国では、改革開放に伴い、民衆の宗教信仰心が抑圧された過去に反発する形でよみがえった。それに政府の宗教保護政策もこれらを支えているため、現在、中国の宗教信仰政策は種々の問題を抱えている。
中でも、宗教問題と民族問題との絡みが緊密化していて、世界的に人権問題や民族問題が深刻化する状況の中で、近年、中国の民族独立運動が活発になる原因の1つは宗教と関わっているところにあるといえよう。
民族的には全国の55の少数民族が中国全体の信徒の大半を占めており、その人口は1億人、居住地域の面積は全国の半分を占めている。その主な信仰宗教は、仏教(朝鮮族)、ラマ教(チベット族、モンゴル族)、南仏教(タイ族)、道教(ヤオ族)、キリスト教(苗族、朝鮮族)、回教(回族、ウイグル族、カザフ族)、シャーマン(満州族、ホチョ族)である。
また、市場経済化に伴う中国社会の変容等に乗じ、民衆の無知につけこむ迷信と宗教の混在が起こっており、最近の例では、1999年7月、新興気功集団「法輪功」に対し、中国政府は「迷信や邪説を流布して民衆をだまし、騒ぎを起こして社会の安定を破壊した」と断定、違法組織と認定し、一切の活動を事実上禁止した。
(注)気功は、古来から心身両面の養生法とされ、改革開放政策が進んだ1980年代以降、国がスポーツとして奨励したこともあり、都市の中高年層を中心に広まった。
「法輪功」は、仏教的要素を取り入れた新興気功集団で、創始者の李氏が1992年から活動を始め、日本など約20か国に組織がある。会員数は数千万と称しているが、中国政府は200万人と発表している。
現在、「中華人民共和国宗教法」はまだ成立していないが、宗教の長期の存在を認め、社会主義と宗教の協調を探りつつ、宗教を効果的に現代化の建設に貢献させようとする点は、今後の宗教政策の大きな課題といえよう。