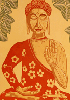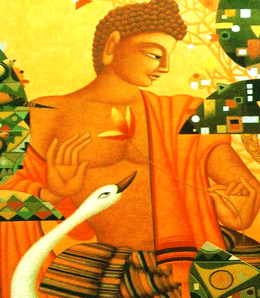 現在日本で目にする仏教(大乗仏教)の姿は、前回までの原始仏教、部派仏教の姿とはずいぶん異なっている。しかし、これは時代を経て様々な地域を通過して形成された姿であって、インドにおいては大乗仏教も、原始仏教、部派仏教から発した系譜上に位置づけることができる。
現在日本で目にする仏教(大乗仏教)の姿は、前回までの原始仏教、部派仏教の姿とはずいぶん異なっている。しかし、これは時代を経て様々な地域を通過して形成された姿であって、インドにおいては大乗仏教も、原始仏教、部派仏教から発した系譜上に位置づけることができる。
大乗仏教の登場以前から話をはじめよう。出家者は悟りによる輪廻世界からの解脱を目指し、在家者は布施などにより善行を積み、生天(昇天)を目指すというのが初期の仏教の教えであった。悟った者は「阿羅漢」と呼ばれ、これは当初は悟った弟子のみではなくブッダ自身をも指す呼称であった。つまり弟子の悟りとブッダの悟りが区別されてはいなかったのである。
しかし、次第に伝統部派教団は、自分たちが目指す阿羅漢の境地をブッダの境地に遠く及ばないものと見なすようになった。ブッダの地位は高められ、身体的にも超人的特徴を具えた者として語られるようになった。次第に整理されたブッダの前生譚、伝記などでも、しばしばその超人的な行状が語られた。自分たち弟子と隔絶したブッダ像が教団内部で形成されていったのである。
輪廻・修行で悟りを目指す
こうした状況のなかで、隔絶したブッダに自らを重ね合わせ、ブッダが歩んだ道を自らも歩み、やがては自らもブッダになることを目指す、という理念が西暦紀元前後から説かれるようになった。これが大乗仏教である。修行者は自らを「菩薩」と呼んだが、これは前生譚や伝記における成道前のブッダと同じ呼称であった。また、大乗仏教で説かれる主な修行は、ブッダが過去世で行ったとされる「波羅蜜」という方法である。ブッダの前生譚に、飢えに苦しむ虎に自らの身体を布施したという捨身飼虎の物語があるように、波羅蜜は極限の修行であり、難行である。大乗仏教の菩薩たちはブッダになるという覚悟のもと、そのような難行を選んだ。
一方、ブッダに自らを重ね合わせたとしても、必ずしも難行のみが要求されるわけではない。前生譚では、ブッダもいきなり悟りに至ったわけではなく、輪廻を繰り返して修行を重ねたことが示されている。人々はこの輪廻のさなかのブッダの姿に、現に輪廻のさなかにある自らの姿を重ね合わせた。そして長い道のりを覚悟しながらもブッダになることを目指し、各々可能な範囲の善行を積んでいったのである。
大乗仏教は、どのような人によって始められたのだろうか。出家僧団とは異なる在家菩薩の集団が仏塔を拠点にして活動し、その人々がブッダへの帰依の心を発展させて大乗仏教を生み出したという説が従来、一般的に支持されていた。しかし近年では、大乗仏教の初期には、その主な担い手は出家者であり、彼らは部派仏教教団から独立した存在ではなかったという見解が有力になりつつある。
(文・鈴木健太◎東京大学大学院博士課程)