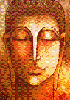仏教が重んじる仏典の数は膨大であるが、なかでも比較的成立が古く、ブッダの教えに近いと考えられているのが原始仏典である。ただし、ブッダの入滅後、数回にわたる結集(編纂会議)を経ていること、様々な付加や削除が行われていることなどを考慮するならば、原始仏典でさえ、ブッダの教えそのものを直接に伝えているとは言いがたい。
現在、形式的に完備している原始仏典としては、パーリ語(「聖典の言語」を意味し、言語学的にはインド中部以西の言語と考えられている)で書かれた南方上座部のものがある。ブッダ自身は、故郷である北インド東部マガダ地方の言葉で教えを説いたと考えられており、布教や結集等を経て、パーリ語に移されたものと思われる。パーリ語仏典は、経の文章の長短に基づいて、以下の五つのグループに分類されている(括弧内は邦訳名、対応する漢訳経典の順)。
1.『ディーガ・ニカーヤ』(『長部』、『長阿含経』)
2.『マッジマ・ニカーヤ』(『中部』、『中阿含経』)
3.『サンユッタ・ニカーヤ』(『相応部』、『雑阿含経』)
4.『アングッタラ・ニカーヤ』(『増支部』、『増壱阿含経』)
5.『クッダカ・ニカーヤ』(『小部』、漢訳なし)
これらは昭和初期に『南伝大蔵経』として翻訳され、その後も続々と新しい日本語訳が出版されている。比較的有名な『スッタニパータ』『ダンマパダ』『ジャータカ』などは、すべて5に含まれている。

大乗仏教の盛んな東アジアに位置し、古来「大乗相応の国土」を自負してきた日本では原始仏典が軽視されてきたが、近代以降、原始仏典の内容が知られるようになり、次第に人々の心を魅了するようになった。最大の理由は、やはり、原始仏典が開祖ブッダの教えに最も近いと考えられているためであろう。近代西洋の仏教研究は、ブッダの歴史的存在を確定した後、その人格を再現・評価することに力を注いだが、このような動きは日本にも波及した。近代以前の日本では、一部の例外を除けば、伝来してくる仏典のすべてをブッダ自身の教えとして受け入れてきたが、近代以降の日本における歴史的ブッダ像の追求は、開祖その人の実像に迫りうるという期待を多くの人々に抱かせ、今日でも大きな影響力を持っている。
その一方で、歴史的ブッダ像という概念により、「仏」の意義など仏教の宗教的核心が切り捨てられてきたことを反省する新しい動きも出てきている。仏典を読む行為は、読み手である私たちが仏典に含まれる理解しがたい内容を切り捨てるのではなく、豊富な内容を含んだ仏典との対話によって、私たち自身を変えていく試みにほかならない。歴史という言葉をより広い意味で捉え直す。そうすることで、かつて現実の仏教世界で行われてきたように、読み手が仏典と向かい合う時々に仏もまた変化し発展するものとして理解し直すことが、改めて模索されているのである。
(文・堀田和義◎東京大学大学院博士課程)