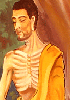仏教はブッダ(仏陀・仏)の教えに由来する。ブッダは「悟った人」の意で一般名詞に近く、特定の一人に限らない。その中でも歴史的に実在し、仏教の開祖とされるのは、紀元前五または四世紀にインドに現れた人物で、本名はゴータマ・シッダールタ(シッダッタ)と言い、そこからしばしばゴータマ・ブッダとも呼ばれる。その出身の種族はシャーキャ(釈迦)族で、そこからシャーキャ・ムニ(釈迦牟尼。釈迦族の聖者)、あるいは釈尊とも呼ばれる。また、如来・世尊などとも呼ばれる。
その伝記は伝説的な色彩に彩られているが、北インドの王族の出身で、出生の地は現在のネパール南部のルンビニーであったという。世俗の生活に満足できずに出家し、はじめは当時の修行者の常として厳しい苦行を行った。しかし、それでは悟りは得られず、二九歳、あるは三五歳の頃、苦行を捨ててブッダガヤーの菩提樹のもとで禅定に入って悟りを開いた。
しかし、ブッダが悟りを開いただけでは仏教ははじまらない。それが人々に説かれて、はじめて後まで伝わる仏教となるのである。ブッダは最初、自ら悟った真理は到底他の人にはわからないだろうと考えて、そのまま悟りの境地を味わって涅槃(ニルヴァーナ)に入ろうとした。それを惜しんだブラフマー神(梵天)がブッダに三回懇願して、そこではじめてブッダは人々のために教えを説こうと決心したという。ブッダはまず、バラナシ(ベナレス)郊外のサールナート(鹿野苑)で、かつて苦行を共にした五人の修行者たちに教えを説き、五人はその教えに感服して弟子となった。これが最初の説法(初転法輪)である。こうしてブッダの説いた教え(ダンマ=法)、ブッダに従う弟子たちの集団(サンガ=僧伽)が具わることになった。ブッダ(仏)・ダンマ(法)・サンガ(僧)をあわせて三宝という。
死であり悟りでもある涅槃
その後、ブッダは当時のインド文化の中心であったガンジス川中流地域で教えを説き、人々を導き続けた。八〇歳に達したブッダは衰えた身で下痢に苦しみ、自ら老いと病いの苦悩を身をもって生き、クシナガラで亡くなった。ブッダの死を涅槃という。ところが、ブッダの悟りもまた涅槃と呼ばれる。涅槃は、煩悩の炎が吹き消されて平安に達した境地のことであるが、死によってもはや煩悩にまったく悩まされることのない完成に達したと考えられたのである。生誕の地ルンビニー、悟りの地ブッダガヤー、最初の説法地サールナート、涅槃の地クシナガラは、後に四大聖地として信仰篤い人々が巡礼するようになった。
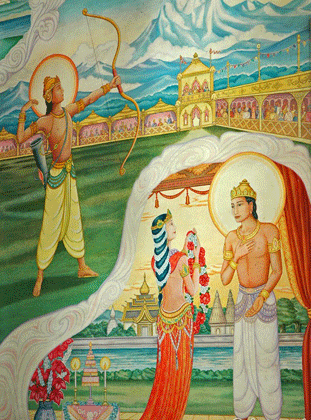
ブッダが亡くなった後、弟子たちはブッダが折にふれて説いた教え(ダンマ)を整理し、それを頼りにサンガを維持し続けた。しかし、三宝のうち、ブッダが亡くなって仏がどうなったかは議論の種となった。ブッダはもはや過去の存在で、死後は何のはたらきもないのであろうか。そのような立場を取るものもいたが、現実にはブッダの遺骨をストゥーパ(仏塔)に祀って崇拝する弟子や信者たちも少なくなかった。そうとすれば、ブッダは涅槃後もまさにその完全な境地から人々を導き続けているのではないか。後に発展した大乗仏教では、この立場からブッダの永遠性を説くこともなされるようになった。
多様な形態の仏教を理解する
このように、仏教は後にさまざまな立場に分かれ、多様な発展をするようになった。まずブッダの涅槃後約百年経った頃から教団の規則をめぐって分裂を生じ、その後二〇以上のグループ(部派)に分かれることになった。そのうち、保守的な立場の上座部がスリランカから東南アジアに伝えられた。彼らはパーリ語の聖典を用いて、今日まで続いている。
大乗仏教の成立はこのような部派の分裂といささか異なり、紀元前後頃に興ったさまざまな新しい動向が次第に統合されていったと考えられる。そのうち、比較的初期に形成された大乗仏教は西域のシルクロードを通って中国に伝えられ、中国語(漢文)に翻訳されて、朝鮮・日本・ベトナムなど東アジアの諸地域に広まった。他方、後に発展した大乗仏教はチベットに伝えられ、チベット語に翻訳され、さらにモンゴルなどにまで広まった。
仏教は発生の地インドにおいては、一三世紀初頭にイスラム教徒の侵入によって滅ぼされたが、このように南伝系の上座部仏教と、東アジア系とチベット系の二系統の大乗仏教の、三つの流れが今日まで続いている。日本の仏教は東アジアの漢文仏教圏に属し、最初朝鮮半島から伝えられ、後には直接中国に学ぶようになった。しかし、同じ東アジアの仏教の中でも、中国・朝鮮・日本ではかなり違いが大きく、まして南伝系やチベット系と較べると、同じ仏教といえるのか、疑問に感じられるほどである。現象面だけとっても、多くの出家者が平然と肉食妻帯しているのは日本だけであり、それがしばしば日本の仏教の堕落として語られる。しかし、それは単純な堕落ではなく、それなりの必然性をもって発展してきた形態である。その日本の仏教の中にもまた多くの宗派があり、さまざまな思想・実践が交錯している。そのような多様な諸形態の理解を深めていくところにこそ、仏教を学ぶ醍醐味があるともいえよう。
(文・末木文美士◎東京大学大学院教授)
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/01.html から