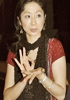音もなくすっと手足の間接を動かし、手をハスの花の形に広げ、ぴたっと止まる。美しい動静の対比は、まるで彫像に命が宿り、目覚めたようだ。
音もなくすっと手足の間接を動かし、手をハスの花の形に広げ、ぴたっと止まる。美しい動静の対比は、まるで彫像に命が宿り、目覚めたようだ。
インド舞踊家・安延佳珠子(やすのぶかずこ)さんが全身で表現するのはインドの伝統舞踊「オリッシー」。オリッシーとはインドの言葉で「月の舞」の意。古代から月の光の下で踊り、ヒンズーの神にささげられてきた踊りだ。両手両足に赤い顔料で印をつけ、グングルという鈴をつけて繊細に躍動的に舞う。
その伝統舞踊が25日、甲府市中央のライブスペース「桜座」で上演される。「古の響き」という上演のテーマは中国に仏教を伝えた古代インドの僧、善無畏(ぜんむい)。強い意志で仏教を伝えた善無畏のように「強い意志を持ち、生きる喜びを感じよう」というメッセージを踊りで表現する。
月の光を再現するため、キャンドルライトを使い、ゆらめく薄明かりの下で安延さんを中心に踊り手7人による群舞や語りをする。伴奏は、インドの太鼓「タブラ」や、琵琶に似たアラブの弦楽器「ウード」。「ウード」は余韻のある神秘的な音色が特徴的だ。
安延さんは18年前、偶然あるインド舞踊家の写真を見て「何か強烈なメッセージ性を感じた」という。そのまま舞踊家の住むインド東部のオリッサ州に飛び、頼み込んで弟子入りした。東京・新宿を拠点に活動しながら今でも半年ごとにインドで舞踊を学ぶというその力量はインド大使館のお墨付きだ。昨年からは同大使館付属のインド文化センターの講師に就任し、日本人やインド人の生徒に伝統舞踊を教えている。
安延さんは昨年、別の公演で桜座を訪れ、たたみのひな壇が並び温かみのある桜座にほれ込み、今回の公演が実現した。「桜座は観客と出演者の距離が近く不思議な一体感がある」と語るその口調には力がこもる。
公演「古の響き」は、前売り4000円、当日4500円。25日午後2時半~同4時。問い合わせは、桜座((電)055・233・2031)へ。
読売新聞 より