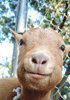国連食糧農業機関の統計によると、ヤギは主にアフリカ・アジアで飼われていて、アジアが飼養頭数・肉生産量の70%前後を占めている。だが、日本では沖縄・奄美にしかヤギ肉食文化はない。
なぜ沖縄・奄美にヤギ肉食文化が根付いたのか。ヤギは人に懐きやすく、子ども・老人も飼いやすかった。農地が狭く、土もやせている島だが、ヤギは草より樹葉を好むため、飼料に困らなかった。肉のほか、乳・ふんも活用できた—といった理由が挙げられるだろう。
食文化の違いもある。日本は仏教の影響で、獣肉を食べる文化は明治以後、100年余りだ。一方、沖縄は中国の影響で、約500年前から獣肉食文化があった。
だが、最大の理由は、食べる物が乏しかった時代、庶民が年に数度食べられる動物性タンパク質の供給源だったことだろう。
沖縄のヤギ料理はヤギ汁、刺身、チーイリチーの3種だが、特に、ヤギ汁に注目したい。沖縄は亜熱帯のため、食べ物が傷みやすい。沖縄の料理は傷みを防ぐため、何度も熱を入れられる汁物が主だ。ヤギ汁も汁物の一種だが、熱を入れるといったん硬くなるヤギ肉を軟らかく食べるために最適の料理だ。ヤギ汁は肉が軟らかくなるだけではなく、何度も熱を入れることで、おいしくもなる。まさに「水増し」することで、多くの人の口にも入る。
それ以上に興味深いのは、アフリカ・アジアはヤギ特有のにおいを嫌い香辛料を多く使うのに対して、沖縄が塩だけを使いヤギ特有のにおいを好むことだ。庶民が高い香辛料を多く使えなかったのだろうが、他地域と比べても極めて珍しい、沖縄独自のものと言える。
戦後も農作業終了後、家の完工・棟上げ、親族の祝い、地域の催しといった場でヤギ料理はごちそうだったが、次第に国外・県外産の安いウシ、トリ、ブタ肉が増えたきたため、ヤギ肉を食べる機会は減ってしまった。復帰後、日本の「と畜場法」が適用され、ヤギを自由に解体できなくなったことも機会が減った一因だろう。
貧しかった時代に食べられていたヤギ肉は、豊かな時代になったため食べられなくなってしまった。「週に数度食べる」「においがたまらない」というヤギ好きも依然、少なくないが、食べる機会自体が減ったため、若い人になじみがなくなっているのが現状だ。
このままだと、日本では沖縄だけ、他地域と比べても極めて珍しいヤギ肉食文化は廃れてしまう
ヤギ肉食を普及させるための壁となっているのが、「ヤギ肉を食べると血圧が上がる」という言い伝えだ。この言い伝えだが、実は、医学的に検証されているわけではない。沖縄と同じようにヤギ肉を食べるアフリカ・アジアの人に尋ねたが、そのような言い伝えはないという。ヤギ肉自体は脂が差さず、ウシ肉と比べ健康的とも言える。この言い伝えの源は、塩・脂を多く使い、骨肉や内臓を煮込む料理法にあるのではないかと私は思っている。
いずれにしても、言い伝えを医学的に検証し、これが正しいなら血圧が上がらない料理法を新たに考える。正しくないなら積極的に払しょくしていくことが肝心だ。

また、ヤギ汁、刺身、チーイリチーの3種以外に、若い人が好んで食べるような新しい料理を考え、機会を増やしていかないといけないし、さまざまな試みがすでに行われ、カレー、ギョーザ、ソーセージといったヤギ肉を使った料理・食材が開発されている。これらは新たな沖縄の特産品へと発展する可能性もある。
また、文化の面だけではなく、教育や健康の面でも、ヤギは可能性を秘めているというのが私の持論だ。過去、子どもや老人がヤギを育てていた。これを現代的にとらえ、意義付けするのだ。
たとえば、飼いやすい特性を活用し、生き物が生まれ育ち、人に食べられるまでの「命のつながり」を子どもに体験させられないか。人は生き物の命を奪い、その命を食べて自らの命をつないでいる。子どもに「生き物はかわいい」といったきれい事だけを教えるのではなく、最終的に命を奪い食べるからこそ、命のつながり、命のありがたさを体験できると思う。乳を搾り、最終的には肉を食べるという前提でヤギを飼っている小学校もある。決して不可能ではないはずだ。
たとえば、老人がヤギを飼う。飼料となる草を刈ることは適度な運動と規則的な暮らしに、生き物を飼うことは生きがいにつながり、高齢者の健康づくりの一助にならないか。
ヤギは沖縄特有の食文化の継承だけではなく、経済、教育、健康の面でさまざまな可能性を秘めているのだ。
琉球新聞 より