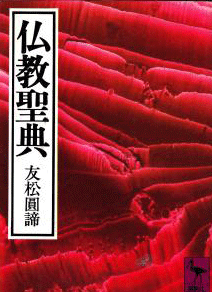 超大国コーサラの王位を奪ったヴィドゥーダバ将軍(パセーナディ王の庶子)は、仏伝資料によれば、自らの出自を侮辱した釈迦族を攻め滅ぼすべく大軍を率いて釈迦国の王城カピラヴァストゥに迫りました。故国の危機を察知した釈尊は、コーサラ軍の進路にある葉のまばらな樹の下で坐禅し、「大王よ、親族の葉陰は涼しいのです」というほのめかしの言葉を用いて、三度にわたってヴィドゥーダバの軍を引き返させた、という伝説があります(漢訳増一阿含経、パーリ・ジャータカ註)。
超大国コーサラの王位を奪ったヴィドゥーダバ将軍(パセーナディ王の庶子)は、仏伝資料によれば、自らの出自を侮辱した釈迦族を攻め滅ぼすべく大軍を率いて釈迦国の王城カピラヴァストゥに迫りました。故国の危機を察知した釈尊は、コーサラ軍の進路にある葉のまばらな樹の下で坐禅し、「大王よ、親族の葉陰は涼しいのです」というほのめかしの言葉を用いて、三度にわたってヴィドゥーダバの軍を引き返させた、という伝説があります(漢訳増一阿含経、パーリ・ジャータカ註)。
しかしヴィドゥーダバが四度目の軍を発したことを知ると、釈尊はもはや釈迦族の命運が尽きたことを悟り、それを止めることはなかったのです。仏伝文学によれば、マハーモッガーラナ尊者が神通力でカピラ城を防衛することを申し出たが、釈尊はそれも退けました。釈尊は釈迦族の過去の業を観察し、かつて釈迦族は河中に毒を投じて漁を行い、下流の生命までも長く苦しめ続ける悪業を行った。その業が熟して、釈迦族も皆殺しになるのだと知って、業の果報の免れられないことを説かれたのでした(パーリ・ジャータカ註)。この説明は、もっぱら個人の業の果報を説く仏典のなかで、「集団の業」について語られた珍しいくだりです。
釈迦国に殺到したコーサラ軍は、ヴィドゥーダバの祖父にあたるマハーナーマ族の一部を除き、釈迦族を乳飲み子に至るまで皆殺しにしたとされます。
ブッダが勧めた?篭城作戦とその瓦解
この攻撃で釈迦族が滅びたことは各仏伝に共通しますが、詳細のディテールはかなり異なっています。
漢訳出曜経によれば、釈尊は釈迦族に対して「コーサラ軍が来ても決して城門を開いてはいけない。開けば皆殺しに逢う」という意味の警告をして、籠城策を取るように諭したとされます。釈迦族はカピラ城に籠城しつつ、舎馬という武将が率いる別動隊を遊撃隊として城外に配して、得意の弓術でコーサラ軍を苦しめました。しかし補給を受けるために城内に戻った舎馬は、国内の内紛*4によって釈迦国から追放され、城内でも開城・降伏派が多数を占めたことで、城門は開かれ、釈迦族は自ら滅亡を招き入れたとされます。これでは、釈尊も「過去の業が熟した」と投げ出しても仕方ありません。ただ、恐らくそのころ釈迦国の政権を握っていたマハーナーマには、「孫を説得することは不可能ではない」という見込みがあったのでしょう。
予想に反して、ヴィドゥーダバは開いた城門から象軍を突入させ、群衆を踏みつぶす凄惨な虐殺を始めました。とっさに機転を利かせたマハーナーマは「自分が場内の池に潜っている間だけでも殺戮を中止して同胞を逃がしてほしい」と懇願します。彼は池に潜ると池の底の樹根に髪の毛をしばりつけ、潜ったままで絶命しました。その間にわずかな釈迦族が城から逃走したのです。ヴィドゥーダバは、「奴隷の血を引いた男が釈迦族の玉座をけがした」と牛乳で清められた王族の腰かけに、こんどは釈迦族じしんの血を注ぐことで、ついに復讐を完遂したのです。
高い民族意識ゆえに滅びた釈迦族
小国ながら由緒ある血筋として尊敬されてきた釈迦族を虐殺したヴィドゥーダバの暴挙は、コーサラ国内でも批判を呼びました。ヴィドゥーダバの息子ジェータ王子は父の軍事行動を批判したことで殺害されてしまいます。また、ヴィドゥーダバ自身も軍隊の野営中に洪水に巻き込まれて溺死したと伝えられます。
釈尊は、自らの民族の滅亡に際しても、「釈迦族は自民族の優秀性を誇り、他国民を見下す高慢な民族だった」ことが滅亡を招いたと冷静に分析していました(ダンマパダ註、出曜経など)。これはヴィドゥーダバが廃太子になったときにコーサラ王を説得したことなどから、ヴィドゥーダバの心の傷と恨みの深さをよく知っていた釈尊ならではの感慨でしょう。
とまれ、ここまで記したことは注釈書に伝えられたものでしかありません。資料的価値の高いパーリ経蔵には、釈迦族の滅亡を伝える記載は一切ありません。繰り返しますが、大般涅槃経(パーリ長部)では、釈尊の入滅後、舎利の分配を求めて「カピラヴァストゥの釈迦族」がクシナーラにやってきた、とも伝えられます。
詳しく内容はこちら

