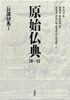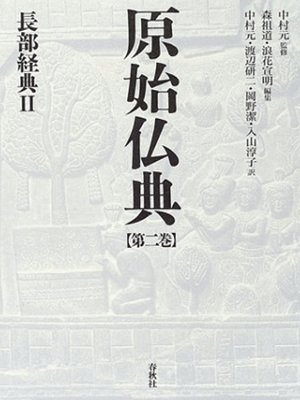 多民族との混血を嫌う
多民族との混血を嫌う
実際の血筋はともかくとして、釈迦族は古代の聖なる王につらなる出自を誇りながらヒマラヤ辺境で農耕を営む少数民族でした。釈迦族はインド社会の四姓制度の文脈では、自らをクシャトリア(王族)階級と位置づけていました。釈迦族のなかではそれほど階級ははっきりしておらず、農地を所有する貴族的な家系(参政権のある王族)とそれ以外の庶民、王家に従属する奴隷(使用人)に分かれている程度だったと思われます。
また、これは釈迦族滅亡の原因となるのですが、「かれらは、混血を恐れ、自分たちの姉妹と同棲生活をしました。」という経典の文章にあるように、釈迦族は他民族との混血を嫌い、独自の通婚タブーを持っていたようです。
釈尊の妃(ヤソーダラ姫)の出自と言われるコーリヤ族は釈迦族の親類民族でしたが、水利権を巡って紛争を起こしたこともありました。以前のエントリ、「様々な菩薩の奇跡と、ほんとうにすごい“ブッダの十八番”」でも触れましたが、中部123「稀有未曾有経」などで「如来の希有未曾有法」として列挙される17項目には、釈尊が立産で生まれたという記録があります。この立産は一部チベット系民族の習慣でもあることなどから、釈迦族はインドを征服したアーリア系民族ではなく、土着のモンゴル系だったのではないかという説も唱えられています(この釈迦族モンゴロイド説は日本の仏教学者からよく言われることです)。
コーサラ国の属国だった釈迦国
そして釈尊の時代、釈迦族が置かれていた状況については、中部98「ヴァーセッタ経」に以下の記述があります。
ヴァーセッタよ、現世においても、来世においても、この衆においても、法がどのように最上であるかということは、次の根拠によって知られるべきです。
ヴァーセッタよ、コーサラ王パセーナディは知っています。
『沙門ゴータマは、釈迦族から出家したものであり、(その)他の人ではない』と。
しかし、ヴァーセッタよ、釈迦族の者たちは、コーサラ王パセーナディに従属しています。
ヴァーセッタよ、釈迦族の者たちは、コーサラ王パセーナディに、平伏、敬礼、起立、合掌、奉仕を行います。
このように、ヴァーセッタよ、釈迦族の者たちがコーサラ王パセーナディに対して行う、平伏、敬礼、起立、合掌、奉仕を、コーサラ王パセーナディは如来に対して行います。それは、『沙門ゴータマは善き生まれの者であり、余は悪しき生まれの者である。沙門ゴータマは力のある者であり、余は力のない者である。沙門ゴータマは端正な者であり、余は醜い者である。沙門ゴータマは大威力の者であり、余は威力のない者である』というようにではありません。そうではなく、その法のみを尊敬し、法を尊重し、法を敬愛し、法を供養し、法を敬礼しつつ、このように、コーサラ国王パセーナディは、如来に対して、平伏、敬礼、起立、合掌、奉仕を行います。
これはバラモン教の生まれ差別に対する痛烈な批判のくだりですが、釈迦族がコーサラ国王に、「平伏、敬礼、起立、合掌、奉仕を行う」従属的な立場に置かれていたことが明言されています。ブッダの時代、釈迦国はコーサラ国の属国だったのです。
釈迦族滅亡の序曲
さて、ブッダの故国である釈迦国は、釈尊の晩年にパセーナディ王から王位を簒奪したコーサラ国のヴィドゥーダバ将軍(琉璃王子)に首都カピラワットゥを攻略され滅亡したとされています。北伝で伝えられた漢訳『増一阿含経』にはその顛末が詳細に紹介されているので、仏教に詳しい方はよくご存じではないかと思います。
しかし、実はテーラワーダ仏教で伝えるパーリ経典には、この釈迦族滅亡の記録が見当たらないのです。ヴィドゥーダバ将軍が釈迦族を滅ぼしたという記録は、釈尊の滅後1000年以上経ってからまとめられたジャータカやダンマパダの注釈書にようやく登場します。パーリ注釈書に出てくる話は、上述の『増一阿含経(36経)』と大筋は似通っています。増一阿含経が訳出されたのは東晋(4世紀から5世紀)の時代なので、その頃には広く知られていた物語なのでしょう。
だいたいの傾向として、漢訳阿含経典に出てくる仏伝エピソードは、パーリ仏典では経典ではなく注釈書に取り入れられているパターンが多いのです。漢訳阿含経典は、経典と注釈書が混ざった形で翻訳されたのでこのような混乱が起こったものと考えられます。
ブッダとその教団の熱心な外護者でもあったパセーナディ王の王子、ヴィドゥーダバが釈迦族を滅ぼすにいたったきっかけは、その生い立ちにあると言われています。
インドの新興勢力であったコーサラ国を統治していたパセーナディは、小国ながら血筋の良さで知られていた釈迦族と姻戚関係を結びたいと考えていました。そこで彼は属国である釈迦国に対して、王族の娘を妃として輿入れさせることを要求します。
これに対して、釈迦国の王族だったマハーナーマは、自らの奴隷女に産ませた娘、ワーサバカッティヤー(一説にナーガムンダー)を自分の王女といつわって差し出します。釈迦族のとりわけ王族は独特な婚姻タブーを持つ閉鎖的な部族社会だったので、族外の異民族との結婚は血の穢れを意味していたのです。
この詐術は、地域大国の台頭でアイデンティティを揺るがされていた小部族国家の意地だったかもしれません。釈迦族の王族たちはコーサラ国に服属している関係からパセーナディ王の要求を断れなかったので、うまく一計を講じたつもりでいたのです。しかし、この近視眼的な態度が、のちに釈迦族の首を絞めることになります。
復讐を誓うヴィドゥーダバ
のちに成長したヴィドゥーダバは弓術(釈迦族は卓越した弓術でも知られていました)を習うために母方の祖国でもある釈迦国に遊学しました。しかし、そこで彼が王族の席に座ったことが大問題になったのです。「奴隷の血を引いた男が釈迦族の玉座をけがした」と憤慨した一部の釈迦族は、呪いの言葉を吐きながら、牛乳でその席を洗い清めました。その光景を偶然目撃してしまったヴィドゥーダバは、自らの血筋を知り衝撃を受けたのです。コーサラ国の皇太子として育てられたにも関わらず、釈迦族が奴隷に産ませた娘が自分の母だったとは……。そして宗主国の王子面する「自分たちの奴隷の子」への嫌悪感をむき出しにした釈迦族に、ヴィドゥーダバは深い復讐心を抱いたのでした。
ヴィドゥーダバの生まれのスキャンダルはすぐコーサラ国にも伝わり(前後関係ははっきりしませんが)、パセーナディ王は激怒してヴィドゥーダバを廃太子し、王子は母とともに蟄居を余儀なくされました。
釈尊のとりなしで窮地を脱する
パーリ・ジャータカ註に記録されたエピソードによれば、パセーナディ王へのとりなしによって、ヴィドゥーダバ母子の苦境を救ったのは、釈尊ご本人だったそうです。これは推測ですが、釈迦族に欺かれたパセーナディ王の方こそ、ヴィドゥーダバを廃太子するどころか、激昂して釈迦国を攻め滅ぼしてもおかしくなかったでしょう。コーサラ王が帰依する「釈迦族の聖者」釈尊がこの問題の仲裁に入ったことで、釈迦族は滅亡の危機から一度は救われたのです。
また、ヴィドゥーダバの生母ではなかったものの、彼に愛情を注いでいたと思われるパセーナディの妃マッリカー夫人(彼女は熱心な仏教徒でした)も彼のために奔走したと思います。この頃の話かは定かではありませんが、パセーナディはマッリカー妃との対話の中で、ヴィドゥーダバを最も愛する者の一人として素直に認めています(中部87経)。パセーナディ王から許されたヴィドゥーダバはしかし、「ヴィドゥーダバ将軍」と呼ばれていました。おそらく王の庶子として扱われており、王位継承者としての地位は曖昧だったでしょう。
ヴィドゥーダバ自身は、自分の血を呪われたものとした「釈迦族の聖者」である釈尊に対して微妙な感情を抱いていたようです。中部90経には、王宮内で釈尊を誹謗する言葉を吹聴したとして、ヴィドゥーダバがパセーナディ王から詰問される描写があります。
またジャータカ註では、釈尊から派遣されたアーナンダ尊者はパセーナディの二人の王妃に法を説いたが、ヴィドゥーダバの母は仏法に関心を寄せることがなかったとされています。釈迦国の王族マハーナーマを父に持っていたにせよ、奴隷の娘としての身分を偽って他国に嫁がされるという数奇な運命をたどった彼女が、その釈迦王族出身のアーナンダ尊者からいくらすばらしい教えを受けたとして、それを素直に受け入れられなかったことは想像に難くありません。
詳しいく内容はこちら