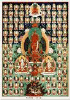神道は多神教だが、祖霊崇拝性が強いため、古いものほど尊ばれる。1881年の神道事務局祭神論争における明治天皇の裁決によって伊勢派が勝利し、天照大神が最高の神格を得たが、敗北した出雲派的なものが未だに強く残っていたり、氏神信仰などの地域性の強いものも多い。
神道は多神教だが、祖霊崇拝性が強いため、古いものほど尊ばれる。1881年の神道事務局祭神論争における明治天皇の裁決によって伊勢派が勝利し、天照大神が最高の神格を得たが、敗北した出雲派的なものが未だに強く残っていたり、氏神信仰などの地域性の強いものも多い。
気象、地理地形に始まりあらゆる事象に「神」の存在を認める。いわゆる「八百万の神」である。この点はアイヌの宗教にも共通する。詳細は神道における神を参照のこと。また、生前業績があった人物を、没後神社を建てて神として祀る風習なども認められる(人神)。
一方で、外来の「神」もみずからに取り込んでしまうという習性を持っており、ユーラシア大陸由来の原始宗教の「神」は多くが神道でも「神」として祀られている。その中には対立しているはずの「神」同士が神道の中では両立していたりする。また、外来の聖者を「神」とあつかうことも多い。この習性は近世になり、産業革命による信仰の重要度の低下と、情報伝達手段が発達したことによって薄れていったが、それでも、本来、キリスト教の要素である十字架が一般に「聖なる物」として認知されたり、月(特に新月、イスラム教)、六紡星(ユダヤ教)といった要素を「人知を越えた存在の象徴」としてとらえたりするなどといった文化的な形で残っている。
神道は多神教だが、祖霊崇拝性が強いため、古いものほど尊ばれる。1881年の神道事務局祭神論争における明治天皇の裁決によって伊勢派が勝利し、天照大神が最高の神格を得たが、敗北した出雲派的なものが未だに強く残っていたり、氏神信仰などの地域性の強いものも多い。
気象、地理地形に始まりあらゆる事象に「神」の存在を認める。いわゆる「八百万の神」である。この点はアイヌの宗教にも共通する。詳細は神道における神を参照のこと。また、生前業績があった人物を、没後神社を建てて神として祀る風習なども認められる(人神)。
一方で、外来の「神」もみずからに取り込んでしまうという習性を持っており、ユーラシア大陸由来の原始宗教の「神」は多くが神道でも「神」として祀られている。その中には対立しているはずの「神」同士が神道の中では両立していたりする。また、外来の聖者を「神」とあつかうことも多い。この習性は近世になり、産業革命による信仰の重要度の低下と、情報伝達手段が発達したことによって薄れていったが、それでも、本来、キリスト教の要素である十字架が一般に「聖なる物」として認知されたり、月(特に新月、イスラム教)、六紡星(ユダヤ教)といった要素を「人知を越えた存在の象徴」としてとらえたりするなどといった文化的な形で残っている。
 神道の研究
神道の研究
平安時代以前より出雲において日本神話とのかかわりが議論されていたらしく、『出雲風土記』には他所風土記とは違い、そういった性格を色濃くみることができる。
鎌倉時代には伊勢神宮の神官による学問的研究がはじまり、徐々に現在の神祇信仰の形を取るに至った。そして、そうした伊勢派の努力はやっと江戸末期のお伊勢参りの確立によって知識人よりも祖霊性の強い庶民の一部からも支持を得ることに成功した。一方で、本居宣長が江戸期には解読不能に陥っていた『古事記』の解読に成功し、国学の源流を形成していった。これら神道や国学の目覚めが欧米列強に植民地化されつつあったアジアの中で、日本の自覚を促し、明治維新を成功に導く思想的流れの一角を成した。神道が形成される過程において、古代は仏教から強く影響を受け、近世では儒教の日本への流入が大きい。伊勢派のはたしたことはそれに対抗する神道側の努力だったと考えるべきだろう。
ウィキ から