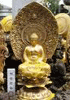「正倉院に伝わる中でも一品」
「正倉院に伝わる中でも一品」
聖武天皇の后(きさき)、光明皇后(701〜760)をしのぶ1250年大遠忌法要が4月と5月の計10日間、皇后が建立した法華寺(奈良市)で営まれる。美術院国宝修理所(京都市)が、正倉院に伝わる香台の“写し”を制作中で、法要の際に本尊、十一面観音立(りゅう)像(国宝)の前に置かれる予定だ。京都市在住の日本画家が皇后を描いた「御影」も奉納される。
制作中の香台は、正倉院に伝わる「漆金薄絵盤(うるしきんぱくえのばん)」(直径約56センチ、高さ約18・5センチ)を8割の大きさに縮小したもの。実物は752年の大仏開眼供養の際、香炉を置くために使われたという。
クスノキを彫った32枚の蓮弁が4段に重なり、赤や青、緑といった鮮やかな色彩が特徴。獅子や鳳凰(ほうおう)、想像上の草花である宝相華文(ほうそうげもん)が描かれ、文様は1枚1枚異なる。
同修理所は08年春に法華寺から依頼を受け、2年間をかけて制作中。藤本青一所長(58)は「正倉院に伝わる中でも一品中の一品と言われている。素晴らしい香台を作らせてもらい、ありがたい」と話す。4月1日の法要で初めてお目見えする。
京都市在住の日本画家、林屋拓蓊(たくおう)さん(63) が光明皇后の姿を描いた「御影」は、縦約160センチ、横約85センチの掛け軸。「みんなの方に一歩踏み出そうという姿」を表現したといい、法要の際に本尊の横に飾られる。同寺の久我高照(こがこうしょう)門跡は「後世に伝えられるものを納めてもらい、大変うれしい」と話す。
が光明皇后の姿を描いた「御影」は、縦約160センチ、横約85センチの掛け軸。「みんなの方に一歩踏み出そうという姿」を表現したといい、法要の際に本尊の横に飾られる。同寺の久我高照(こがこうしょう)門跡は「後世に伝えられるものを納めてもらい、大変うれしい」と話す。
大遠忌法要は4月1〜7日と5月6〜8日。午前10時から法要を営み、午後から琴などの奉納演奏が続く。5月6日の法要には東大寺の僧侶が出仕し、8日は興福寺や唐招提寺などの南都隣山会の僧侶が法要を営む。
asahi 新聞から