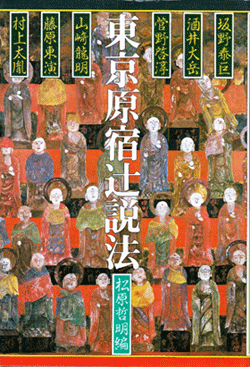
洞林寺護持会会報 平成22年新年号
「南無の会」という超宗派の仏教関係の団体があります。仏教の基本的な教えを一般の方に学んでもらうため、昭和51年から講演会や法話の会などを企画運営している団体です。
「日本仏教は葬式以外何もしない。」という偏った認識をお持ちの方は結構おられると思います。私もそのように感じていた時期もありました。そういう認識を打ち破るべく活動してきていたのが、臨済宗の松原泰道老師を会長とする南無の会でした。私がサラリーマンとして東京に居た当時、南無の会辻説法会場は東京原宿でした。私の職場からわりと近かったので何度か行ってみました。
会長の松原老師は、学部は違いますが、私の出身大学の大先輩です。そういう親近感もあって、松原老師の著書を読み重ねた数も十冊程になります。松原老師の御著書も御法話も、たいへんわかりやすく、温かみがあり、ユーモアがあり、それでいて仏教の教えで貫かれています。私が僧侶の道を本格的に歩むようになってからは、松原老師は大いなる憧れであり大きな目標でした。坊さんとして松原老師のようにはとても成れそうにはないけれど、せめて松原老師が伝えようとすることはしっかり学ぼうという気持ちで著書を読んだり法話を拝聴したりしてきました。
ちなみに松原老師の御子息の松原哲明老師のお話も拝聴したこともあります。私の元職場の研修所に講師としてお見えになり、講話をされました。
「寺の息子として生まれ育ったが、坊さんに成る気にはならず、普通の大学に進み、サラリーマン生活を送っていました。しかし、哲明さんはサラリーマンを続けることに迷いを抱いていました。
或る時、会社が研修の講師に鎌倉円覚寺の朝比奈宗源老師をお願いし、哲明さんがその世話役を命じられました。上司が朝比奈老師に松原哲明さんはお寺の出身ですよと何気なく言いました。すると朝比奈老師から松原と言えば松原泰道は良く知っているが、関係あるのか質問されました。
哲明さんは小さな声で、息子です、と答えました。すると雷が落ちたかのような声で朝比奈老師は、お前ら若い者がこんなところで仕事をしているから、わしみたいな年寄りが今日のようにあっちこっち回らねばならんのだ。こんな会社、さっさと辞めて、わしらのことを手伝え、と言ったそうです。朝比奈老師の言葉が直接の原因ではないですが、哲明さんは心に期するところがあって、会社を辞め、臨済宗の修行道場に行かれました。」
ちょうど私も心に期するところがあり、仕事を辞め駒澤大学仏教学部に編入することを考慮している時でした。哲明さんの話を聞いて決断した訳ではありませんが、自分と似たような境遇の方が実際に居て、自分が今から踏み出そうとしている事を既にやっている方が居る。自分の進む道を照らして頂いたような感じがしました。職場を辞めることを考えていた時期にこういう話が聞けたことに、不思議な因縁を感じました。
別の記事で既に書きましたが、昨年9月15日、大阪伊丹市在住の古結(こけつ)芳子さんという方から突然本と手紙が届きました。実は、会報平成十四年春彼岸号に「希望を持って生きるには—膠原病患者の手記に学ぶ—」という題で古結さんの事を書かせていただいていたんです。
平成13年頃『中外日報』という仏教系の新聞に松原泰道老師のエッセイが載っていました。松原老師は、古結芳子さんという主婦の著書『膠原病を生きる — 銀のしずく』を読んで、難病に苦しみながらも前向きに生きておられる古結さんの生き方に感銘を受け、お手紙を出され、それ以来の交流が続いておられるという内容でした。松原老師ほどの方がこれだけ推奨しているのだから、読んでみようと思い、取り寄せてみました。
「こんな体でも工夫すれば何か出来る、何か出来る喜びは生きている実感」という古結さんの言葉が松原老師のエッセイの締め括りに使われていますが、この言葉に辿り着くまでに古結さんは多くの苦しみを味わい、自殺を考えたこともあったそうです。難病に苦しみながらも前向きに生きる古結さんの歩みは、難病に苦しむ多くの方々へ希望を与えてきました。私も非常に感銘を受け、会報で紹介させていただきました。
会報で少し紹介させていただいたことがありましたが、平成18年11月から私はインターネットでブログを始め、洞林寺の様子や今まで会報に書いた原稿を掲載してきました。「希望を持って生きるには」の原稿もブログに掲載しました。
そして、古結さんから本と手紙に届いたのです。
「突然のおたよりにてたいへん失礼致します。パソコンのグーグルで自分の名前を検索していました。すると、松原泰道老師が私の事を紹介していただいたエッセイを、吉田ご住職様がパソコンで取り上げて下さっており、大きな驚きでした。」
本来なら、本を読んだ私が、松原老師のように、著者に感想や感銘を頂いた御礼を手紙で書くべきところです。それなのに著者自ら旧著『銀のしずく』と新著『生きててよかった』を私に送って下さったのです。恐縮するばかりです。自分なりに一生懸命に書いた文章であっても、必ずしも多くの方が読んで下さるとは限りません。でも、こういうこともあるんですね。十分な紹介記事ではないにせよ、記事で取り上げた本の著者からお手紙と本を頂戴するとは思いもよらないことでした。
古結さんは松原老師から「二冊目を書きなさいよ。」と激励され、「続きの本はまだですか?」という問合せもたくさんきたそうです。何とか力を振り絞って書き始めましたが、長期間鬱(うつ)病に苦しめられ筆を取ることさせ出来ない日々が長く続いたそうです。一冊目の完成から13年後の平成20年8月、二冊目の著書『生きててよかった』が完成しました。この本の冒頭に、百一歳の松原泰道老師の推薦の言葉が寄せられておりました。「(古結さんの)病中生活も、自分を学び他にも尽くす修行です」と賞賛されて居られます。
昨年7月29日、松原泰道老師がお亡くなりになられました。享年103歳でした。松原老師はお亡くなりになられても、「あなたの本に感銘を受けた坊さんが私以外にも居ますよ。」と古結さんを導き、「拙い文章でも、正しい教えを伝えようと努めていけば、伝わっていくんですよ。」と私を導いて下さったのだと思います。感謝を込めて、御冥福を祈って手を合わせました。
私が読んだ松原老師の著書の数は、全著作の十分の一にも満たないかもしれません。まだまだ偉大なる先達から学ばなければ、と思っております。大きな書店なら、松原老師の著書は必ずあります。皆様も是非松原老師の教えに触れてみて下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/dorinji/31361823.html から

