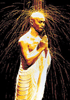大航海時代以降、列強諸国は領土的野心などもあって、多くの探検家を生み出した。間宮林蔵らによる北方探検の歴史があった日本も、一九世紀以降、数多くの探検家を輩出した。その目的の多くは列強諸国と同様であったが、求法を目的とする僧侶も多く含まれていた。そして、彼らの行き先は、ほぼ中央アジアやチベットに限られていた。
このような現象の背後には、明治期の廃仏毀釈を経て、近代化を図りたいという仏教界の思いがあり、近代仏教学の成果がそれを後押しするという形をとった。サンスクリット語仏典の多くは失われてしまったが、中央アジア等では原典が見つかる可能性もあり、また、チベットには原典に忠実なチベット語訳仏典が残されていたのである。
中央アジア探検では、西本願寺第二二代門主大谷光瑞(一八七六~一九四八年)の組織した大谷探検隊が有名である。探検は第一次~第三次の三度にわたり膨大な数の物品を収集した。現在それらは分散しており、日本、韓国、中国の博物館などに収蔵されている。
チベット探検では、寺本婉雅(一八七二~一九四〇年)、能海寛(一八六八~一九〇一?年)、河口慧海(一八六六~一九四五年)、青木文教(一八八六~一九五六年)、多田等観(一八九〇~一九六七年)らがいる。
当時のチベット入りは、清朝やイギリス・インド政庁の厳しい監視もあって困難を極めていた。それにもかかわらず、浄土真宗大谷派の僧侶であった寺本婉雅と能海寛は、中国の四川省からラサを目指し、一八九九年にダライ・ラマの直轄領であったパタン(現・中国四川省)にまで到達した。こうして二人は初めてチベットの地を踏んだ日本人となったが、寺本は危険を察知して一時帰国し、そのまま滞在した能海は雲南省からの手紙を最後に消息を絶った(寺本は、六年後にラサ入りを果たしている)。
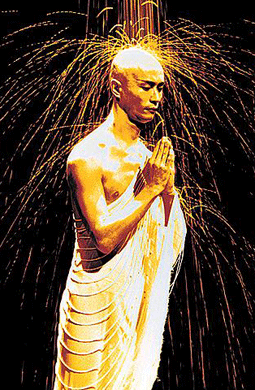
ラサ入りした河口慧海
黄檗宗の僧侶であった河口慧海は、漢訳仏典内に見られる解釈の相違に悩み、原典、もしくはそれに忠実なチベット語訳仏典を求めて旅立ち、一九〇一年に世界中の探検家が果たせなかったラサ入りに成功した。その時の旅行記は“Three Years in Tibet”という英題でも出版され、世界中で高く評価された。また、彼は十数年後に二度目のチベット入りも果たしている。
青木文教、多田等観の二人は浄土真宗本願寺派の僧侶であり、彼らの行動は大谷光瑞の命令によるところが大きい。彼らのチベット滞在には、他の者たちと違ってダライ・ラマ十三世による正式な許可があった。青木は一九一三年から約三年間滞在して、俗学の分野を中心に学び、一方の多田は約一〇年間滞在して、最高学位「ゲシェー」を取得して帰国した。
チベットを探検したこれらの僧侶たちは、非常に多くの仏典や仏画などを請来し、玄奘三蔵の日本近代版とでも呼ぶことができる。彼らがもたらした貴重な請来品は、現在でも多くの大学や博物館で保管されている。
また僧侶以外で、軍事的任務その他によって中央アジアやチベットを探検した日本人も数多くいる。そして、探検には詳細な記録が付き物であり、彼らも多くの記録を残している。これらの記録は、僧侶とは異なった視点に基づいて書かれており、僧侶探検家たちの記録と併せて読んでみるのも面白い。
(文・堀田 和義 ほった・かずよし 一九七七年、愛知県生まれ。専攻はインド哲学。東京大学大学院博士課程)