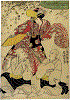「寝るほど楽なことはないけれど、起きて働くアホもある」。生前に母美子がいつも就寝前に言っていました。私がインドの大学院で学んでいたころ、がんのため49歳の若さで亡くなりました。
母は日高川町の農家の5人兄妹の末娘です。陸軍大佐や大相撲の幕内力士、ミスユニバースなど多彩な身内がいたので、地元では知られた一家だったそうです。高校を卒業し、20歳の時に25歳だった父と見合い結婚しました。本当は大学へ進学したかったが、家庭の事情であきらめたと言います。代わりに高校では「クラスで一番先に結婚する」と言っていたそうです。その通り実行したんです。
お寺では、掃除や帳簿付け、檀家さんからの相談など、法要以外は女性の仕事です。嫁いで3、4年後に祖母が亡くなり、ほとんど一人で引き受けていました。子供のころは気がつかなかったのですが、母が他人の2、3倍も働いていたことに、亡くなってから気付きました。お寺の仕事に加え、子育てもしていたのですから。体がそんなに丈夫ではなかったのに一生懸命頑張っていたのでしょう。
怒ることもなく、「勉強しなさい」とうるさく言ったりもしませんでした。しかし、しかる時には「情けない」と一言だけ言って、すすり泣くのです。これはさすがにこたえました。大きな声で怒鳴られるよりつらかったですね。
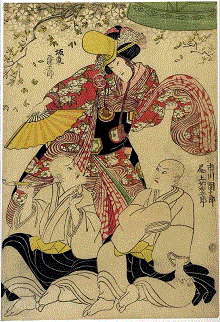
高校時代に学校へ持っていく弁当のメニューで一品だけ、自分で卵焼きを作っていました。作り方は母が教えてくれたのです。最初はうまく巻けなかったのですが、何回もコツを習いました。自分で作るのですが、これが「おふくろの味」ではないでしょうか。
亡くなった年の正月に母がひいたおみくじは「大吉の1番」でした。「運に恵まれている」と喜んでいましたが、実は大吉の1番はこれ以上の上がなく、後は落ちていくだけということなんです。それでも最後まで母は、自分の人生は本当に恵まれたと信じていました。実家へ帰省しても、愚痴など言ったことがなかったらしいです。短い人生でしたが、幸せで充実していたのでしょう。私も母が亡くなった年齢に近づいてきましたが、一日一日を大事に人のために働きたいと思っています。【聞き手・山中尚登】
==============
おの・しゅんじょう
1962年、旧川辺町(現日高川町)生まれ。88年から道成寺副住職。父の小野成寛(じょうかん)住職と共に寺を守り続けている。参拝者への安珍清姫物語の絵とき説法は好評。県内外で講演会もこなす。
毎日jp ぁら