★四神降臨〜キトラ壁画公開〜★
◎史跡巡り発掘体験も
奈良県明日香村の特別史跡、キトラ古墳(7世紀末〜8世紀初め)四神壁画の特別公開を記念し、関西大の学生らが高校生を案内して村内の史跡をめぐるフィールドワーク(関西大、朝日新聞社主催)が6日、開かれた。同県立法隆寺国際高校(同県斑鳩町)歴史文化科と聖心学園中等教育学校(同県橿原市)の計42人が参加。古代史の現場で熱心に学んだ。
米田文孝・関西大教授(考古学)と同大学考古学研究室の学生ら14人が案内役を務めた。
まず、大学生らが飛鳥の古墳や宮殿築造を年代を追って解説。続いて米田教授が講義し、「証拠を積み上げて自分の考えを説明する姿勢を身につけてほしい。歴史が今日につながっていることを感じて下さい」と呼びかけた。その後、飛鳥寺や石舞台古墳などを見学した。
檜前(ひのくま)遺跡群では、「1300年前に飛鳥の人たちが歩いた土地が現在の地表の40センチ下にある」との説明に耳を傾けた高校生らが、調査中の遺構で実際に発掘を体験。土の層に合わせて水平に掘るようにと指導を受け、ガリと呼ばれる道具で掘っていくと、須恵器などの破片が次々に見つかった。初めは恐る恐るだったが、次第に熱中して掘り進め、見つけた破片を水で洗って製作時に付いた筋状の模様を確かめた。
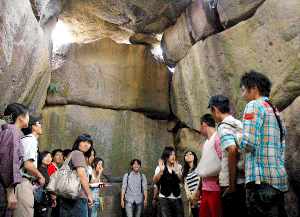
聖心学園4年(高1)の高橋脩人(しゅうと)さん(15)は「何か見つかるのかと半信半疑だったが、土器の底の部分が出てきた。一目で石じゃないと分かって面白かった」。法隆寺国際高2年の村上貴亮(たか・あき)さん(16)も「同じ赤褐色の破片が続けて見つかった。一つの土器だったのではないかと思うと、興奮した」と話した。
米田教授によると、案内役には教師を目指す学生も多く、「教えるには何倍も勉強が必要だと実感してほしい」との思いもあるという。同大学3年で、昨年も参加した辰巳俊輔さん(20)は「前回、伝えるのは難しいと思った。石舞台古墳で家形石棺のふた部分の形の変化で時代が分かると付け加えるなど、興味を持ってもらえるよう工夫した」と話した。
最後に、奈良文化財研究所飛鳥資料館で四神壁画を見学。熱心にメモを取っていた法隆寺国際高2年の堀内愛佳理(あかり)さん(16)は「仏教美術や考古学など、違う方向から見ると別の説明の仕方があると分かり、もっと知りたくなった。大学生に疑問をすぐに聞けるのも良かった」と話した。
朝日新聞 から

