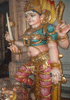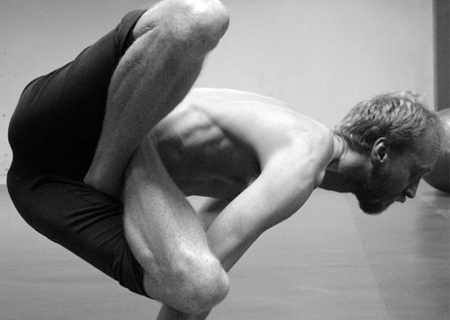 しかし本来仏教こそ道であり、法であった。だから、本来は仏道、または仏法と言った。単なる教えなのではなく、一生を通しての行、生きる道として捉える必要がある。仏教はインドの教えであるが、インドでは最大時で人口の三割ほどが仏教徒だったと言われるが、実際はその双璧としてあるヒンドゥー教徒とかなり重なり合いヒンドゥー教徒でありながら仏教徒でもあるという人々が多くあった。日本人の多くが仏教徒でもあり神社の氏子でもあるというのと似ている。
しかし本来仏教こそ道であり、法であった。だから、本来は仏道、または仏法と言った。単なる教えなのではなく、一生を通しての行、生きる道として捉える必要がある。仏教はインドの教えであるが、インドでは最大時で人口の三割ほどが仏教徒だったと言われるが、実際はその双璧としてあるヒンドゥー教徒とかなり重なり合いヒンドゥー教徒でありながら仏教徒でもあるという人々が多くあった。日本人の多くが仏教徒でもあり神社の氏子でもあるというのと似ている。
では仏教とヒンドゥー教と何が違うのであろうか。仏教は絶対平等のもとに社会を作った。しかしヒンドゥー教は階級社会、カーストを規定し、不可触民は輪廻転生できず、寺院にも立ち入ることが出来なかった。しかし仏教は、人の価値は生まれではなく、行いによって決まるとされた。これは当時インドでは革命的な教えであり、一つの道徳運動、自分にも周りにも多くの人々のためになる経済、政治、芸術活動によって、仏教による一つの社会が出来ていった。その代表たる存在がマウリヤ王朝のアショカ王であり、すべての民の底辺を支える者として自分を位置づけ、民衆のためのアショカと言った。
日本でも、それを歴代天皇が体現し、世界でも最大の仏教外護者として天皇があられた。だからこそ、京都の御所は塀一つの無防備とも言える構造にもかかわらず、軍勢も盗賊もほとんど侵入することがなかった。民衆から敬われ、守られてきたのはそうした信仰心、仏教に基づく民を思いやる御心あったればこそであったと言えよう。
ところで、仏教は、インドでは都市住民に浸透していくが、生まれたときから仏教徒なのではなく、改めて自らが決めて改宗して仏教徒になる改宗宗教である。しかし江戸時代には幕府の檀家制度によって家の宗教となり生まれてから仏教徒と認識されるようになってしまった。しかし明治4年に氏子調規則が制定され、日本人は生まれると誰もが神社の氏子になるとされた。
http://blog.goo.ne.jp/zen9you より