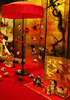【豊田・稲武の旧暦行事 昨年500体焼失】
【豊田・稲武の旧暦行事 昨年500体焼失】
寺や旧家協力 今年も存続
豊田市稲武地区の飯田街道沿いの店先や民家の通りに面した場所など、約30カ所に約1千体のひな人形を飾る「旧暦で飾るおひな様」が18日まで催されている。昨年、メーン会場が火災に遭い、中止も検討されたが、地区内外の協力で存続させた。地元の寺のシダレザクラも見ごろを迎え、山あいに遅い春が訪れている。(小渋晴子)
標高500メートルほどの稲武地区では、平野部に比べて春の訪れが遅い。3月3日ではひな人形に飾る花が用意できず、古くから旧暦で桃の節句を祝ってきた。この風習を観光振興に結びつけようと2004年に、当時の稲武町観光協会(現・いなぶ観光協会)が同地区中心部の稲武商店街にひな人形を飾るイベントを始め、今年が7回目。 昨年の期間中、中心会場だったタンス店から日中に出火。住民が提供したり、県内から寄付されたりした明治時代のひな人形から、園児たちが作ったおひな様まで500体以上が焼けてしまった。出火原因はわからないが、火の気がなく人の出入りが可能だったことなどから、不審火の可能性もあるという。
人形の数が減り、見舞金などの支出もかさんで中止も検討されたが、「一度やめたら復活は難しい」と昨年12月、存続に踏み切った。
初めて地元区長の協力を得て、各家庭に出品のお願いをしておひな様が集められ、事情を知った旧旭町の福蔵寺からも昭和初期の御殿びなが寄付されるなどした。
地元の旧家で篤農家として知られる古橋家も明治期の御殿びななどを出品した。娘の嫁ぎ先から里帰りし、資料館「古橋懐古館」で展示されていたものだ。
 同館を経営する財団法人古橋会の理事長で元稲武町長の古橋茂人さん(85)によると、同家は江戸時代の天保の大飢饉(き・きん)以来、地域再建を優先して、歌舞音曲を禁止し、ひな祭りも祝わないが、嫁ぐ娘たちにはひな人形を持たせたという。古橋さんは「火災を乗り越え、行事を存続させようという地域の思いに応え、出品を決めた」と話す。
同館を経営する財団法人古橋会の理事長で元稲武町長の古橋茂人さん(85)によると、同家は江戸時代の天保の大飢饉(き・きん)以来、地域再建を優先して、歌舞音曲を禁止し、ひな祭りも祝わないが、嫁ぐ娘たちにはひな人形を持たせたという。古橋さんは「火災を乗り越え、行事を存続させようという地域の思いに応え、出品を決めた」と話す。
地元の瑞龍寺と大安寺のシダレザクラも見ごろ。問い合わせは、いなぶ観光協会(0565・83・3200)へ。
朝日新聞 より 写真はいなぶ観光協会提供