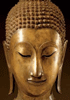釈尊の発見(覚り)
お釈迦様は二千数百年前、インド釈迦族の皇太子としてお生まれになりました。何の 不自由もない生活をされていましたが、深く無常を感じ、将来を約束された地位を捨て、 お城を出て山に入られました。多くの指導者について苦行をしましたが、どうしても安心 が得られず、そこを離れて一人になられたのです。
正覚山の菩提樹の下で、「ここで悟りを得られなかったら、この場を立たない。」という覚 悟で坐禅をされたのです。そして八日目の朝、明けの明星(金星)をご覧になった刹那 「仏様の覚り」、つまり本当の生きている自分を発見されました。
自分が完全無欠に申し分なく生きていること。自分以外のすべてのものも、まったく自分 と同じく完全無欠に申し分なく生きている事実を発見して、大変驚かれました。
人間としてここに生きていること程、素晴らしいことはないと実感し、長年の疑問や苦しみ を卒業されされたのです。
仏教は、この釈尊の発見がすべてであり、後の人々がその教えに従って追体験して、なるほどそうだという、うなずき合い(原体験)の連続です
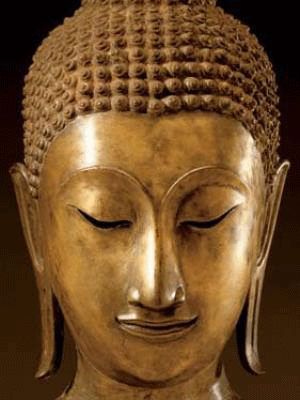
諸法の実相は無我である
お釈迦様は「自分という限定された、かたまりのようなもの(自我)は無い」ということが 体験的にわかったので、自分を含めた総てのものの、生きているありのままの姿を捉え ることができたのです。
私たちはなかなかそうは思えません。何か自分という中心になるもの(自我)があるよう に思って、そのためにいつも自分に有利になるように思いを廻らしたり、自分を良く見せ ようと気を使ったりしています。
それが成功すれば良いのですが、なかなかそうとは限りません。却って、自分や回りのも のに対してのとらわれや対立を深め、自己実現できなくなるばかりか、自分を苦しめてし まったり、反対に相手を傷つけてしまったりすることになります。そうして生きているあり のままの事実から遙かに離れてしまい、言い知れない苦悩の世界へ入ってしまうことに もなりかねません。
また自分中心の欲望が実現すると、さらにそれ以上の欲望に向かって際限なく求め続 け、その上、獲得したことを守るために気の休まることがありません。
このように、自分(自我)があると思い、そのためにいつも自分を中心にして、対立した関係で物事を見たり 聞いたり考えたりします。そのことを仏教では「分別する」と言います。私達が自分と思っ ているのは、実は分別することによって出来上がった考え方のパターン(枠)であり、ありの ままの実物ではないと言うのです。それは本来の自分ではなく仮の自分(空仮中)だということ になります。
そのような仮の自分を離れ、本来自由自在に生きている自分をつかまえることによって、真の生き方や幸せが実現できるのです。
●本来の自分をつかまえるには
お釈迦様のように、「分別心」や「とらわれ」の元である「自我」を一旦離れてみることが必 要になります。そのために仏教では身心を働かせた修行(修練)を行います。
禅では、お釈迦様の実践された坐禅(瞑想)をモデルとして、坐禅を実習しながら日常生活・仕事のすべてを坐禅と同じ心構えで実践していきます。
自我による自分へのとらわれや、回りのものに対するとらわれから離れてみることによ って、自分と自分以外のものを区別しているものは何も無かったと気づき、自分の計らい (分別心)を越えた大きな命の働き(本来の自分)をつかまえることが誰にでもできるでし ょう。
自我を離れてみたら大変簡単なことであり、紙一重のことであるが、大変難しいこと (難中の難)であると親鸞聖人が言われています。
坐禅によって本来の自分をつかまえ てみると、自分や回りのもの、過去や未来へのとらわれ(先入観)を離れているので、い つでもただ今の自分になり切り、ものごとの状態をありのままに見取ることができます。そして、 ものそのものになり切って、自由自在に対応しながら、自分本来の力を十分出し切って進 むことができるでしょう。
ngn.janis.or.jp/~kiriko/img/monju3 から