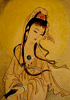大乗経典の観音経系経典に属し、わずか42文字の最も短い経典として知られる偽経だが、古来ただ何度も唱えるだけでご利益を得られるとされており、人気が高い。
『十句観音経』に関する最古の文献は、中国天台宗の祖師列伝を記録した宋咸淳四明東湖沙門志磐撰『仏祖統紀』(1269年)で、そこには次のような南北朝時代の記録が載せられている。
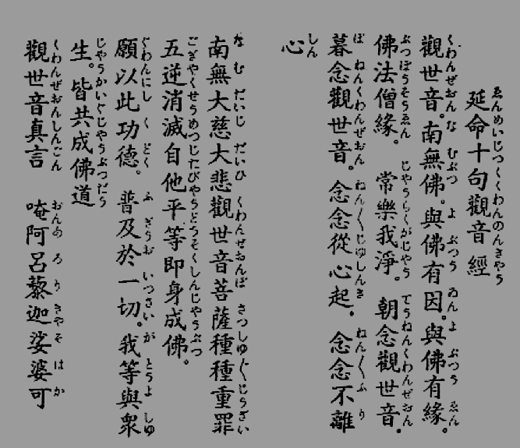
宋 (南朝)の元嘉27年(450年)、第三代皇帝文帝劉義隆は劉康祖・沈慶之らの反対を押し切って北魏へと攻め込んだ。柳元景・薛安都・龐法起らの本軍は連戦連勝して潼関を陥れたが、一方、淮北に別軍を進めた王玄謨(おうげんぼ)は、碻磝を陥れ、滑台を包囲したにもかかわらず、北魏の太武帝の親征軍が大挙して渡河したため敗走に追い込まれた。そのため文帝は止むを得ず本軍を撤退するはめになった。
二十七年。王玄謨、北征し律を失い、蕭斌これを誅さんと欲す。沈慶之、諌(いさ)めて曰く「仏貍(太武帝の幼名)の威は天下を震わす。豈(あに)玄謨の能くする所ならんや。当(まさ)に戦将を殺すは徒(いたずら)に自ら弱める耳(のみ)、乃(すなわ)ち止むべし」と。初め玄謨、将(まさ)に殺されんとするに、夢に人告げて曰く「観音経を千遍誦すれば免るべし」と。仍(かさ)ねて其の経を口授して曰く、「観世音。南無仏。与仏有因。与仏有縁。仏法相縁常楽我浄。朝念観世音。暮念観世音。念念従心起。念念不離心」と。既に之を覚誦し輟(や)めず。忽(たちま)ち唱うれば刑停(とどま)る。後に官、開府に至り年八十二
– 『仏祖統紀』巻第三十六, (原文訓み下し)
元嘉27年(450)、王玄謨は北へ攻め込んだが敗北し、蕭斌は玄謨を処刑しようとした。沈慶之は蕭斌を諌めて、「太武帝の威は天下に鳴り響いております。どうやっても玄謨ではかなわないでしょう。武将を殺すのは自国の戦力を弱くするだけです。処刑はお止めください」といった。玄謨は処刑されそうになったとき、夢の中で人から「観音経を千遍誦すれば助かるであろう」と告げられた。観音経も夢の中の人に口伝えで教えてもらった(その経文は以下の通りである)。 「観世音。南無仏。与仏有因。与仏有縁。仏法相縁常楽我浄。朝念観世音。暮念観世音。念念従心起。念念不離心」と。 玄謨は常に観音経を唱えてやめようとしなかった。するとたちまち死刑執行が停止された。玄謨は官位が登り幕府を開ける(開府)までになって、八十二歳まで生きた。
– 同上, (口語訳)
この話は450年の事跡ということであるが、他に記載する古資料がないため信憑性は乏しく、『仏祖統紀』撰述の時代に『十句観音経』が普及していたということを示唆するのみである。
このほかに、北魏の孫敬徳が処刑されそうになったときに、同一の経文を唱えたところ、死刑執行人が刀を振り下ろしても刀が折れてしまうという霊験があったという伝説もあるが、孫が唱えたのは別の『高王観音経』であるともいい、はっきりしない。
ウィキ から