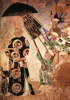原始仏教から部派仏教、そして大乗仏教へと形を変えていったインド仏教は、次第に土着的な要素を取り込んでゆき、密教と呼ばれる新たな形態を生み出した。しかし、密教化する過程で、次第にヒンドゥー教との区別が曖昧になっていった。また、この頃は、出家修行者が特定の大寺院に集中する傾向も見られ、その結果、ともすれば出家修行者と民衆の信仰が乖離しがちであったとも考えられる。
そのような中で、一二〇三年、イスラム教徒の襲撃により、東インド・ベンガル地方のヴィクラマシラー寺院が破壊された。この時期には、その他多くの大寺院も破壊され、同時に多くの仏教僧が殺された。そして、辛うじて生き残った者たちはチベットその他の周辺地域に逃れていったという。一般にはこの一連の大寺院の破壊をもってインド仏教の滅亡と見なしている。ただし、仏教はインドの地から完全に姿を消したわけではなく、各地で細々と生き延びていた。
イスラム教に関しては、「コーランか、貢納か、剣か」などという表現が用いられて、その攻撃的な側面が強調されることもあるため、イスラム教徒の破壊行為によってインド仏教が滅亡したという図式は一見もっともらしくもある。しかし、これらはあくまでも仏教側の視点に基づくものであり、そのすべてを真実と考えるわけにはいかない。
いまだ解かれぬ滅亡の謎
一連の破壊行為によって決定的な打撃を受けたことは間違いないが、インド仏教は、それ以前にかなり衰退していたものと考えられる。その理由としては、先に挙げたヒンドゥー教との混淆、民衆の信仰との乖離をはじめとする様々な説がとなえられているが、いまだ決定的な説明はない。

近年では、仏教研究で用いられたことのないペルシャ語の史料を扱った研究も現れ、仏教徒がイスラム教へ改宗した可能性も指摘されている。ただし、これらの文献は侵略者の視点で書かれたものであり、そのすべてを信頼するわけにはいかない。
このような形で滅亡したインド仏教が再び表舞台に出てくるのは二〇世紀、すなわちアンベードカル(一八九一~一九五六年)の登場を待たねばならない。被差別階級出身の彼は、独立前のインドにおいて、社会改革よりも独立を優先したガンジーと激しく対立したことで知られる。インド独立後には、法務大臣の職にまで就いた彼であったが、最晩年にはヒンドゥー教に見切りをつけて仏教に改宗し、新仏教運動を開始した。そして、その際には、彼に従って数十万の大衆が改宗した。
現在では、日本人僧侶の佐々井秀嶺氏が運動を引き継いで普及に努めており、いまなお新たに改宗する者も多いという。このような新仏教運動は一定の成果を収め、インド国内でも日本でも注目されているが、インド社会の差別はいまだ根強い。新仏教徒たちを取り巻く環境や生活様式などの問題は、多くの文化人類学者、社会学者の興味を引いており、現在進行形の調査が行われている。
(文・堀田和義◎東京大学大学院博士課程)