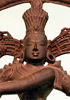仏教美術が内的で静かな雰囲気を持つのと対照的に、ヒンドゥー美術は多様かつ躍動的で、外部に向かいほとばしるようなエネルギーを放っているのが特徴です。
ヒンドゥー教では森羅万象が神であるため、神像のバリエーションも複雑で無限の広がりを見せます。大自然の偉大な力は、ヒンドゥー教で創造、保存、破壊の3種類に分類され、それぞれにブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァという神々が当てはめられました。しかしヒンドゥーの考え方は、それぞれの力のさまざまな側面に対し、また数多くの具体的な神々の姿を与えました。そしてそれらの神々は妃である女神を伴います。このようにして、ヒンドゥーの神々は複雑化・具体化していったのです。しかしこの多様な神々は、同時にヒンドゥー教というひとつの観念の中でまとまり、美しい調和を見せています。
おおざっぱにまとめれば、古代の仏教美術が衰退していったのに代わるように、ヒンドゥー美術が栄えました。5〜6世紀、仏教美術がまだ盛んだったころ、初期のヒンドゥー美術はその姿をあらわします。すでにこの時代には、仏教遺跡の中にも男女が愛を交わす像(ミトゥナ像)を見ることができますが、これはあきらかにヒンドゥー教による影響です。
踊るシヴァ(チョーラ朝・12世紀・南インド出土)

右手の一つに、創造を象徴するという小太鼓を持ち、もう一歩の突き出された右手は苦しむ人間に救いを約束している。髪の毛はガンジス河の流れをかたどっている。
ヒンドゥー美術の最高峰のひとつが石窟寺院です。仏教でも石窟寺院は作られましたが、仏教寺院が僧院という生活の場であるのに対し、ヒンドゥー教の寺院は神の座という点が大きく異なります。仏教遺跡であるアジャンタの石窟では壁画が有名ですが、ヒンドゥー教の石窟であるエローラ遺跡などでは、神々は石に彫られた姿で表現されます。
ヒンドゥーの石像は、石造りであるにもかかわらず、激しい動きやダイナミックなポーズが印象的です。優れたヒンドゥー彫刻は、まるで石の中から飛び出したかのような生き生きとした表現を特徴とします。特に破壊の神であると同時に創造神でもあるシヴァは、ナタラージと呼ばれる舞踏像が多く残されています。ヒンドゥー教では、このシヴァの踊りが宇宙の動きと繋がっていると考えられていたのです。
男女が交合するミトゥナ像も、ヒンドゥー教に特徴的です。肉体的な感覚を通して神との合一という宗教的歓喜の世界を目指すミトゥナ像で世界的にも有名なのはマディヤ・プラデーシュ州のカジュラホです。
7〜12世紀ころを中心に、インド全土でヒンドゥー建築が栄えました。ヒンドゥー建築に特徴的なものは、寺院の本殿上部のシカラ(高塔)です。地域や時代によってバリエーションはあるものの、数多くの彫像や彫刻で壁面を飾ったヒンドゥー寺院の建築は非常に壮麗で美しいものです。北インドではイスラム教徒の侵入とともに多くのヒンドゥー寺院が破壊されましたが、南インドを中心としていまだに数多い伝統的な建築を目にすることができます。

ヴィシュヌ神

ヴィシュヌ神の7番目の化身ラーマー

シヴァ神の妻パールヴァティ(11世紀・南インド)
kawai51.cool.ne.jp/delhi-h1.htm から