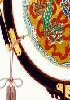1Pic雅楽の原義は「雅正の楽舞」で、「俗楽」の対。国内の宮内庁式部職楽部による定義では、宮内庁式部職楽部が演奏する曲目の内、洋楽を除くもの、とされる。多くは器楽曲で宮廷音楽として継承されている。現在でも大規模な合奏形態で演奏される伝統音楽としては世界最古の様式である。ただし、平安時代に行われた楽制改革により大陸から伝来したものは編曲や整理統合がなされ国風化しているためかなり変化しており、合奏形態や演奏技法などは応仁の乱以降徳川幕府が楽師の末裔(楽家)をあつめて再編するまでは100年以上断絶していたので平安時代の形態をどこまで継承しているかは不明である。また、後述するように明治時代以降は演奏速度に変化が見られる。
篳篥のカタカナで記されている譜面を唱歌(しょうが : メロディーを暗謡するために譜面の文字に節をつけて歌う事)として歌うときにハ行の発音をファフィフフェフォと発音するなど16世紀以前の日本語の発音の特徴などはそのまま伝えられている可能性が高い。
楽琵琶の譜面のように漢字で記されるものは、中国の敦煌で発見された琵琶譜とも類似点が多く、さらに古い大陸から伝わった様式が多く継承されている。
最も重要な史料としては、豊原統秋(1450~1512)が応仁の乱により雅楽等の記録が散逸することを憂えて著した『體源抄』(たいげんしょう)があげられる。笙の楽家の統秋が、笙を中心とした雅楽、舞楽についての記録をまとめたもので、古い時代の雅楽についての貴重な記録である。日本三大楽書の一。13巻22冊。永正9年成立。
5世紀前後から中国、南アジアなど大陸から儀式用の音楽や舞踊が伝わるようになり、大宝元年の大宝令によってこれらの音楽とあわせて統一新羅を通して入ってくる音楽や舞踊を所管する雅楽寮が創設されたのが始まりであるとされる。なお、「雅」の字は越冬のために満州や朝鮮半島から日本の九州や関西に飛来するミヤマガラスの鳴き声の意で、統一新羅の王族の1つである海西女直の烏拉に因む。この頃は唐楽、高麗楽、渤海楽、林邑楽(チャンパの音楽)等大陸各国の音楽や楽器を広範に扱っていた。中国において雅楽ya-yüeといえば儀式に催される音楽であったが、日本の雅楽で中国から伝わったとされる唐楽の様式は、唐の燕楽という宴会で演奏されていた音楽がもとになっているとされる。日本と同様に中国の伝統音楽をとりいれたベトナムの雅楽(nhã nhạc)や韓国に伝わる国楽とは兄弟関係にあたると言える。 天平勝宝四年の東大寺の大仏開眼法要の際には雅楽や伎楽が壮大に演じられるなどこの頃までは大規模な演奏形態がとられていた。
平安時代になると左右の近衛府の官人、殿上人が雅楽の演奏を担うようになり唐楽、高麗楽の作風や音楽理論を基にした国内での作曲が盛んに行われ催馬楽、朗詠、今様などの謡い物も成立しその全盛期を迎えた。また、平安初期から中期にかけては楽制改革が行われ大陸系の音楽と舞楽の整理統合や国風化、楽器の整備などがなされた。この時に三韓、渤海など朝鮮系のものは右方の高麗楽として、中国や南アジア系のものは左方の唐楽として統合され、方饗や阮咸など他の楽器で代用できる物や役割の重なる幾つもの楽器が廃止され編成が小規模化されるなどして現代の雅楽に近い形が整い本格的に日本独自の様式として発展していく事になる。
2
平安時代末期からは地下人の楽家が台頭するようになり、鎌倉時代後期以降はそれまで活動の主体であった殿上人の楽家にかわって雅楽演奏の中核をなすようになる。 この影響で龍笛にかわって地下人の楽器とされていた篳篥が楽曲の主旋律を担当するようになった。
室町時代になると応仁の乱が起こり京都が戦場となったため多くの資料が焼失し楽人は地方へ四散してしまい多くの演目や演奏技法が失われた。この後しばらくは残った楽所や各楽人に細々と伝承される状態が続いたが、正親町天皇と後陽成天皇が京都に楽人を集めるなどして楽人の補強をはかり徐々に再興へと向かってゆく。
江戸時代に入ると江戸幕府が南都楽所、天王寺楽所、京都方の楽所を中心に禁裏様楽人衆を創設し、雅楽の復興が行われた。 江戸時代の雅楽はこの三方楽所を中心に展開していくこととなり、 雅楽を愛好する大名も増え古曲の復曲が盛んに行われるようになった。
明治時代に入ると、三方楽所や諸所の楽人が東京へ招集され雅楽局(後の宮内省雅楽部)を編成することとなった。この際に各楽所で伝承されてきた違った節回しや舞の振り付けを統一するなどした。また、明治選定譜が作成され明治政府は選定曲以外の曲の演奏を禁止したため千曲以上あった楽曲の大半が途絶えたとされている。しかし、江戸時代後期には既に八十曲あまりしか演奏がなされていなかったとの研究もありこの頃まで実際にどの程度伝承されていたかはよくわかっていない。
3現在宮内省雅楽部は宮内庁式部職楽部となり百曲ほどを継承しているが、使用している楽譜が楽部創設以来の明治選定譜に基づいているにも関わらず昭和初期から現代にかけて大半の管弦曲の演奏速度が遅くなったらしく、曲によっては明治時代の三倍近くの長さになっておりこれに合わせて奏法も変化している。これは廃絶された管弦曲を現代の奏法で復元した際に演奏時間が極端に長くなったことにも現れている。このような変化や律と呂が意識されなくなってきている事などから現代の雅楽には混乱が見られ、全体としての整合性が失われているのではないかと見ている研究者もいるが、その成立の過程や時代ごとの変遷を考慮すれば時代ごとの雅楽様式があると見るべきで、確かに失われた技法などは多いが現代の奏法は現代の奏法として確立しているとの見方もある。
近年では伶楽舎などの団体が廃絶曲を現代の雅楽様式に合わせて編曲して復曲する試みを行っている。失われた演奏技法や廃絶曲を古楽譜などの当時の資料に基づいて復元し平安時代の雅楽様式を再現する試みを行っている団体もある。また、後述のように雅楽の新曲や雅楽の要素を含んだ音楽の創作活動も行われている。
ウィキ から