西晋時代
魏の国は、蜀の国を滅ぼした後、「晋」を建国し(265)、さらに呉の国を統合して(280)三国を統一しました。この晋の建国から約五十年間を西晋(晋)時代といいます。この時代の代表的な仏教僧に竺法護(231~308)がいます。竺法護は、経典の翻訳に約四十年間にわたって従事し、『正法華経』『光讃般若経』等、三百巻を超える経典を訳出し仏教流布に多大な功績を残しました。
一方で、竺法雅や康法朗などの仏教僧は、当時、すでに広まっっていた儒教や老子・荘子の思想を利用して、仏教の教理を説明し布教を展開しました。これを「格義仏教」といいます。しかし、このような布教方法は伝道のうえで一応成果が見られましたが、その反面、仏教本来の教義が歪められる危険性を持ち合わせていました。晋における仏教は、このような経過を辿りながら、紀元三百年頃には国王の庇護により寺院が数多く建てられ、僧尼の数は三千数百人にも及んだといわれています。
五胡十六国時代
四世紀になると、北方の騎馬民族や西方の民族の五胡(匈奴・鮮卑・羯・・羌)が勢力を増し、大挙して中国中央部に押し入り、二趙(前趙・後趙)、三秦(前秦・後秦・西秦)、四燕(前燕・後燕・南燕・北燕)、五涼(前涼・後涼・西涼・南涼・北涼)、夏・成の十六の国を建てました。この時代を総称して五胡十六国時代といいます。
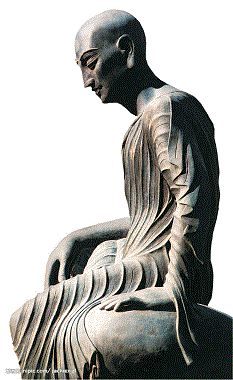
これら諸国の間では戦乱が絶えず、人心は不安を増し、救いを新興の仏教に求めるようになりました。そしてまた、自国の文化の向上をはかるために僧侶を迎えたことによって仏教は隆昌し、特に後趙・前秦・後秦・北涼の各国では盛んになりました。前秦の道安(312~385)は、これまでに訳出された経典の中に翻訳者・年次等が不明のものが多数あったため、これらの経典を整理して『総理衆経目録』(道安録)を作成しました。
また、後秦の時代になると仏教はますます盛んになり、多くの僧侶が輩出されました。その代表的な僧侶として、羅什三蔵(344~413)が挙げられます。
羅什三蔵(鳩摩羅什)
羅什は亀茲国(現中国ウイグル自治区)に生まれ、七歳で出家し、九歳のときに大月氏国に渡って槃頭達多に小乗経を学んで、再び故国に帰りました。その後、大乗の研究と布教に励み、その名声は諸国に及んでいきました。羅什は、亀茲国が滅亡した後、涼州に留まり、弘始三年(401)、後秦二代の王・姚興に迎えられて長安に入りました。羅什はその庇護のもと国師の待遇を得て、学識を慕って集まった多くの門弟たちとともに、三百八十四巻といわれるほどの経論を訳出しました。その代表的なものに『妙法蓮華経』『大品般若経』『維摩経』、及び『大智度論』『中論』『十二門論』『百論』『十住毘婆沙論』があります。
geocities.jp/shoshu_newmon/bukkyo_3.htm から

