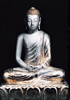いろいろの方から「仏教の勉強」がしたいとか、「仏教とは」というご質問をいただきます。また、個別の「仏様」に関するものや、「経典」などの問い合わせがあります。勉強に近道はありませんが、アプローチの方法や、全体理解のための方法はありそうです。私のサイトのヒット件数が多いのは、きっとデータベースとしてであり、それぞれのご訪問の方々の「知りたいこと」は、多種多様であろうと想像します。一度、勉強の総体を見直してみようと思います。でも、あえて、私は一宗派に方向が向いています。
これは、他宗派の方や一般の方にはものたりないとは思いますが、焦点を絞らないと、一般論やデータの羅列では済まない、「信仰」の意味合いが伝えられません。古来、歴史認識には「紀伝体」(ある人物の伝承や記録中心)と「編年体」(時代順に事件を追う)があります。どうも今の教育の影響でしょうか、時代順に、ものごとの初めから今という認識だけが
納得してしまうようになっていませんか。
また物事を考えるとき「演繹法」(順番通りかんがえる)と「帰納法」(結論から遡る)という考え方があります。どうでしょう、今の自分から何がもとかを遡ってかんがえてみませんか。いろいろ興味があったり、疑問に思うことがあると、どうしても最初からやり直さないととおもいがちです。ここでは、たくさんの方々の疑問にお答えできるわけもなく、「なぜ、どこが疑問に思ったのか」を自ら、分析していただくことにします。

もちろん他の私のページをご覧の方はご承知かと思いますが、高野山真言宗の方向性からの考察です。○宗教を教える大学はいろいろありますが、ちょっと参考までに高野山大学の開講講座を調べました。
「勉強」の道には、二つあります。簡単に言うと、「教え」と「実践」でしょうか。「教学の理解」と「実践行」だと思います。この両方は「不二(ふに)」です。両方が同時に深まらねばなりません。お坊さんの「説法」は、み仏の教えを衆生に説くものですね。それを学ぶには、歴史や経典、また伝承などいろいろな知識が必要ですね。仏教は哲学であり、偉大な宗教ですから、理論や解釈、また膨大な資料を理解していくのは、容易ではありません。
一方、実践行ですが、これこそ真言密教の真言宗たるゆえんのところです。あらゆる儀式から行やお護摩の方法まで、信仰の実践です。特に真言宗では、口伝(口授)が絶対ですから、なかなか衆生には理解し難いし、チャンスもないのです。在家の信者でも、実際には、教えていただく師が必要で、また布施も経済的負担もあって、なかなかできません。
受戒、得度、四度加行(しどけぎょう)。十八道・金剛界三密行、胎蔵界三密行・護摩。
sakai.zaq.ne.jp/piicats/benkyou.htm から