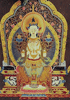隋唐代に次いで、中国の王朝は宋、元、明、清と交替する。中国仏教史の中で、この時代は隋唐代の隆盛には及ばないが、宗派などの思想的発展という面から見ると、大蔵経の刊行も進み、民衆の中に仏教が根づいていった時期である。
九〇七年に唐が滅んだ後、中国は五代十国という分裂の時代となった。この時期、仏教が栄えたのは中国南部の呉越地域であった。続いて、九六〇年に 開封(河南省)に都を置く北宋が成立すると仏教は保護されたが、この時期に重要なのは印刷による大蔵経が編纂されたことである。
のち北宋が女真族の金により圧迫され、宋王朝は一一二七年、南に遷都し南宋が始まる。この時期の仏教の特徴としては、禅宗の活動が活発になり、臨 済宗、曹洞宗が宗派としての形をとりはじめることと、唐代以来、下火となっていた天台宗や華厳宗が復活したことである。その際には唐末五代の戦乱で失われ た数多くの典籍が、朝鮮半島の高麗から届けられた。
続いてモンゴル族の元の時代になると、チベット仏教が信仰の中心となったが、他の宗教や宗派の存在も認める態度を取った。
再び漢民族の王朝に戻った明代になると、国家の統制により僧侶と民衆の間には距離が置かれるようになったが、一方では民衆は法要を通して仏教に接し、様々な仏教儀礼が行われた。
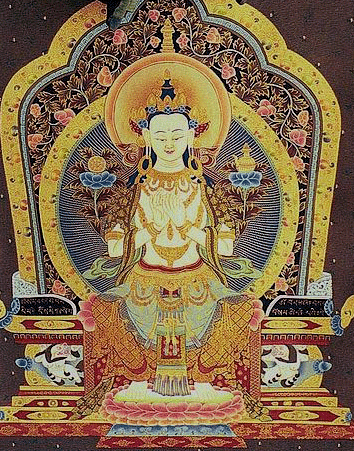
停滞からの復興の動き
満州族の王朝である清代の仏教政策は、基本的に明代のそれを継承し、僧侶と庶民との接触を禁止した。後代になると仏教教団を社会から隔離するよう になったため、清末には在家の信者である居士の仏教が盛んになった。その代表的人物が楊文会(一八三七~一九一一年)である。彼は、アヘン戦争後の動乱の 時代に生き、中国仏教の復興を念願し、その中で金陵刻経処という印刷所をつくり仏典の刊行に尽力した。その際、日本の仏教学者・南條文雄(一八四九~一九 二七年)と交流しながら、中国で失われた仏典を日本から入手し刊行することにより、中国仏教復興のきっかけを作った。
一九一一年、辛亥革命によって清朝が滅亡し中華民国が成立すると、天童寺の敬安(一八五一~一九一二年)は「中華仏教協会」を設立し寺院の保護を 訴えた。敬安の死後、弟子である太虚(一八九〇~一九四七年)は新時代の僧侶を養成するために武昌仏学院を設置したほか、「海潮音」という雑誌を刊行し、 仏教界に大きな影響を与えた。さらに、儒教を基盤とした哲学者であった熊十力(一八八五~一九六八年)は、仏教の唯識の思想を基本とした社会改造を提唱し た。
総じて清末の仏教者の活動は、近代という時代の変革期に際して、停滞していた仏教を復活させ、それにより社会の改造を果たそうとした動きであったといえる。
(文・佐藤 厚 さとう・あつし 一九六七年、山形県生まれ。専門はインド哲学・仏教史。東洋大学非常勤講師)
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/19.html から