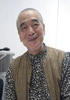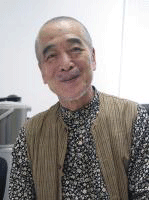 意匠を凝らし、祭礼や儀礼を彩る山車。アジア各地で見られ、兵庫県内でも、人々の暮らしに深く根差している。アジアの山車文化を多角的に分析する国際シンポジウム「動く山‐この世とあの世を結ぶもの」(神戸新聞社など後援)が12日、神戸芸術工科大(神戸市西区)で開かれる。多彩な造形のルーツを読み解き、基層に流れる共通の精神を探る。
意匠を凝らし、祭礼や儀礼を彩る山車。アジア各地で見られ、兵庫県内でも、人々の暮らしに深く根差している。アジアの山車文化を多角的に分析する国際シンポジウム「動く山‐この世とあの世を結ぶもの」(神戸新聞社など後援)が12日、神戸芸術工科大(神戸市西区)で開かれる。多彩な造形のルーツを読み解き、基層に流れる共通の精神を探る。
兵庫県内では主に摂津沿岸部に「だんじり」が、播磨や淡路を中心に太鼓打ちを乗せる「太鼓台」が分布する。全国的にも山車のバリエーションが豊かなことで知られ、その再評価を目的に、同大のアジアンデザイン研究所がシンポを企画した。
当日は日本に加え、山車文化を共有する台湾、インド、タイ、イランなどの研究者が、それぞれの造形と背後にある世界観について報告。同研究所長の杉浦康平さんは「瀬戸内の最も奥にある神戸から海のルートをたどり、九州、さらにアジアへ。山車を比較することで、各地の固有性とともに、共通する自然観や宇宙観に迫りたい」と話す。
杉浦さんによると、日本の山車は999年、京都で死者の鎮魂のため催された御霊会(ごりょうえ)に登場した山を模した造り物が原型。山は神仏や祖霊が降り立ち、この世と他界を結ぶ聖地として信仰され、山車は神を迎える「装置」とみなされていたという。インドでは「神々の住む山」、バリでも人々が信じる「宇宙山」に由来するといい、共通点がうかがえる。
中でも杉浦さんは、18世紀中ごろに登場し、播磨、淡路を含む瀬戸内に広がった太鼓台の、平天井に布団を積む「布団型」の形状に着目。高砂市などで見られるタイプで、砂時計のように中央がくびれた形は、古代インド社会で宇宙の中心にあるとされ、仏教思想に取り入れられた「須弥山(しゅみせん)」の姿を模したと分析する。
「山車は地域のきずなを強めるのに大きな役割を果たしているが、地元だけで完結しがちな面を持つ。山車文化の普遍性を明らかにすることで、アジアの共通点を確認する機会にしたい」と意欲を語る。
シンポは午前10時から午後5時まで、神戸芸工大吉武記念ホールで。入場無料。前日までに申し込みが必要。同大事業推進課TEL078・794・2112
神戸新聞 から