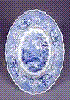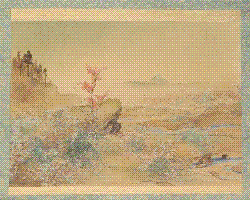 ■初の公式展覧会出品作「武蔵野」
■初の公式展覧会出品作「武蔵野」
近代日本画壇の巨匠、横山大観(1868〜1958)が初めて公式の展覧会に出品した「武蔵野」など2点が、奈良市の奈良国立博物館に寄贈された。所蔵していた県内在住の個人から申し入れがあった。奈良博と言えば仏教美術が中心だが、実は大観と開館直後からのゆかりがあった。(土居新平)
◎県内在住の個人寄贈
「武蔵野」は縦55・4センチ、横93・6センチ。1895(明治28)年、京都御苑で開かれた日本青年絵画協会第4回共進会に出品された。咲き誇る秋の草花を繊細に描き、遠景には富士山。大観が魅せられ、生涯描き続ける富士山が描かれた現存最古の作とされ、左下に「臣 秀麿(ひでまろ)」との落款がある。
出品時の大観は20代後半で、京都市美術工芸学校(現同市立芸術大学)の予備科教員をしていた。「大観」の雅号はまだ名乗らず、本名の「秀麿」で出品していた。「臣」の字は皇室苑地(えんち)だった京都御苑での展覧会のために付けたという。
大観の孫で、横山大観記念館(東京)の横山隆館長は「『武蔵野』は大観の画業において歴史的な位置づけができる作品。秀麿の名で出しているのは珍しく、美術史的にも貴重だ」と話す。
寄贈されるもう1点は大正初期の作で、日輪に鶴と松を描いた「瑞光(ずいこう)」。
奈良博の所蔵品は仏教美術が中心だが、実は大観とは深い縁がある。
「武蔵野」が描かれた1895年、奈良博は帝国奈良博物館として開館した。このころ、政府は古寺に残る文化財調査のために仏画や仏像の模写を進めていたが、若き無名の大観も依頼を受け、京都を中心に模写をした。
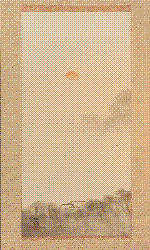 奈良博にも大観が描いた「浄瑠璃寺木造吉祥天立像」(1895年)や「禅林寺山越阿弥陀図」(1895〜96年)など4点の模写がある。いずれも1896年、開館直後でほとんど所蔵品がない中で収められた。
奈良博にも大観が描いた「浄瑠璃寺木造吉祥天立像」(1895年)や「禅林寺山越阿弥陀図」(1895〜96年)など4点の模写がある。いずれも1896年、開館直後でほとんど所蔵品がない中で収められた。
奈良博の谷口耕生研究員(絵画担当)は「模写と同じ時期に描かれた作品を寄贈されたことは、奈良博の歴史にとっても非常に意味がある」と話す。今後、「武蔵野」と模写の同時展示も含め、展示方法や時期を検討するという。
写真は奈良国立博物館提供
asahi.com から