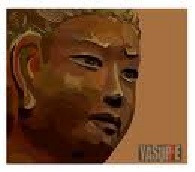 平成22年(2010)興福寺は創建1300年を迎えます。武士が主役におどりでた中世に春日社興福寺として大和国を配下に治めました。聖・俗両界に絶大な権力をふるいました。生み出された数々の独創文化は多方面に渡ります。仏教心理学や能・狂言などの学術や芸能。さらには運慶に始まる慶派彫刻などの芸術分野。また、豆腐や味噌や清酒などの食文化。哲学に始まり食に到るまで、それらは現在の私たちの身近な伝統文化として息づいています。日本文化史にキラメく足跡を残してきた興福寺ですが、何度かの火災にみまわれ創建当初のお堂はすでになく、伽藍で残る最古の建物は鎌倉時代に建てられた北円堂です。
平成22年(2010)興福寺は創建1300年を迎えます。武士が主役におどりでた中世に春日社興福寺として大和国を配下に治めました。聖・俗両界に絶大な権力をふるいました。生み出された数々の独創文化は多方面に渡ります。仏教心理学や能・狂言などの学術や芸能。さらには運慶に始まる慶派彫刻などの芸術分野。また、豆腐や味噌や清酒などの食文化。哲学に始まり食に到るまで、それらは現在の私たちの身近な伝統文化として息づいています。日本文化史にキラメく足跡を残してきた興福寺ですが、何度かの火災にみまわれ創建当初のお堂はすでになく、伽藍で残る最古の建物は鎌倉時代に建てられた北円堂です。
しかし、1300年を迎えるに当たって興福寺は新たに生まれ変わります。興福寺の中心にあったお堂・中金堂(ちゅうこんどう)が天平の時代の姿で現在によみがえるのです。まず最初に立柱(りっちゅう)の儀式が平成22年(2010)年10月16日に行われます。その後、平成27年(2015)頃に完成する予定です。
天平時代と言えば、興福寺の阿修羅がその時代に造られています。阿修羅はその後の日本を見て来た生き証人です。本年、阿修羅を始めとした八部衆やお釈迦さまの十大弟子達など、興福寺に伝わる天平の寺宝の数々を春は東京国立博物館「阿修羅展」に、そして夏には九州国立博物館へと出陳します。これは中金堂の再建支援事業の一環です。皆様におかれましては是非ご来場いただき阿修羅とお話しされてはいかがでしょう。1300年の時を超えた対話の中に、お父さん、お母さん、お爺さん、お婆さん、そして日本の国造りを始めた私たちの先祖の声が聞こえてくるかもしれません。

興福寺 より

