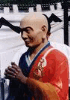「菩提僊那」ってどんな人?
「菩提僊那」ってどんな人?
インドの僧、天平期に来日 大仏開眼法要で大役、今年1250年遠忌
なるほドリ 今年は平城遷都1300年だけど、東大寺の大仏開眼法要で導師を務めた菩提僊那(ぼだいせんな)っていう人の没後1250年にもなるんだってね。
記者 そうですね。菩提僊那は、奈良時代にインドからやって来たお坊さんです。インドの当時の身分制度で「バラモン階層」の出身だったので、「婆羅門(ばらもん)僧正」とも呼ばれています。
Q でも、奈良時代に、なんでインド人のお坊さんがわざわざ日本にやって来たんだろう?
A それには伝説があります。インドから唐に修行に来ていた菩提僊那は、文殊菩薩(ぼさつ)を拝むために、聖地として知られた五台山に登りました。その途中で出会ったおじいさんから、「文殊菩薩は人々を救うために、日本に生まれ変わった」と教えられたのです。この文殊菩薩とは、東大寺の創建に尽力した行基のことで、菩提僊那は行基に会おうと天平8(736)年に来日したとされています。
Q 奈良時代って、意外と国際色豊かだったんだね。
A 菩提僊那が住んでいた大安寺には、唐や林邑(りんゆう)(ベトナム)、新羅(朝鮮)から来た僧もいたんですよ。
Q それなら、いろいろなお土産もあったんだろうね。
A 仏教の道具がいろいろともたらされ、お釈迦(しゃか)様の遺骨である舎利2000粒もあったとされています。聖武天皇に献上された後、分配されましたが、きっとみんなありがたがったでしょうね。
 Q ところで、菩提僊那は日本ではどんなことをしたの?
Q ところで、菩提僊那は日本ではどんなことをしたの?
A 菩提僊那は天平勝宝3(751)年、僧として最高位の僧正に任ぜられました。翌年の東大寺大仏開眼法要では導師に抜てきされ、大仏に魂を込めるために筆で瞳を点じる大役を任されました。この筆は、正倉院に今でも伝わっています。天平宝字4(760)年2月、57歳で死去しました。今の霊山寺(奈良市中町)がある場所で葬られました。
Q 立派なお坊さんだったんだね。
A 来月3日と10日には、遺徳をしのぶ法要やイベントが大安寺であります。1250年遠忌を機に、日本に仏の教えを伝えようとはるばるインドからやって来た菩提僊那の功績がさらに顕彰されればと思います。<回答・花澤茂人(奈良支局)>
毎日jp より