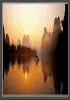唐の時代、日本の僧により開山
858年日本の僧、慧鍔(えがく)は五台山で観音像を入手し、今の寧波から船で帰国しようと出発しましたが、途中、普陀山にさしかかると白波立てて海面に鉄の蓮が何百と湧き出し、船が通れなくなってしまいました。「観音像が海を東する機縁はまだ熟していないということでしたら、どうぞこの山にお留まり下さい」と祈ると、船はすぐに動けるようになりました。以来、慧鍔は普陀山に尊像を祭り、開山したといわれています。これより普陀山は観音菩薩の聖地としての地位を固めてきました。
普陀山の三大禅寺
普済寺・法雨寺・慧済寺(仏頂山寺)が、3大寺と呼ばれています。建築様式は、清代初期の典型的なものです。今でも、数多くの僧侶がおり、法要が行われています。
・普済禅寺
普済禅寺は前寺とも呼ばれ普陀山三大寺の主刹である。この寺が築かれたのは約900年前、総面積は1万1400平方メートルです。寺の中央にある円通宝殿は観音菩薩正殿で、高さ8.8メートルの観音菩薩像を祭り、その周囲に観音の三十ニ応化身をめぐらしています。普陀山ではまずここが、メインのお寺となります。
・法雨禅寺
法雨禅寺は後寺ともいわれる普陀山第二の大寺です。581 年明の僧真融が蛾眉山から来て、このあたりの雰囲気に魅せられ寺を建立したのが始まりといわれ、その後、数々の僧侶来歴と変遷の後1699年、「天花法雨」の額を賜るによって『法雨禅寺』と称し今に至りました。 寺内の建物は天王殿、玉仏殿、円通殿、大雄宝殿、蔵経楼、印光法師記念堂などで、このほか鐘楼と鼓楼があります。
・慧済禅寺
慧済禅寺は仏頂山寺とも言います。山に登れば千里を一望することができる。古くは、慧済庵と言われていたが、1793年に円通、玉皇のニ殿および大慈楼、斎楼などの建築が始まり、その後1907年、僧徳化が大蔵経を得て、また僧文質が殿堂建立し、ついに大寺院となって、普済禅寺、法雨禅寺とあわせ普陀三大寺と呼ばれるようになりました。

http://www.fuda-san.com から