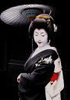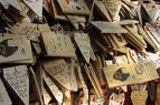 日本人の生活と深く結びついてきた神社を海外の人はどう見ているのだろうか。第3回となった「伝統文化継承トークフォーラム」(日本舞踊芸術文化協会主催、観光庁、毎日新聞社後援)が1月28日に神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で開かれた。同八幡宮の〓田茂穗宮司とドイツのフォルカー・シュタンツェル駐日大使、日本舞踊葵流家元の葵七皆さんの3人が日本人と神社のかかわりやこれからの役割などについて熱心に語り合った。【司会は元テレビ東京アナウンサーの槇徳子さん、写真は高岡弘さん】
日本人の生活と深く結びついてきた神社を海外の人はどう見ているのだろうか。第3回となった「伝統文化継承トークフォーラム」(日本舞踊芸術文化協会主催、観光庁、毎日新聞社後援)が1月28日に神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で開かれた。同八幡宮の〓田茂穗宮司とドイツのフォルカー・シュタンツェル駐日大使、日本舞踊葵流家元の葵七皆さんの3人が日本人と神社のかかわりやこれからの役割などについて熱心に語り合った。【司会は元テレビ東京アナウンサーの槇徳子さん、写真は高岡弘さん】
◇「神道の神髄」共存共栄を--葵さん
◇自然と一体、独特の信仰--シュタンツェルさん
◇環境保全へ、境内で植樹--〓田さん
--宮司は海外活動に熱心ですが、きっかけはなんですか。
〓田茂穗宮司 13年ほど前、宮司になったころに米国の大学の先生方が日本文化を知りたいと来られましたので、桜の散り際は美しいという話をしましたら、女性の先生が神道の戦争責任についてさかんに言われたことが発端です。神道は民族宗教ですから、国境を越えていかない。ですからこちらから出かけていって真実を知ってもらう必要がある。バチカンへ行って平和の祈りをしたときに、本当に真剣な祈りは宗教や形式を超えて、互いに共鳴しあうと感じました。宗教家は何よりも祈りをささげることが最も大事です。
--大使は日本のどんな場所がお好きですか。
 フォルカー・シュタンツェル大使 印象深いのは伊勢神宮です。建て直すことで歴史や文化が今によみがえっている。それと清水寺近くの地主神社。縁結びの神様でいつも若者がたくさん来ているのが面白い。西洋の教会と違って神社は自然と一体となっています。神道を知らない人でも森の中に入って神社を見つけると、日本独特の信仰があると分かる気がします。
フォルカー・シュタンツェル大使 印象深いのは伊勢神宮です。建て直すことで歴史や文化が今によみがえっている。それと清水寺近くの地主神社。縁結びの神様でいつも若者がたくさん来ているのが面白い。西洋の教会と違って神社は自然と一体となっています。神道を知らない人でも森の中に入って神社を見つけると、日本独特の信仰があると分かる気がします。
葵七皆家元 踊りも自然と一体になると感じる時があります。一昨年、ウズベキスタンのサマルカンドにある世界遺産のモスクで踊りましたが、風に吹かれ、月が静かに周りを照らし、自分だけが自然の一部になったような静寂さと充実感を覚えました。
--宮司は積極的に青少年育成に取り組まれているとか。
宮司 以前は境内で子どもがたくさん遊んでいたのに、6、7年前に子どもの声がしないことに気がつきました。ここには年間1800万人の参詣者が来られ、また遠足でも学校の生徒さんが大勢来る。でも彼らが帰るとシーンとしている。境内の自然で遊ぶことが子どもをはぐくむエネルギーになるし、鎮守の森にとっても子どもの存在やにぎやかな声がエネルギーになる。ですから子どもを呼び戻そうと親子教室などいろいろな試みをしています。
--有名な流鏑馬(やぶさめ)を海外でもされたそうですね。
宮司 10年ほど前にロンドンのハイドパークで行いました。両国の皇太子さまが拝観されましたが、人出は25万人。矢が当たった時のどよめきは地響きのようでした。日本の皇太子さまは「生まれて初めての流鏑馬をロンドンで見た」と仰せられました。9割方当たったのですが、チャールズ皇太子さまは「こんなに当たって褒美はどうするのか」と想定外の質問をされ返事に困りました(笑い)。
--海外からは神道は分かりにくいと思われるかもしれませんが、基本は自然崇拝、祖先崇拝ということなのでしょうか。
宮司 神道は他の宗教と違って創始者がいないし、教典もありません。では、どこが起点かというと日本の神話ということになる。神話は史実ではないと今では教育の現場から追いやられていますが、大事なのは古代の日本人が神様を信じた生活の中から生まれたということです。日本人はご先祖が亡くなって山にいらっしゃると信じてきた。村の祭りになると山から神様であるご先祖をお迎えして里宮にお連れする。祭りが終わると山に帰っていただく。そうなると日本人のものの考え方、歴史観は循環思考となる。一直線に右肩上がりで伸びていくという考えはリーマン・ショックでそうではないことが分かりましたが、元々日本人の考え方とは違うのです。
家元 神話で日本人の価値観や世界観を知ることができると思います。世界はますますグローバル化が進みますが、日本人のアイデンティティーの確認という意味からも自国の神話を知ることは大切なのではないでしょうか。大使、ドイツにも民族神話のようなものはあるのですか。
大使 神話はありますが、宗教とそれほどつながっていません。日本の神話は昔の話が続いているという意味で、日本文化の一つの独特さだと思います。おはらいもそうです。木には神様がいて、枝で汚いものをはらうという神道と同じようなおはらいが、ドイツや他のヨーロッパの国でもありました。でもキリスト教やイスラム教が入ってきてなくなってしまう。神道で今も続けているということは、日本人の文化として残ったからなのですね。
--宮司、鶴岡八幡宮の歴史を教えていただけますか。
宮司 頼朝公の5代前の源頼義が前九年の役で奥州を平定して鎌倉に帰り、出陣に際しご加護を祈願した源氏の氏神、京都の石清水八幡宮を由比ケ浜におまつりしたのが始まりです。1063年のことです。その後、頼朝公が1180年に今の境内に八幡様をうつしました。源氏のプライベートな神様でしたが、頼朝公が征夷(せいい)大将軍となると、精神的な支えだった八幡宮も鎌倉幕府の後ろ盾となり、武士たちの信仰を集めて彼らの守護神、関東の総鎮守となっていったのです。
 家元 鎌倉と踊りのつながりというと、二つの演目を思い出します。一つは長唄「黒髪」です。伊豆の武将、伊藤祐親の息女の辰姫が源氏再興を志す頼朝公のために己の恋をあきらめて、北条政子に妻の座を譲り、2人を2階の寝所に上げる。自分は鏡台に向かって髪をすき始める。しんしんと雪の降る夜。夜が明けると、自分の募る思いのように一面に白い雪が積もっていた……という演目です。もう一つは長唄「賤のお田巻」です。義経の恋人であった静御前が捕らえられ、八幡宮の舞殿で、「吉野山峰の白雪踏み分けて……」とうたい踊る、静の、死をも恐れない純粋で切ない女心あふれる曲です。私も大好きで、何度も踊らせていただきました。
家元 鎌倉と踊りのつながりというと、二つの演目を思い出します。一つは長唄「黒髪」です。伊豆の武将、伊藤祐親の息女の辰姫が源氏再興を志す頼朝公のために己の恋をあきらめて、北条政子に妻の座を譲り、2人を2階の寝所に上げる。自分は鏡台に向かって髪をすき始める。しんしんと雪の降る夜。夜が明けると、自分の募る思いのように一面に白い雪が積もっていた……という演目です。もう一つは長唄「賤のお田巻」です。義経の恋人であった静御前が捕らえられ、八幡宮の舞殿で、「吉野山峰の白雪踏み分けて……」とうたい踊る、静の、死をも恐れない純粋で切ない女心あふれる曲です。私も大好きで、何度も踊らせていただきました。
宮司 そうですね。非常にドラマチックで800年を超えて今なお心を打つ物語です。頼朝公、静御前、政子の3人が神様のご照覧の下、自分の心に正直で真剣な三者三様の姿を見せる。普段は静かな八幡宮ですが、いざというときは命をかけて自分自身に真剣に向き合う場が神社の境内だということを私は教えられましてね。神職としてしっかりやらねばと志を立てたのはこの物語を知ったことからでした。
--大使、ドイツでお勧めの観光スポットというとどこですか。
大使 ドイツで神話といえば英雄「ジークフリート」の物語があります。ジークフリートがドラゴンと戦った山はボンからすぐでライン川下りや古城めぐりも楽しめます。おいしいワインも多い。変わった飲み物としてはリンゴ酒。2度3度飲めばすごくおいしいことが分かると思いますね。近くのケルンに行けば、500年以上かけて造られたケルン大聖堂が見られます。教会ではドレスデンの聖母教会も知っていただきたい。第二次世界大戦の爆撃により多くの人が亡くなった。それが数年前にイギリス市民らの協力も受けて再建されました。平和と戦争の悲劇を考えることのできる場所です。
--自然を敬う神社はエコロジー精神を感じさせる場所ですが、ドイツは環境でも先進的に取り組んでいますね。
大使 環境の大切さは市民にも企業にも分かりにくかった。ですから法律を作ったのです。温暖化の問題もあり、10年、15年たって市民にも企業にも環境対策が利益になるということが理解されてきました。
宮司 日本人は古来、一本の木、森、川、山、すべてに霊が宿っていると考えて大切にしてきました。戦後の復興期に経済最優先となり、国内はもちろん、東南アジアの国々の木まで切り倒した。かつての日本人としては考えられないことをしたわけです。ですから自然を大切にする心根を取り戻したいと、境内で植樹活動をしています。人間は本来、心や情など内から外へ影響を与えていましたが、今は外の無機質なものが中へ入っている。金融やIT、子どもたちのゲームソフトもそうです。内から外へ出て行くような営みに変えなくてはいけませんが、それには自然に親しむことが一番だと思います。
 家元 明治の文明開化以来、日本は欧米に追いつけ追い越せと近代化を進めてきましたが、最近では若者を中心に経済競争はもういいのではないかという考えが起こっています。それぞれの国柄を再認識し、その中で自らを発見するという流れになってきた気がします。異質の世界を認め合い、受容するという、神道の神髄である共存共栄ができたら世界はもっと豊かになるのではないでしょうか。
家元 明治の文明開化以来、日本は欧米に追いつけ追い越せと近代化を進めてきましたが、最近では若者を中心に経済競争はもういいのではないかという考えが起こっています。それぞれの国柄を再認識し、その中で自らを発見するという流れになってきた気がします。異質の世界を認め合い、受容するという、神道の神髄である共存共栄ができたら世界はもっと豊かになるのではないでしょうか。
吉田しげほさん より