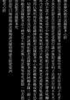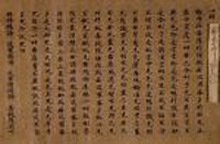 『般若心経』は一般には600巻に及ぶ『大般若波羅蜜多経』の心髄を治むといわれているが、『大般若波羅蜜多経』(『大般若経』)及び『摩訶般若波羅蜜経』(『大品般若経』)からの抜粋に『陀羅尼集経』に収録されている陀羅尼(Skt:dhāranī)を末尾に付け加えたものである。般若経典群のテーマを「空」の1字に集約して、その重要性を説いて悟りの成就を讃える体裁をとりながら、末尾に付加した陀羅尼によって仏教の持つ呪術的な側面が特に強調されている。
『般若心経』は一般には600巻に及ぶ『大般若波羅蜜多経』の心髄を治むといわれているが、『大般若波羅蜜多経』(『大般若経』)及び『摩訶般若波羅蜜経』(『大品般若経』)からの抜粋に『陀羅尼集経』に収録されている陀羅尼(Skt:dhāranī)を末尾に付け加えたものである。般若経典群のテーマを「空」の1字に集約して、その重要性を説いて悟りの成就を讃える体裁をとりながら、末尾に付加した陀羅尼によって仏教の持つ呪術的な側面が特に強調されている。
般若心経の「心」とは、サンスクリットで心臓=重要な物を意味する「hṛdaya」(フリダヤ)の訳語であり、同時に呪(陀羅尼、真言)をも意味する語である。そのため、般若心経は空観を説く経典であるとされる一方、陀羅尼の経典であるともいわれている。一般に般若経典には、後期の密教化したものは別として、呪文などは含まれていない。それを考慮すると、『般若心経』は、般若経典としては極めて特異なものと言える。またサンスクリット・テキストの原題には経という語はないため、陀羅尼(総持)のために作られた唱文が、中国で経として扱われるようになったのではないかという説もある。
なお最古の経典目録(経録)で、東晋の釈道安撰『綜理衆経目録』(梁の僧祐撰『出三蔵記集』にほぼ収む)には、『摩訶般若波羅蜜神咒一巻』及び『般若波羅蜜神咒一巻 異本』とあり、経としての般若心経成立以前から、呪文による儀礼が先に成立していたという説もある。
また『大般若波羅蜜多経』(大般若経)では、第二分功德品第三十二に「般若波羅蜜多」(という語句・概念自体)が大明呪(偉大な呪文)であると説かれているが、『般若心経』では、付加された雑密の陀羅尼との辻褄合わせのために「般若波羅蜜多咒」という語句が挿入されている。
陀羅尼は雑密の呪文で、サンスクリットの正規の表現ではないため翻訳できず、仏教学者の渡辺照宏説、中村元説など、異なる解釈説を行っている。
西暦2~3世紀にインドの龍樹が般若経典の注釈書である『大智度論』を著したとされ、般若心経もこの頃に成立したものと推定する説がある。しかしながら、現存する最古のサンスクリット(梵字)本は、法隆寺所蔵の8世紀後半(伝承では609年請来)の写本とされる貝葉本であり、漢訳経典より時代を下る。また、現在チベットやネパール等に伝わる写本も、それ以降の時代のものであり原形については不明で、偽経説もある。
『摩訶般若波羅蜜神咒一巻』及び『般若波羅蜜神咒一巻 異本』は、後世の文献では前者は3世紀中央アジア出身の支謙、後者は鳩摩羅什の訳とされているが、『綜理衆経目録』には訳者不明(失訳)とされており、この二人に帰することは信憑性にとぼしい。前者は現存せず、後者は大蔵経収録の羅什訳 『摩訶般若波羅蜜大明咒經』とされるが、羅什の訳経開始が402年であるため、釈道安の没年385年には未訳出である。またそのテキストの主要部は宋・元・明大蔵経版の鳩摩羅什訳『摩訶般若波羅蜜経』のテキストと一致するが、宋版大蔵経の刊行は12世紀後半であるため、このテキストが羅什訳であるということも疑われている。
649年、インドより帰還した玄奘もまた『般若心経』を翻訳したとされている[1]。 しかし、文献学的にはテキストの主要部分が高麗大蔵経版(13世紀前半)の鳩摩羅什訳『摩訶般若波羅蜜経』からの抽出文そのものであり、玄奘が翻訳した『大般若波羅蜜多経』の該当部分とは異なるため、これも羅什訳と同様に玄奘訳であるということが疑われている。
現在、玄奘訳の最古のテキストとされるものは、672年に建てられた弘福寺(興福寺)の集王聖教序碑(集字聖教序碑)中の『聖教序』の後に付加されているテキストである。しかしながら太宗が『聖教序』を下賜した648年から大幅に時間が経過している上、跋文に「勅を奉けて潤色せり」という記載があることから、この碑文は玄奘の没後にその偉業を讃えるために鳩摩羅什の訳文を元に玄奘訳としてまとめられたものではないかとする説もある。また、玄奘の弟子である慈恩大師基の『般若波羅蜜多心経幽讃』にもその旨を示唆するような記述がある。
また玄奘訳とされている『般若心経』は読誦用として最も広く普及しているが、これは羅什訳と玄奘訳との双方がある経典は、古来前者が依用されていることを考慮すると異例のことである。なお『大般若波羅蜜多経』転読は頻繁に行われるが、経典のテキストそのものを読誦することは稀である。
ウィキ から