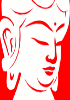私の好きな言葉といってはおこがましいが、励まされる言葉であります。仏教が他の宗教と峻別されるところなのだろうと思います。この教義は初期仏教や上座仏教ではどの様な表現になっているのでありましょうか?勉強して見ないといけないな、と思っています。(追記) 道元禅師のおことばあり「あきらかにしりぬ、自己即仏の領解をもて仏法をしれりといふにはあらずといふことを」(『弁道話』)
私の好きな言葉といってはおこがましいが、励まされる言葉であります。仏教が他の宗教と峻別されるところなのだろうと思います。この教義は初期仏教や上座仏教ではどの様な表現になっているのでありましょうか?勉強して見ないといけないな、と思っています。(追記) 道元禅師のおことばあり「あきらかにしりぬ、自己即仏の領解をもて仏法をしれりといふにはあらずといふことを」(『弁道話』)
『ブッダ』という日本語表記は、最近は違和感なく使われておりますが、実はこれは比較的新しい流れであるという、確かにそうであります。“近代以後の日本における仏教研究の進展が、必然的に「ブッダ」の表記法を選択させるに至ったという一面を見逃すことは出来ない“ (木村清孝氏 創元社 ブッダの生涯 序文)
宗派の枠外で仏教研究の著しく進展し、特に初期仏教、原始仏教について多くの著作により、そもそもお釈迦様はどのように説かれたのか、がより明快に示されるようになっております。 次なる発展として、日々多忙なる現代人の心にも響く、新しき説法の開発普及が待たれます。恥ずかしながら、“分に合わぬ話”を続けます。ページの参考サイトに日本テーラワーダ仏教協会のHPアドレスを入れました。日本で珍しい上座部仏教(南伝仏教)の協会(寺)のホームページです。<小生はこの協会を 佼成出版社「原訳発句経 一日一話」(A・スマナサーラ著)で知りました>まじめな教団のように思われますが、日本仏教界にとっては、イスラム原理主義・過激派のような存在となるかも知れません。その説法の一部を引用します。『もし釈迦尊の教えを仏教と定義するなら、日本をはじめ中国などで仏教と呼んでいるものは仏教でないということです。最澄の興した天台宗、空海の真言宗、法然の説く浄土宗、親鸞の説く浄土真宗、日蓮の説いた日蓮宗など、ふつうのひとはみんなこれを仏教と思っていますがそれはとんでもない大間違いだということです。これは当時の新興宗教であって、分かりやすく言えば最澄宗、空海宗、法然宗、親鸞宗、と解釈すべきなのです。』 (前記HPの根本仏教講義8 「仏教と仏教の違い」より)上記と同じことを仏教学の権威・故中村元博士がその著書で述べておられます。末尾の著書の釈迦の「最後の説法」(長くなるので省略)を解説されたところで、この様にあります。
『この立場をつきつめていくと、驚くべき結論に達します。後代に発達した(仏教)なるものが全部ゴータマ・ブッダによって否定されることになってしまうでしょう』 <岩波ゼミナーブックス10「原始仏典を読む」中村元 第2刷 P.129>仏教が時代とともに変化し内容豊かになることは是としても、現世利益へ誘導とか、おどろおどろしきオマジナイなどは、後世になり、他宗教やインドや中国や日本の土俗習慣などと融合するなどして付加されたもので、お釈迦様が説かれた本来の仏教には無縁のものということでしょう。原始仏教の研究成果を学習し、お釈迦さまの説かれた仏教を再確認することが極めて大切な時代的課題であると思われます。( 誇大妄想癖の分不相応な大言です )またまた、飛躍しますが、最近のニュースでみる日本人の精神世界は殺伐として末恐ろしさを感じます。
産業大国“Japan as No.1”の自信は昔話となり、20年もすると中国の台頭がさらに際立って、文化的・精神的な面でもその影響が大きくなると思われます。中国に限らず、文化も人の動きもますますボーダレス化が進むと思われます。 この状況下、わが日本人の精神的アイデンティティーはどこに求められるのでしょうか。現在日本には100を超える宗派と75000のお寺があるようであります((財)全日本仏教会のホームページから)。 また、主なる宗派人口は創価学会が820万世帯(2003年末)、真言宗 549万人、浄土宗 602万人、浄土真宗西本願寺派 694万人、真宗大谷派(東本願寺)553万人立正佼成会 561万人 であるとのことです。(新潮新書・創価学会P.14 臨済宗、曹洞宗は記載がなかった)精神的アイデンティティー崩壊に瀕しているこの日本社会を救済するべく、既成宗教各派が小異を捨て大同することは難しいのでありましょうか・・、これは大変、難しい? ことのようにおもわれます。今日の倫理崩壊社会の状況に仏教界が宗派の枠を越えた働きができず、事実上は傍観的であってはならない、ことは確かであります。