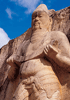隋の仏教
大象9年(589)、隋の文帝(位:581~604)によって天下が統一された。
異民族の王朝と漢民族の王朝に分裂していた中国を、再び一つに纏め上げたため、隋は、漢民族と異民族の摩擦という問題を抱え込むことになった。この問題を解決し、新たな統一国家の基礎を確立することが、文帝の急務であった。
こうした状況下、文帝は、新国家の精神基盤・施政原理として、仏教を採用した。一切の差別を超越し、超民族的である仏教は、漢民族と非漢民族との融和をはかるには都合がよかったのである。
こうしたわけで、文帝は、大興善寺を中心として仏教保護政策をおしすすめていった。文帝に続いて煬帝(位:604~618)も、仏教に理解をしめし、文帝と同じく仏教保護政策をとった。
このように、隋の仏教は国策に利用され、国家の庇護下におかれたため、国家宗教としての性格を強く有していた。

隋代には、仏教界にも大きな動きがあった。前述の通り、北周の廃仏を契機に、その反動、危機意識から、仏教復興の運動が巻き起こっていた。また、南北仏教が統一されたことは、中国仏教界に大きな刺激を与えた。
仏教保護政策、仏教復興運動、南北仏教の統一により、隋代には仏教が飛躍的に発展した。隋代に新たに成立した宗派に、三階教や天台宗、三論宗がある。隋代の仏教の発展は、唐代の仏教最盛期の基礎となった。
隋唐期は、南北朝時代までの輸入仏教が、中国的な思想・感情に適応した中国仏教へと再組織され、宗派の体制が確立した時代であった。
唐の仏教
唐王朝は、諸宗教に対して寛大であり、保護を加えたが、道教の開祖・老子と唐王室が同姓であるとして、道教を特別に重んじた。そのため、道教の地位を仏教の上におくとする「道先仏後」の政策をとった。武周朝期には、則天武后(位:690~705)が仏教を重んじたためにこの席次が覆されたものの、基本的に、唐代の仏教政策は「道先仏後」で貫かれ、玄宗(位:712~756)や武宗をはじめ、唐の歴代の皇帝たちは道教を尊んだ。しかし、実際の社会上の勢力は、仏教のほうが上であった。
唐代の仏教は、中国史上、最も隆盛を極めた。
玄奘(602~664)、義浄(635~713)らがインドに渡り、それぞれ唯識学や律などに関する新たな知識を中国に伝えた。また、玄奘は、太宗(位:626~649)の援助のもと、翻訳活動をすすめ、非常に大きな成果をあげている。
東晋頃から呪術的要素の強い雑密が伝えられていたが、それよりも体系化された純密が、不空(705~774)によって伝えられた。また、不空は、翻訳においても功績が大きかった。
こうした新たな仏教からの刺激もあり、唐代、教学仏教は最盛期となった。地論宗や摂論宗の学説を取り入れ『華厳経』に基づいて華厳宗が開かれ、真諦三蔵や玄奘のもたらした唯識学を基として法相宗や倶舎宗が開かれた。
唐の国威高揚を背景に、唐代の中国仏教は東アジア世界に伝播した。渤海、朝鮮、日本、ベトナムを包括する東アジア仏教圏が形成され、『漢訳大蔵経』に基づく中国仏教が、東アジア諸国に伝えられた。
唐代は、律令格式が整備され、それに基づく体制が整えられた時代であった。仏教関係の条目の基本であった道僧格をはじめ、出家者の犯罪等、仏教に関係する事柄についても規定が設けられていた。
道教及び仏教に関する宗教行政は、唐初は政府の鴻臚寺に、玄宗以降は鴻臚寺と尚書省の祠部に所属していた。また、唐の中期頃から、中央には僧録が、地方には僧統・僧正が設けられ、仏寺や僧尼の管理・統括にあたった。

私度を防止するため、出家者の籍を厳重に管理し、試験によって出家者を選考する制度が設けられた。公度の出家者には、祠部から度牒が交付され、身分が保証された。
唐代には、出家者といえども国家の法の支配下に置かれ、俗人の統括を受けるという原則が確立されたのである。
その後、唐代以降も、形式に多少の違いはあっても、こうした仏教統制のための諸制度は続いていった。
唐の中期以降、仏寺で催される年中行事に、一般大衆が参加するようになってゆき、民衆のために、教義を平易に親しみやすく説いた俗講が起こった。仏教が民衆の間に浸透していくにつれて、仏教は娯楽化していった。寺院は民衆にとっての文化の中心地であるとともに、娯楽の場でもあった。特に年中行事が催される時には、多くの人々が集まり、それにともなって市も開かれるようになった。
また、僧尼達は、孤児や病人等弱者に対する福祉活動や、治水、橋梁の架設、無料宿泊施設の設置などの社会事業にも積極的に貢献した。寺院による貧困者救済目的の金融事業もまた、社会事業の一種であったが、三階教の無尽蔵院のように、のちに営利目的化するものもあった。
安史の乱以降、貴族社会の崩壊と庶民社会の台頭が進んだ。仏教も、これまでは長安や洛陽に集中していたが、地方へと分散・浸透していく傾向が強くなっていった。
唐の武宗は、会昌五年(845)、決められた数の寺と僧尼とのみをとどめ、そのほかの諸寺をすべて破壊し、僧尼を全て還俗させた。また、寺院の荘園所有を禁じ、寺院財産を没収した。これが、会昌の廃仏である。
この廃仏の原因の一つに、武宗の道教信奉があげられる。
また、唐代の仏教勢力の拡大とその堕落も、廃仏の原因の一つであった。この時代、寺院は土地寄進による大土地所有を進めており、経済的繁栄を遂げてはいたが、その一方、免税目当ての私度僧や僧尼に与えられる特権を利用して暴利を貪る出家者が増加するなどして、仏教界の腐敗が進んでいた。
この現象は経済的問題にもつながる。僧は農耕等の労働を行わず、免税特権を有するため、免税目当ての私度僧の増加は、労働力不足と税収減の元となった。寺院の大土地所有も、土地集中という問題を引き起こす。また、寺院が広大な土地を所有するようになった背景には、寺院に土地を寄付することで、課税を免れようとする者が多くあらわれたこともある。このこともまた、税収減を引き起こした。
武宗の死後、廃仏の動きはやんだ。しかし、晩唐の仏教にはかつてのような力はなく、唐の国力低下にともなって、徐々に衰微していった。
http://kyoto.cool.ne.jp/rekiken/data/2001/011221.html から