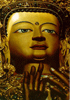初期の仏教

中国仏教の初期段階の時代には、仏は、黄帝や老子と一緒に信仰され、また、この二者と同様、神として祀られた。前述の伊存は、仏教と老子の教えとには合致点があると述べており、また、明帝は楚王英について、「楚王は黄老(黄帝と老子)の微言を誦し、浮屠(Buddhaの音訳)の仁祠を崇び、潔斎すること三ヶ月、神と誓を為す」と述べている。そして、初期仏教は、黄老信仰同様に、神仙の超越的な力による救いや利益が求められた。仏教は、まずは、仏を神仙として祀り、呪願をかけるというスタイルで、当時の中国の民間信仰と融合して受け入れられたのである。
宮中でも仏教は受容されていった。記録上最初に仏教を信奉したのは、後漢の桓帝(位:147~167)である。桓帝は、黄帝、老子および浮屠を祀り、豪華な儀式を行っている。こうして王族・貴族たちの間に仏教が受容されていった理由には、異国的な仏教法要が、当時の上流階級の好みに合ったということもあったようである。
中国では、他の多くの国々と異なり、仏教経典の翻訳が盛んに行われ、多くの経典が漢訳された。これは、中国に仏教を伝え経典を広めようとさまざまな困難を乗り越えて中国にやってきた、西方やインドの僧たちの力によるところも大きい。
その元祖といえるのが、パルティア出身の安世高である。安世高は、後漢の桓帝の建和二年(148)頃洛陽にやってきた人物で、主に小乗仏教系経典を翻訳した。桓帝の治世の末頃には、月氏出身の支婁迦讖が、大乗仏教系経典を翻訳している。また、漢民族最初の出家者といわれる厳仏調(2世紀末)も、経典翻訳を行なった。
複雑な教義を説いた経典を異言語に翻訳するのであるから、さまざまな問題が生じる。例えば、語彙の問題である。それまでの中国に無かった新たな概念を導入するとき、それを表す言葉が無いという問題にぶつかることになる。このように言葉の不足に直面したとき、老荘思想など、もともと中国にあった思想から類似する言葉を借りることもあった。そうなると無論、教義内容の説明に限界が生じる上、教義内容も本来のものから多少となりと変化してしまう。
中国に入ってきた仏教自体も、インドのものとは異なっていた。このころはまだ、中国にインド仏教が直輸入されることは無かった。中国に入ってきた仏教は、いったんインドから西域へ入り、そこで変化したものであった。また、渡来僧たちが経典を翻訳したり、伝え広めたりするとき、何らかの形で自己流の解釈が入ることもあったであろう。
後漢後期には、それまでの国家・社会の体制が大きく変動し、長い動乱の時代を迎えた。こうした中で生じる社会不安や価値観の動揺が、人々の間に仏教が浸透してゆく下地となった。人々は、これまでのものとは異なる新たなるイデオロギー、あるいは、超越的な力による救いを求めたのである。

後漢の霊帝(位:167~189)の時代、?融という人物が、広陵に大規模な仏寺を建立し、黄金で塗った仏像を作り、浴仏会や施食を行なった、という記録がある。この記録から、後漢末期には大きな仏教寺院が建設されるようになったことや仏像を祀る形式が取り入れられていたこと、儀礼面では少なからぬ進歩があったことが読み取れる。また、このころには、長江北岸まで仏教が伝播していたことがわかる。
後漢末の戦乱によって江北の住民が江南地方へ流入し、仏教信者や仏教僧も江南地方に渡った。また、当時、南海交通の発達により、南海航路から東南アジア経由で仏教が江南地方に伝わってきた。江南地方には、北からの仏教と南からの仏教が伝播し、浸透していった。北からやって来た僧侶を代表するのが支謙であり、南からやって来た僧侶の中で代表的であるのが康僧会である。二人は、呉の皇帝孫権に重んじられ、布教や経典翻訳を行った。こうして、江南地方では、首都・建業を中心に仏教文化が栄え、建業は洛陽に次ぐ仏教の中心地となった。
なお、蜀地方の仏教については資料がなく、不明である。
仏教の浸透につれて、やがて、道教や儒教からの反対攻撃もおこった。仏教は、それまでの中国になかった新たな思想・概念を中国に持ち込んだ。それが、儒教などの旧来の思想・概念と齟齬をきたし、批判・攻撃を受けることになったのである。また、仏教は夷狄の教えであるとして、中華思想の立場から攻撃を受けることもあった。三国時代、こうした攻撃に対して、牟子が、『理惑論』を著し、三教の調和を図っている。
この段階での仏教理解の程度は、あまり高くはなかったようである。前述の『理惑論』も、その教義理解は極めて貧弱であるといわれる。また、三世紀中ごろの魏でも、僧は受戒しておらず、世俗の人との違いはただ剃髪しているか否かのみであり、その宗教儀礼も、黄老信仰のようなもともと中国にあった信仰のものと変わらなかったらしい。三国時代頃までは、中国仏教は未熟であり、細かな教義理解が追求されたり、教義実践が徹底されたりすることはあまりなかった。
南北分裂期の仏教
前述のとおり、後漢時代から経典翻訳は行われていたが、西晋時代、月氏出身の竺法護によって、翻訳活動は本格化した。彼は、西域と呼ばれる中央アジアの国々を巡遊し、サンスクリット語の経典の原典を持って中国を訪れ、各地を回りつつ多数の経典を翻訳した。
また、2世紀後期ごろから、インドや西域の僧たちによって翻訳された経典をただ受動的に受け入れるだけでなく、自ら経典を求めて西方へと旅立つが現れるようになった。魏の甘露五年(260)に西域へと求法の旅に出た朱士行は、そのさきがけであったと言えよう。
4世紀初め、西晋が滅ぼされ、華北を異民族に占領され、中国は南北分裂状態に突入する。このころ、漢民族の仏教に対する関心が急速に高まってゆく。また、道教も発展し、仏教の影響を受けつつ宗教教団としての体系を形成してゆく。相次ぐ戦乱や社会の混乱の中にあって、死と死後に対する関心や、救済への願望が高まったものと考えられる。
漢代に国家のイデオロギーとして採用され、大きな力を振るうようになっていた儒教だが、それは礼や道徳を説いたものであり、人間の生活する社会を越えた世界や個人の救済といったことに関しては、ほとんど説くことはなかった。それに対する反動・反発、あるいは補いとして、仏教あるいは道教が歓迎されたという側面もある。
仏教及び道教の発展につれて、道教と仏教の対立は激化し、道仏の論難が行われ、釈迦と老子の出生の前後などが争われた。また、儒教と仏教との間でも、儒教の説く忠・孝の倫理と仏教の出家の思想との対立や、礼と戒律の齟齬、沙門の君主及び父母に対する拝不拝の問題など、双方に相容れない点が多く、この両者の間でも論戦が繰り広げられた。
仏教の側もこの時代、中国化が進んでいった。その中から、例えば華厳のような独自の教学や、禅という新たなスタイルが生まれた。
この時代、華北の王朝でも華南の王朝でも、仏教が重んぜられ、中国社会に大きな影響を及ぼしていた。だが、南北分裂期だけあり、華北と華南とでは、文化の違いやそれぞれの国家の仏教政策の違いによって、仏教の様相もずいぶんと異なっている。

五胡の諸王朝および北朝の多くは、漢民族を支配するために、漢民族固有の文化に拮抗しうる外国由来の文化として仏教を採用し、これを保護した。非漢民族である彼らは、儒教思想や中華思想にとらわれることがないだけに、比較的自由な立場から、仏教を受容してゆくことができた。華北の王朝の仏教保護政策は、中国への仏教の浸透を進めた。華北の王朝においては、宗教は国家宗教であり、人民統治の手段であった。華北の仏教は、国策と深く結びつき、保護を受けた反面、強い国家管理を受けたのである。
華南では仏教そのものが限定された少数派に過ぎなかったこともあって、国家の仏教への干渉は緩やかであった。宗教は個人の信仰とみなされ寛大な対応がとられる傾向が比較的強く、個人主義的な形態の信仰が発展した。
また、華南と華北では、仏教の形態にも違いがみられる。「南講北禅」といわれるように、華南の漢民族中心の仏教は、研究が中心であり、華北の非漢民族中心の仏教は、実践を重んじる、という傾向があった。
前述の通り、五胡の諸王朝のほとんどが仏教を重んじた。
例えば、後趙(319~352)の石勒や石虎は仏図澄(?~348)に帰依し、その布教を支援した。仏教は夷狄の宗教であり、中華の天子の奉ずべきものではないという上奏に対して、石虎は、自分は中華に君臨することになったが、もともとは胡の出であるから、仏教を信奉するのだ、と答えている。
また、前秦(351~394)の苻堅(位:357~385)も、道安をはじめとする多くの僧たちを尊崇し、その布教を助けた。また、協調関係にあった高句麗に、僧侶と経典とを送り、仏教を伝えた。これが、朝鮮初の、公式の仏教伝来であった。ついで百済にも、384年、東晋から僧が派遣されている。さらに、道安の勧めで亀茲から翻訳僧・鳩摩羅什(344~413)を迎え入れようとした。苻堅は、鳩摩羅什の到着を待たずして死亡したが、その後、後秦の姚興(位:394~416)が鳩摩羅什を長安に迎え、莫大な費用を投じて彼の翻訳を援助した。鳩摩羅什が短期間に莫大な翻訳をなしえたのは、彼の才によるところもさることながら、姚興の支援によるところも大きい。
西域からの渡来僧の中で、最も重要といわれる一人が、亀茲出身の仏図澄(?~348)である。
仏図澄は、後趙(319~352)の石勒や石虎に重んぜられた。石勒と石虎は仏図澄の布教を支援し、それにより、仏図澄は、30数年間華北で布教活動を行い、華北における仏教の振興に大いに貢献した。また、仏教の戒律を広めることにも尽力している。
彼の教化力は大きく、900近くの寺院を建て、1万人ともいわれる数の弟子を養成したといわれる。彼のもとからは、前秦時代に長安に迎え入れられ、経典翻訳や戒律の研究といった面で活躍した道安(314~385)をはじめとして、尼寺を建て、中国にはじめて正式の尼僧を生み出した安令首尼ら有力な僧侶たちが多数輩出された。
これほどに多くの弟子が生まれた背景には、仏図澄の進言をいれた石虎が、初めて漢民族の出家を公式に認めたこともある。
仏教は伝来以来、黄帝や老子とともに信仰されたが、思想上でも、老荘思想を媒介として仏教を理解・説明することが行われた。仏教の教えの基本は「虚無」であるとされ、仏教の「空」の思想は、老荘思想の「無」の思想と相通ずるものとされた。江南の貴族たちの間では清談や玄学が流行しており、江南貴族たちの知遇を得た南遷僧たちは、仏教と並んで老荘哲学をも講じた。このような、老荘思想を用いて教理を解釈・理解してゆく仏教は、格義仏教と呼ばれる。
これに対し、道安は、仏教の教義は仏教経典によってのみ理解すべきであると主張し、格義仏教を批判した。しかし、道安自身の仏教理解にもやはり、老荘的性格が見られるという。老荘思想と仏教との結びつきは、後々まで、中国仏教の性格を決定する強い要素であり続けた。空や涅槃、縁起といった、仏教に見られる思想・概念の多くは、中国にはそもそもなかったものである。したがってそれらは、中国人に理解・受容される段階での変質、中国化を避けがたい。中国人は長い年月を要して、インド人とは違った方法で、仏教を自分のものにしていく必要があったのである。
東晋・五胡十六国時代の仏教の発展には、道安(314~385)の果たした役割が大きい。
道安は、格義仏教を排し、仏教経典のみによる仏教理解の方法を確立した。
また、道安は、翻訳事業を推進し、経典の漢訳及び経典研究に尽力した。彼は、訳経を研究し、序や註釈をつけるなどするほか、経典研究に欠かせない経録(経典の目録)を制作した。翻訳僧たちが思い思いに経典の漢訳を行ったため、漢訳経典は全く未整理の状態であり、また、本物の経典であるか疑わしいものも多くあった。そこで、彼は、経典研究のため、仏法を永久にとどめるために、経典を体系的に整理し、訳経の序や註釈、経典の訳時、訳者等を記録した。これが、中国最初の経録である『綜理衆経目録』である。
さらに、戒律を重視した道安は、初めて本格的な律の翻訳を行い、戒律を研究し、僧団の日常生活の規範や僧徒の修行方法を明示した。
こうした道安の活動は、この少し後、鳩摩羅什によって新しい経典翻訳が行われた時代の、仏教の飛躍的発展の下地となった。
サンスクリット語を漢語に翻訳する際、「質」を重んじるべきか「文」を重んじるべきか、すなわち、内容が直接的に伝わる直訳を行うべきか読みやすく美しい文にするために中国風の文飾を加えるべきか、ということが問題にされた。一般に、「質」を重んじる論のほうが優勢であったが、この論は建て前でしかないことが多く、実際には、中国知識人たちに受け入れられやすく理解されやすいように、「文」を重視した翻訳が行われることが多かった。こうした中、道安は、翻訳の原則を示した『摩訶鉢羅若波羅蜜経抄序』を著している。
数多くの経典翻訳者が中国で活躍したが、そのうちもっとも重要な人物は、鳩摩羅什(344~413)であるといえよう。
道安の勧めにより、前秦の苻堅(位:357~385)は、亀茲から鳩摩羅什を迎えようとした。しかし、鳩摩羅什が来ないうちに両者ともに死亡し、後秦の姚興(位:394~416)が鳩摩羅什を長安に迎え入れた。
語学に非常に優れていた鳩摩羅什の翻訳は、非常に優れたものであり、的確な訳語が用いられ、文章も流暢で理解しやすいものであった。
彼の翻訳は一時代を画するものであった。彼の訳文は訳文の模範とされ、彼以降の訳経者の訳文は、彼の訳文に従うようになり、彼以前の訳経よりはるかにわかりやすい漢訳経典が生みだされるようになった。彼の翻訳によってはじめて訳文のみによって仏教を理解し研究することが可能となった、とまでいわれる。
鳩摩羅什の翻訳は、次の隋唐期の仏教への準備となった。仏教研究が漢訳経典のみによってできるようになったことが、隋唐期に中国独自の仏教が生み出されるようになったことの主要な基盤となったのである。例えば、彼が翻訳した経典のうち、『法華経』によって天台宗が、『阿弥陀経』によって浄土教が、『中論』によって三論宗が、それぞれ成立した。
なお、鳩摩羅什以前の翻訳は「古訳」、鳩摩羅什以降玄奘以前の翻訳は「旧訳」、玄奘以後の翻訳は「新訳」と呼ばれ、区別される。
教義理解の進展という点に関しても、鳩摩羅什は大きな功績をあげた。例えば、大乗仏教と小乗仏教の問題である。彼は、中国仏教において、大乗仏教と小乗仏教の峻別をはじめて明確にし、大乗仏教の教義を深く掘り下げ、正確に示した。東アジア仏教を大乗仏教中心へと方向付けたのは彼であるとさえいわれる。
仏教が国家によって保護されたこともあり、東晋及び五胡十六国時代から南北朝時代まで、仏教の中心となる地域は、南朝の建康及び北朝の大同・洛陽・長安といった、都の置かれた地域であった。また、西方からの仏教情報の最前線であった涼州も、仏教の中心地の一つであったし、廬山のような神聖な山岳も、仏教修行の地として重要とされていた。
なおこの時代、僧侶の修道形態は、大別して二通りの形態をとる。
一つは山居隠遁型で、中国に伝統的な隠士の生活の仏教版である。ここから道教や山岳信仰と習合した独特の仏教が形成された。
もう一つの形態は、都市にあって時の支配者の手厚い保護を受け、講学に励むというものである。
儒教は、社会や人間の関係を規定し、礼や道徳を説く。「怪力乱神を語らず」として、人間の社会を超えた存在について、説くことはない。一方道教は、儒教とは異なり、人を超えた存在や世界の原理について説き、個人の救済を視野においている。この点で、仏教と道教の間には、共通点があった。また、道教には、国家を支え、国家に保護されたイデオロギーであった儒教とは違い、為政者の学ではないという気安さもあった。そのため、仏教と道教は、もちろん対立が無かったわけではないものの、比較的容易に結びつくことができた。
しかし、儒教と仏教の間では、そうはいかなかった。仏教が漢民族社会に広まっていった東晋以降の南朝においては、仏教に理解を示す為政者・知識人が多くいた。例えば、北斉の顔之推(532~602)の『顔氏家訓』には、儒教と仏教の根本は同じであり、儒教が仏教に背くということはない、と述べられている。これは、南北朝末期の漢民族貴族の一般的な見解であったらしい。だがその一方、「仏教は夷狄の教」「仏は儒に背く」との考えもあり、仏教を排斥しようとするものも多かった。
そうした中、仏教側にも、仏教と儒教との共通点をあげ、強調を図ろうとする動きがあった。
特に、出家修行と仁・忠孝の概念との融和が問題であった。出家は、家族や君臣といった人間関係を崩壊させ、ひいては社会秩序を破るものであり、忠孝に背くものであるとして批判されていた。
そのため、仏の慈悲が衆生の救済を目的とすることが強調され、出家修行の目的が他者を救うことであるとされた。これは、儒教の独善を排し兼善を尊ぶ考えや、修身・斉家・治国・平天下の趣旨に合致するものとされた。

こうした理論をおし進める上で、大乗仏教の菩薩道は都合がよかった。だからこそ、鳩摩羅什によって大乗仏教と小乗仏教がはっきりと峻別され、大乗仏教の教義を深く正確に示されると、中国の仏教僧たちは積極的にこれを取り入れた。中国仏教においては、大乗仏教の一切衆生救済が信奉され、小乗仏教の出家主義が、老荘の隠遁思想と同様に独善的なものであるとして批判されることもあった。
さらに、『父母恩重経』が創作されるなど、孝の概念が強調され、また、皇帝の任務を衆生救済の実現として讃えるといった、俗権との折り合いをつける考えも現れた。儀式面での変容も進み、本来行われなかった葬儀や先祖崇拝の儀礼が行われたりするようになった。中国において、仏教は、孝を重んじ、先祖に対する供養を重視する宗教へと変容していった。
仏教が中国社会に受容されていくためには、こうした中国思想に基づく変容を余儀なくされたのである。
後漢末から南北朝期までに、量・種類ともにおびただしい数の仏教経典が西域や南海経由で中国に輸入され、漢訳された。
それにともない、仏教経典にも注釈がつけられるようになった。これが、注疏である。中国では、諸子、とりわけ儒教の典籍に対する註釈の伝統がある。それ故に、注疏が活発に行われたのであろう。また、儒教などの典籍に対する註釈がそうであったのと同様、仏教経典に対する註釈も、独立の書をたてることなく「註釈」という形式を守ったまま、自己の思想を主張するための道具でもあった。
この経疏にみられる様に、中国では学問仏教が盛んであった。このことも、中国仏教の特色のひとつである。
経典を受容するのみでなく、中国の各時代の宗教的ニーズに応じた経典を偽作することが行われた。これが、偽経(疑経)である。偽経は、南北朝期を中心に、あるいは仏教の権威をかりて時代・環境に応じた新鮮な主張を表現する手段として、あるいは仏教を中国にあわせて適応させるための手段として、盛んに制作された。例えば、儒教思想にあわせて孝を強調した『父母恩重経』などが、そうである。偽経にはさまざまな批判があり、経録作成時にも問題となったが、もともと宗教的ニーズに応じて制作されたものであったため、また、それぞれに独自の思想が盛り込まれていることが多いため、人気があり強く支持される経典も多い。
釈迦の死後、仏教は時代を追うごとに変化してゆき、さまざまの宗派に分裂した。当然、時代ごと、宗派ごとに、その教義内容は異なる。中国は、インド仏教の変遷の歴史を知らぬまま、そうしたさまざまな教えを無区別に輸入した。また、経典を輸入したのみでなく、偽経の制作をも行っている。
さらに、多くの経典が、その冒頭に、「如是我聞」の四字を置いたことから、経典のほとんどが、釈迦によって直接語られたものとして受容された。
こういうわけで、同じ釈迦が語った思想でありながら、それらの思想が相矛盾する、ということになってしまったのである。このため、釈迦はなぜ矛盾・対立する教義を説かなければならなかったのか、釈迦の教義の核心は何か、といったことを追究する必要が生じたのである。釈迦が説いたとされる多くの経典を何らかの基準に基づいて整理・統合することを、教相判釈という。釈迦が説いたとされる教義の矛盾を解決する必要性故に、この教相判釈が中国仏教における重要な課題となるのである。
中国人が仏教を学ぶ手がかりは、漢訳経典のみであった。だからこそ、求法の旅や経録、経疏、偽経の制作、教相判釈が行われた。新たな宗派をたてる場合にも、その根拠づけは、経典によって行われた。
北魏(386~534)の太武帝は、426年に長安を占領し、さらに北涼を滅ぼして涼州を占領した。長安と涼州という二大仏教圏が北魏に組み入れられ、北魏仏教の活力を高めることとなった。
五胡十六国時代にその基礎を築いていた仏教教団は、南北朝に入って急速に発展した。だが、仏教教団の急速な拡大のために、教団に対する国家の統制の問題が起こった。
本来出家者は出世間の存在であり、世俗の諸活動とは、政治的にも経済的にも無縁であった。それゆえに、世俗の権力者たちも、政治的介入を控え、税金の免除などを行った。しかし、中国では、反乱・一揆に仏教が利用されたり、税を免れるために出家者の免税特権が利用されたりした。僧尼には、租税や徭役を免ぜられるなどの特権があったため、この特権を目当てに、公の認可を得ず出家する私度僧が横行していた。また、大寺院は広大な土地を所有し、経済的繁栄を遂げるとともに、営利にはしり、堕落していくこともあった。このため、仏教は、出世間性を失うとともに、国家の教団統制や廃仏を受けるようになったのである。例えば、北魏は、僧制四十七条を設け、道人統という僧官を設けて僧尼あるいは仏教教団の統括にあたらせた。

太武帝(位:423~452)は、道士の寇謙之らを信任し、道教を重んじた。彼は、道教保護政策、北魏の漢化政策、仏教の急激な発展と堕落などを背景として、太平真君七年(446)、廃仏を断行した。この廃仏により、寺院の破壊、経典の焼却、僧尼の還俗などがなされた。これが中国仏教史における四回の仏教弾圧事件である「三武一宗の法難」の一回目のものである。
452年、文成帝は復仏の詔勅を下し、仏教の復興を進めた。僧を管轄する僧官である沙門統に就任した曇曜は、仏教復興事業の一環として、都・大同の近くに雲崗石窟を造営した。曇曜は、道武帝以下の北魏の五帝を五体の大仏で表し、「皇帝即如来」の思想を具体化して表現した。
孝文帝(位:471~499)は、洛陽の南、伊河のほとりに、竜門石窟を造営した。北魏から唐に至るまでの約400年間に渡って造営されたこの大石窟・竜門は、敦煌、雲崗とともに三大石窟と呼ばれる。
このころ、太武帝の廃仏に対する反動や仏教保護政策のために、仏教勢力は再び盛んになっていた。地論宗の基となる典籍を翻訳するなど、とりわけ重要な翻訳を行った菩提流支や、中国浄土教の祖の一人とされる曇鸞らが活躍している。
北周の廃仏は、建徳三年(574)、北周の武帝によってなされた。この廃仏によって、仏教寺院が没収されて貴族の住宅に当てられ、経典は焼かれ、多数の僧尼が還俗させられた。この廃仏の背景には、仏教の堕落や道仏の対立、皇帝専制体制に都合のよい儒教が国家統治の原理として採用されたことなどがあった。
武帝の廃仏のあとにも、その反省・反動や危機感情から護法の運動が起こっている。
武帝の廃仏のあとの護法の運動には、末法思想もかかわっている。このころ釈迦と老子の生誕の前後があらそわれていため、552年頃から末法が始まるとされていた。また、この頃新たに翻訳された経典にも幾つか、末法思想について述べられたものがあった。そこへ、北周の廃仏が起こった。北周の廃仏により仏法の瀕した惨状を目の当たりにした仏教徒は、急速に末法の到来を意識するようになった。
そのため、仏法を永久に保存しようとする護法の精神が強まり、経典を石刻する刻経事業が急激に興った。隋代には、那羅延窟や房山石経が造営されている。房山石経の刻経事業は、隋から金・元に至る数百年の間、断続的にではあるものの、継続されていった。
西晋が滅ばされると、西晋の一族が南下して東晋を建国した。このとき、貴族たちも含めた大量の漢民族が南下したこともあり、漢民族の有する文化が南方に進出した。これが、中国南部における仏教の発展の理由の一つとなった。
中国には、東南アジア経由でも仏教が伝えられてきた。インド仏教がスリランカ経由で東南アジア諸国に受容・消化され、それが中国に伝えられたものと、インドから中国へ、海路で直接伝えられたものが、それである。こうした仏教は主に長江以南、南北朝における南朝で受容されていった。
南朝では貴族的文化が発達し、貴族社会では高踏的・哲学的思想論議がもてはやされていた。仏教方面でもそうした傾向が強く、南朝の仏教は研究中心となる傾向が強く、教学が発達した。
こうした状況のもと、南朝の仏教は、歴代の皇帝たちの保護を受け、首都・建康を中心として発展していった。
東晋の仏教の初期に活躍したのが、道安の弟子の一人であった、廬山の慧遠(334~416)である。
慧遠は、白蓮社を創立し、阿弥陀仏を信仰し西方浄土への往生を願う浄土教をひらいた。白蓮社は中国浄土教の源流の一つであるといわれる。また、白蓮社は、中国における初の組織的な仏教結社であった。
慧遠は阿弥陀信仰を起こしたが、その頃弥勒菩薩や観音菩薩の信仰も起こっている。また、この頃、仏教を平易に説くなどして民衆の仏教享受をはかり、あるいは社会奉仕や医療の方面で活躍するなどして民衆のために貢献する僧尼も現れた。こうしたことが背景となって、この時代、仏教の民衆化が進んだ。
慧遠は、世俗の権力との妥協せず、世間と出世間とを区別づけ、出家教団は国家権力の外にあり超然たるべきであると主張し、仏門に入ったものは帝王を拝する必要はないとして『沙門不敬王者論』を著した。しかし、この「沙門不敬王者」の思想を、俗権や儒教思想の強い中国で貫き通すことは、結局不可能であった。
世俗的な権威である王法と出世間の教えである仏法との関係について、師であった道安は、「国主に依らずば則ち法事立ちがたし」と述べている。仏教に対しても強大な支配力を有していた華北の皇帝権の存在と、その皇帝権と自らとの、保護被保護の関係が反映されているのであろう。皇帝権の強い華北の王朝では、沙門の皇帝に対する拝・不拝は、問題にすらならなかった。北魏初代の道人統は、皇帝は当今の如来であり、礼を尽くすべきである、として、皇帝を拝していた。
だが、国家の統率力の弱い華南にあった慧遠は、『沙門不敬王者論』を著し、出家者は国家権力の支配外の存在であり、国王を拝する必要はないと主張した。
いったんはその主張を認める裁定が下ったが、つまりはそれも王法によって許されたものであるから、仏教はもはや法外の存在として国法の埒外にあることは認められなかった。慧遠の『沙門不敬王者論』は、出家者の世俗に対する独立性の主張であったが、中国の仏教教団は国家機構の中に組み入れられる度合いを強めていった。道安や慧遠は自治的な教団統制をはかり、制度を整備したが、その程度では僧尼の秩序は維持されることはなく、結局国家の介入を許すこととなった。
その後も、沙門の拝不拝は問題となり、皇帝を拝するよう詔が出されたり、また、それが撤回されたりを繰り返していたが、唐代頃には、沙門も皇帝を拝するという結論に落ち着いていった。この頃には、中国の仏教は中国の思想・社会様式に適応したものへと変容しており、ほとんど反対意見も出なくなっていたのである。出家者も肯定の進化としてみなされるようになり、儀式面でも、祝聖(皇帝への祈り)など、皇帝崇拝が行われるようになった。
なお、皇帝に対する拝不拝と平行して、父母に対する拝不拝も問題となっていたが、こちらも、拝すべしとの勅令が出されたり引き下げられたりが幾度か繰り返されたのち、唐代頃に、沙門といえど父母を拝すべしという結論に落ち着いた。
4世紀末、戒律は、道安などによって翻訳されたものがあったとはいえ、まだまだ不足しており、戒律の実践も極めて不完全であった。そこで、こうした状況を嘆じた東晋の僧・法顕(337?~422?)は、経と律とを求めてインドへと求法の旅に出た。同じ頃、法顕のほかにも幾人かの僧がインドを訪れている。この頃から、中国人がインドに行き、実際にインド仏教に触れ、あるいはインドから中国に仏教を直輸入するようになった。
法顕が律を得て帰国した頃には、中国でも鳩摩羅什によって律の翻訳作業が進められていた。鳩摩羅什によって翻訳された律と、法顕によって中国に持ち込まれた律によって、戒律の実践、僧伽の運営や修行方法に対する理解が進んだ。
ただ、律の実行には限界があった。律の研究者は多くあったが、完全な実践者はほとんどいなかった。たとえば、僧は三衣一鉢のみを持ち、粗末な袈裟を片肌脱ぎで着するのみであると定められているが、これは礼教を重んじる中国では受け入れがたいことであった。戒律を生み出したインドと中国の間の環境・文化の差は大きく、中国社会の中にあって戒律をきちんと実践しきることは、まず不可能である。戒律の文字どおりの実践は、僧として当然ことと認められていたのではなく、ただ形式のみのものとみなされていたのである。
インドやスリランカだけでなく、東南アジアからも、仏教が輸入されていった。
現在のカンボジア南部からメコン川下流部にあった扶南国は、仏教が盛んであった。484年、扶南国王から斉へと、仏教僧が派遣されている。また、五世紀後半から六世紀中頃にかけて梁に渡り、翻訳活動を行った僧もいた。
南朝は、宋、斉、梁、陳と王朝が変遷したが、仏教文化の黄金時代を迎えたのは、梁の武帝(位:502~549)の時代であった。
梁の武帝は、皇帝菩薩、菩薩天子などと呼ばれ、仏教を熱烈に信奉し、保護したことで有名である。自ら積極的に仏教活動を行い、仏教関係以外の政策面でも仏教の影響の強い政策を打ちだしている。その生活においても、布衣を着し酒肉を絶ち、出家者と同じ生活を送ったという。さらには、しばしば捨身を行った。皇帝たるものが布衣を身につけ捨身を行うというのは、儒教的伝統の見地からは、考えがたいことである。また、漢民族の伝統的な祭祀のスタイルを、仏教の教義に合うように変えてしまうということもあった。仏教を保護した皇帝は多いが、そのほとんどは政治的理由からで、梁の武帝のように、心底仏教に傾倒してしまうという例は珍しい。
武帝の時代、首都・建康には、多くの寺院が建設され、僧侶たちが集った。仏教学も発達し、仏教文化が隆盛をきわめた。
南朝を通じてもっとも顕著な功績をあげた訳経僧の一人とされるのが、真諦三蔵(499~569)である。
真諦三蔵は、梁の武帝に招かれ、太清二年(548)、南海航路を渡って建康にやって来た。彼の翻訳活動によって、中国の仏教学界にインドの唯識思想の体系が伝えられた。また、彼の訳した典籍は、摂論宗や倶舎宗の土台となり、華厳宗の思想形成も大きな影響を与えた。
南北朝時代の仏教で重要なものに、禅宗がある。
禅経は後漢末には既に中国に伝えられていた。初期に伝えられた禅は小乗禅であったが、南北朝期には次第に大乗禅へと移行しつつあった。そうした中、菩提達磨が中国に渡来し、大乗禅を広め、中国の禅の基礎を確立したという。
禅は、南北朝時代、主に南朝で発達した。禅は個人主義的傾向が強く、南朝では受け入れられたが、北朝では弾圧される傾向にあった。
http://kyoto.cool.ne.jp/rekiken/data/2001/011221.html から