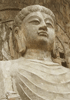中国では古来、さまざまな宗教、あるいは、それに準ずる思想が、信奉されてきました。インドから取り入れられてきた仏教も、その一つです。今回は、仏教の歴史を、非常に大雑把にではありますが、たどってみたいと思います。
仏教の伝来
中国と中央アジア、インド、さらにはイラン、ローマを繋ぐ交易路・絹の道は、紀元前2世紀ごろから開けていた。この絹の道が、中国への仏教伝来ルートの一つとされる。仏教は、主にこのルートを通じて中国に伝来した。
絹の道を通じて、古くから仏教が栄えていた西域やインドの商人が、中国を訪れた。特に、紀元1世紀に北インドから中央アジアにかけて建国されたクシャーナ朝の時代には、広範囲にわたって活発な貿易活動が展開され、中国との交渉も盛んであった。商人たちの中は、当然仏教徒もいる。彼らとの接触の中で、中国人の間にも少しずつ仏教が伝わっていった。紀元1世紀には、仏教が中国に伝わっていたであろうと考えられる。
また、西域方面から、仏教信者たちが渡来してくることもあった。こうした渡来者たちが、中国仏教のごく初期の段階における信者の中心となったと考えられる。
この絹の道は、その後も、西方からの仏教情報の伝達ルートであり続けた。
ただ、西域は、単なるインド-中国間の中継地・経由地ではなかった。一度西域に入った仏教は、この西域の各地で特色ある仏教へと変化し、それが中国に伝えられた。西域は、いったん自身のうちに取り込み、消化した仏教を、中国に伝えていたのである。

仏教情報の伝達ルートには、もう一つ、大きなものがある。それが、インドやスリランカから、マレー半島やスマトラ島、インドシナ南部を経由して広州へと到達する南海航路である。山東や江南などの沿海部では、このルートから仏教が初伝したともいわれている。また、中国僧がインドやスリランカへと仏教を学びに行く際にも、このルートが用いられた。
仏教の初伝については、古くから中国にはさまざまな伝承・記述がある。しかし、その多くは、主に六朝時代から唐代にかけて創作されたものである。仏教より早くから中国に根付いていた儒教や道教に対して仏教が優位に立つために、仏教側は、仏教がより古くから中国にあったのだと主張することで仏教を権威づけようとしたのである。こうした伝説には、例えば、三皇五帝の時代に既に仏教が中国に知られていたとするものや、秦の始皇帝の焚書によって仏典が失われたとするものがある。
そのような中で比較的信用できるものとしては、魚豢の『魏略』西戎伝および笵曄の『後漢書』があげられる。『魏略』西戎伝には、前漢の哀帝の元寿元年(紀元前2年)に景廬という人物が大月氏の使者・伊存から仏教の経典を口授された、とある。また、笵曄の『後漢書』には、後漢の明帝(位:紀元57~75)の異母弟・楚王英が任地・彭城で仏教を信奉していたと記されている。
http://kyoto.cool.ne.jp/rekiken/data/2001/011221.html から