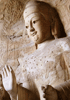四世紀から五世紀のはじめにかけて、北方に五つの異民族(五胡)が興亡し、その中で十六の国が興廃した時代、すなわち五胡十六国時代が展開し、南方には漢民族の王朝である東晋(三一七~四二〇年)が展開した。
四世紀から五世紀のはじめにかけて、北方に五つの異民族(五胡)が興亡し、その中で十六の国が興廃した時代、すなわち五胡十六国時代が展開し、南方には漢民族の王朝である東晋(三一七~四二〇年)が展開した。
この時代、北方を代表する僧侶は仏図澄(二三二~三四八年)である。彼は神通力と予言能力・教化力により多くの門徒を養成した。その弟子の道安(三一二~三八五年)は、仏典に注釈を施し序文を書いたほか、最初の経典の目録を編纂するなど重要な役割を果たした。
一方、南方の東晋を代表する僧侶で、道安の弟子であった慧遠(三三四~四一六年)は廬山にこもり、東晋仏教界の指導者となった。彼は北方で活躍していた鳩摩羅什と仏教教理に関する問答を行ったほか、浄土思想である念仏結社の白蓮社を創設した。また僧侶(沙門)は王者に敬礼する必要がないと説いた『沙門不敬王者論』を著した。東晋においても『涅槃経』や『華厳経』などの大乗経典の翻訳が行われた。総じてこの時代は、鳩摩羅什が翻訳した経典とあわせて、主要な経典の翻訳が行われた時代であり、これが次の時代に学派が興隆する基盤を形成した。
五世紀になると、北は北魏など五代の王朝が支配し、南は宋・斉・梁・陳の四つの王朝が統治する南北朝時代となる。北魏は廃仏もあったが、基本的に仏教を積極的に保護し、現在にも残る雲崗石窟、竜門石窟を開鑿した。また南においても仏教は保護された。特に梁の武帝(在位五〇二~五四九年)は崇仏天子として有名であり、夥しい寺院建立などは国家財政を傾けたほどであった。
この時代には、南北ともに仏典の本格的な研究が行われ、『涅槃経』を研究する涅槃学派、同じく『成実論』の成実学派、『十地経論』の地論学派、『摂大乗論』の摂論学派などの諸学派が成立した。さらに、この時代には、『提謂波利経』『占察善悪業報経』など中国で撰述された経典が作られるようになった。これらはインド撰述の経典を正統とする立場から疑経(偽経)とよばれ区別された。疑経の制作目的は、仏教と中国人の土着思想(儒教など)とを結合させ、民衆の布教に役立たせようとするものであった。そのほか、この時代には仏教芸術も発達し、雲崗・竜門以外にも、敦煌石窟、麦積山石窟などの石窟寺院が開鑿された。
四世紀から六世紀にかけては、前代に引き続き仏典の翻訳を行いながらも、一方では様々な学派の形成に見られるように、中国人がインド仏教を消化し、自分たちのものにしはじめた時期といえる。そしてこれが土台となって次の隋唐代の仏教へと結実する。
(文・佐藤 厚 さとう・あつし 一九六七年、山形県生まれ。専門はインド哲学・仏教史。東洋大学非常勤講師)
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/16.html から