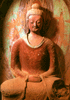インドで成立した仏教は、時を経て中国に伝わったが、インドと中国とでは古来、言語や習俗・思想が大きく異なる。そのため、仏教も、次第に中国的 な特徴を獲得していった。また、こうした中国の仏教は、朝鮮半島、日本、ベトナムなどに伝播し、東アジア世界に中国仏教文化圏を形成した。
中国への仏教伝来の説話のなかで最も有名なのは、後漢(二五~二二〇年)の明帝(在位五七~七五年)の感夢求法説である。これは明帝が夢の中で金 色に輝く「金人」を見て西方に仏がいることを知り、大月氏国(アフガニスタン北部)に使者を派遣して『四十二章経』を写させ、さらに仏寺を建てたとするも のである。この仏寺は洛陽の白馬寺であると言い伝えられてきたが、現在では、この説は史実とはみられていない。
現在、史実と考えられているのは、後漢の明帝の異母兄であった楚王英(?~七一年)の仏教信仰に関する記録である。そこでは楚王英が「黄老の微言 を誦し、浮屠の仁祀を尚ぶ」と記されている。黄老とは、黄帝(中国古代の伝説上の王)と老子のことで、不老長生を願う信仰であったと考えられる。次の浮屠 とはブッダの音写であり仏教のことである。これは現世利益を求める中国の伝統的な思想と外来の仏教とをともに信仰していたことを意味する。

また、中国の皇帝ではじめて仏教を信奉したのは後漢の桓帝(在位一四六~一六七年)であるが、桓帝も楚王英と同様、仏陀と黄老とを合わせて祀り、不老長生の現世利益を願った。このように中国人は仏教を現世利益の神の一つとして受け取ったのである。
多くの訳経僧の活躍
後漢の時代には、西域を通じて経典を翻訳する僧侶(訳経僧)が渡来するようになった。最初の訳経者は安世高(二世紀)である。彼はイランを中心と した安息国(パルティア)の出身であり、一四八年頃、桓帝のときに洛陽に来て、『安般守意経』『阿毘曇五法経』など禅観(修行や実践の教え)と「小乗」仏 教の経典を訳した。安世高と同じ頃、支婁迦讖(二世紀)も洛陽に来ている。彼は大月氏国の出身であり『道行般若経』『般舟三昧経』などの大乗経典を訳し た。
後漢が滅んだ後、中国は分裂し、魏、西晋王朝と続く。王朝の変化にともない中心的な思想も、儒教から老荘思想へと移り変わった。また、魏の時代には西域との交通が盛んになり、訳経僧も数多く渡来した。
こうしたなか、朱士行(三世紀)は中国人として初めて西域に求法し『般若経』の原本を求めた。『般若経』の思想は、世俗から距離を置く老荘思想を 信奉する中国の知識人層に受け入れられ、とくに「空」の思想の解釈が追求された。これ以降、仏教は中国人のあいだで哲学的に研究されていくことになった。
続く西晋(二六五~三一六年)時代の仏教界で最も活躍したのは大月氏出身の竺法護(二世紀後半頃)である。彼は『光讃般若経』『正法華経』をはじめ一五〇部を超える多くの経典を翻訳し、大乗仏教を中心として後代の中国仏教に大きな影響を与えた。

(文・佐藤 厚 さとう・あつし 一九六七年、山形県生まれ。専門はインド哲学・仏教史。東洋大学非常勤講師)
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/15.html から