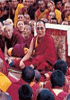一四世紀、チベットのツォンカの地に生まれた男児は、長じて偉大な学僧となり、出身地に因んでツォンカパと呼ばれた。そして、彼を慕う弟子たちによってゲルク派と呼ばれる新たな宗派が誕生した。この派の勢力が伸びるに従って他宗派、特にカギュー派の支派カルマ派との軋轢が大きくなったが、ゲンドゥンギャムツォはカルマ派の勢力を押さえてゲルク派の最高指導者となった。さらに彼が逝去した後、スーナムギャムツォが迎えられ、青海湖のほとりでチンギス・ハーンの末裔アルタン・ハーンに「ダライ・ラマ」(「大海のラマ」)という称号を授けられる。現在、世界的に有名になったダライ・ラマは、このような経緯で誕生した。
スーナムギャムツォはダライ・ラマ三世に位置づけられ、ツォンカパの直弟子ゲンドゥントゥプが一世、ゲンドゥンギャムツォが二世とされた。さらには、ソンツェンガンポ王(五八一~六四九年)にまで遡る転生の系譜が作られ、ダライ・ラマは古代からチベットを治めていたという物語が作られた。

その後も、モンゴルから選ばれた四世、国王として政権を確立し、ポタラ宮を建設した五世、酒食を愛し、遊興に耽った六世、清朝の内政干渉により政権崩壊を経験した七世……といった具合に、それぞれ特徴を持ったダライ・ラマが続いたが、九~一二世は、みな若くして毒殺され、政治的混乱が続いた。
一方、一三世はそのような事情を知っていたため、用心深く振る舞うことによって暗殺を回避することができた。そして、辛亥革命により清朝が滅びると、亡命先のインドからポタラ宮に戻り、反対派勢力を粛清して、チベット独立を宣言した。しかし、一四世の時代になると、チベットは再び試練の時を迎える。一九五〇年代の中国人民解放軍による侵攻をきっかけとする武装蜂起(チベット動乱)を経て、一四世はインドへ亡命することとなる。このような経緯については、ブラッド・ピット主演の映画「セブン・イヤーズ・イン・チベット」などにも詳しい。また、文化大革命の際にも破壊活動によって、多くの貴重な文化遺産が失われた。
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/14.html から