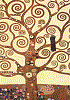団塊の世代が父母を送り、自らも送られる年齢に近づいたのと無縁でないのかもしれません。死や葬儀をテーマにした映画や歌、書物が売れています。
記憶に新しいのは昨年二月に映画「おくりびと」が日本映画初のアカデミー賞外国語映画賞を受賞した快挙でした。
チェロ奏者の職を失い、故郷に帰って納棺師となった青年を主人公にした二〇〇八年度のこの映画は、死が人類普遍のテーマでもあるからでしょう、国内の映画各賞を総なめにし、モントリオール世界映画祭グランプリなど世界各地で賞を獲得しました。
死とかけがえなき生と
遺体を清め、化粧を施し、着付ける納棺師の所作から伝わる優しさ、尊厳と敬意は、外国人をも感動させ、癒(いや)しました。死と向き合うことはかけがえのない生を見つめること、とのメッセージと余韻。映画は死を語ることがタブーではなくなった時代の到来をも告げてもいました。
人はだれも死を免れないのは歴然たる事実です。肉親や知人の死には心を込めた哀悼を捧(ささ)げたいし手厚く弔いたいものですが、葬儀や埋葬に巨額な費用が伴うとなるとためらいや懐疑が生まれます。
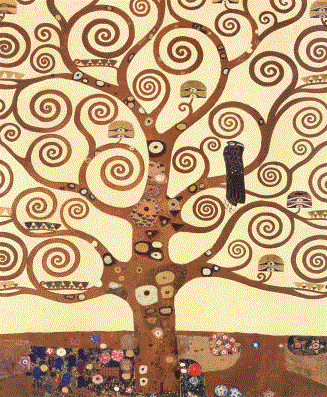 戒名や法名への謝礼を含め、日本人の葬儀にかける費用は平均二百三十一万円と世界一。墓まで設けると、都市では五百万、一千万円も珍しくなく、葬儀、埋葬は何のため、本当に必要だろうかとの疑問がわくのも当然です。
戒名や法名への謝礼を含め、日本人の葬儀にかける費用は平均二百三十一万円と世界一。墓まで設けると、都市では五百万、一千万円も珍しくなく、葬儀、埋葬は何のため、本当に必要だろうかとの疑問がわくのも当然です。
そんな疑問に答えつつ、「葬式仏教が衰退し、葬式を無用なものにする動きが強まっていく。それは歴史の必然」と予言するのが宗教学者の島田裕巳氏の著書「葬式は、要らない」(幻冬舎新書)。一月の発売以来二十九万部を売り上げ、いかに葬儀に関心がもたれ共感を得ているかが分かります。
直葬や家族葬の必然
日本書紀による仏教伝来は欽明天皇十三年(西暦五五二年)。皇室や豪族、貴族の宗教は、鎌倉新仏教で一般民衆のものに革新されましたが、「葬式仏教」の成立は新しく、江戸初期の寺檀(じだん)制度に由来するとされます。
寺檀制度は、寺が家と檀家関係を結び、葬祭や法事を永続する代わりに布施を受けるシステム。禁教のキリシタンでないことを証明させる幕府の宗教政策として始まりましたが、寺は宗旨人別帳に檀家の家族構成や生没、婚姻を記録して行政機能の一翼を担うようになりました。戒名や法名を授かることもほぼ義務化され、これが現代の葬儀へと連なります。
ただ寺檀制度は村落共同体と家の存在を前提にしています。共同体は檀家を構成し葬儀の際には助け合わなければなりません。日本人の信仰の核は祖先崇拝で、寺への期待は先祖供養です。その共同体も家も消えているのが戦後社会で、現代の変化は急速です。
 最近の都市部で急増しているのが直葬や家族葬。近親者だけで通夜、火葬場で荼毘(だび)に付して見送るのが直葬。僧侶に読経してもらうケースもあるようですが、東京では二、三割が直葬とされます。
最近の都市部で急増しているのが直葬や家族葬。近親者だけで通夜、火葬場で荼毘(だび)に付して見送るのが直葬。僧侶に読経してもらうケースもあるようですが、東京では二、三割が直葬とされます。
故郷から離れて久しく、寺との檀家関係も、供養すべき祖先をもたない都市生活者には直葬や家族葬の方が心のこもった弔いになるようにも思えます。葬儀の簡素化は必然。戒名も仏典の規定にない日本独自の奇妙な習慣と知れば、高額な謝礼を支払ってまで授かる必要はない、と割り切れます。
納骨も跡継ぎがいなければ、墓をつくるのは躊躇(ちゅうちょ)することになります。永代供養の寺や海や山への散骨、樹木のもとへの樹木葬、焼き物の容器やペンダントに入れての手元供養などさまざまな工夫が広がるのも自然です。
ライフスタイルの変化は新たな問題を生みます。精神科医の香山リカさんが「しがみつかない死に方」(角川oneテーマ21)で報告しているのは、都会のひとり暮らしの三十、四十代女性を襲う孤独死恐怖症候群。タレントの飯島愛さんや女優の大原麗子さんの孤独死をきっかけに診療室を訪れるシングルが増えたといいます。
香山さんは「孤独死時代」の豊かな生き方をアドバイスしていますが、孤独は女性ばかりではありません。男性も、高齢者も、戦後の核家族化した社会の宿命です。
本義に立ちかえるとき
変わる葬儀と埋葬。あらためて気づかされるのは、数百年の慣習や習俗を捨てさせ、死生観や精神の奥深くにまで影響を与えている戦後社会の大変化です。変わるべきものと不易であるべきものとの見極めが問われてもいます。
全国に寺院は七万、二万が廃寺や無住になっているとされます。生きる者の苦悩や不安に向き合う仏教の本義にかえる以外に、甦(よみがえ)る道があるものなのでしょうか。
中日新聞 から