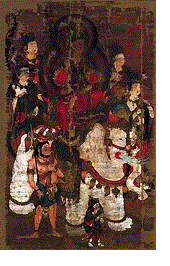 上田市別所温泉の常楽寺美術館は7月19日から8月8日まで、開館40周年を記念した特別展「法華経の光-天台法華宗、信濃へ-」(信濃毎日新聞社、上田市教育委員会共催)を同館で開く。国宝3点、重要文化財10点をはじめ、京都や東京の博物館などが所蔵する貴重な仏教美術品42点が並び、中には県関連の品もある。監修する京都国立博物館企画室長の久保智康さん(51)は「国宝や重文が地方でこれだけ集まるのは珍しい」と話している。
上田市別所温泉の常楽寺美術館は7月19日から8月8日まで、開館40周年を記念した特別展「法華経の光-天台法華宗、信濃へ-」(信濃毎日新聞社、上田市教育委員会共催)を同館で開く。国宝3点、重要文化財10点をはじめ、京都や東京の博物館などが所蔵する貴重な仏教美術品42点が並び、中には県関連の品もある。監修する京都国立博物館企画室長の久保智康さん(51)は「国宝や重文が地方でこれだけ集まるのは珍しい」と話している。
常楽寺美術館は、比叡山延暦寺(滋賀県)住職の半田孝淳天台座主(上田市出身)が住職を務めた常楽寺境内にある。特別展で展示する国宝のうち「金銅宝相華文(こんどうほうそうげもん)経箱」=比叡山延暦寺所蔵=は平安時代に作られ、時の権力者、藤原道長の娘が写経した法華経を収めた経箱。ほかの2点は、平安時代最高の技法で蒔絵(まきえ)が描かれた「宝相華蒔絵(げまきえ)経箱」=同寺所蔵=と、巻物「法華経 開結共(かいけちとも)」=浅草寺(東京都)所蔵。
重要文化財は、木の板に仏を彫った「板彫法華経曼荼羅(まんだら)」=横蔵寺(岐阜県)所蔵=や、「普賢(ふげん)菩薩(ぼさつ)像」=安楽寿院(京都市)所蔵=など。県関係では、松本市宮渕で出土した仏具「銅鰐(わに)口」=東京国立博物館所蔵=が登場する。平安時代の物で、現存する最古の鰐口という。
久保さんによると、天台宗の開祖・最澄が東国布教の足掛かりにしたのが信濃の国で、多くの天台寺院が建立された。上田市内の遺跡からは仏像や仏塔のかけらなどが多数出土しており、このうち6点を展示する。久保さんは「平安時代の信濃は仏教文化の先端を走っていた。特別展で当時の仏教文化を感じてほしい」とする。
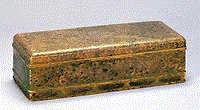
7月19、23、28日、8月7日の4日間は午後1時半から、常楽寺本堂で記念講演会がある。19日は久保さんが特別展の見どころ、富山大教授の松浦正昭さんが仏教美術について講演する。
常楽寺美術館は準備のため今月15日から休館する。特別展は午前9時~午後5時。観覧料は大人800円、高校生以下500円。講演会はいずれも無料。問い合わせは同美術館(電話0268・37・1234)へ。
信濃毎日新聞 より

