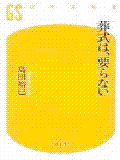 日本における葬儀費用の平均は、231万円。ちなみにイギリス12万3千円、ドイツ19万8千円、韓国37万3千円、アメリカ44万4千円。日本だけが飛びぬけて高いのは一目瞭然で、この比較を広告や帯に打ち出した『葬式は、要らない』が売れている。
日本における葬儀費用の平均は、231万円。ちなみにイギリス12万3千円、ドイツ19万8千円、韓国37万3千円、アメリカ44万4千円。日本だけが飛びぬけて高いのは一目瞭然で、この比較を広告や帯に打ち出した『葬式は、要らない』が売れている。
葬儀に金がかかることはずいぶん前から知っていたが、ここまでとは……。そんな驚きとともにこの本を手にとった読者は多いだろう。著者の島田裕巳はまず、今にいたる日本の葬式の歴史を振り返り、なぜこうなってしまったのか解説する。そこでポイントとなるのが、日本の仏教が葬式仏教と化していく過程と、村社会によって育まれた世間体という問題である。
〈生前に死後について考え語ることはできないし無駄だ〉と説いた釈迦の教えとはうらはらに、中世の貴族たちは死後も華やかに暮らせるよう願い、浄土を目の前に出現させようとした。ここにこそ日本人の葬式が贅沢になった〈根本的な原因〉があると島田は指摘する。この浄土教信仰が一般民衆にまで広がり、江戸時代に「寺請制度」によって村落共同体が強化されることで、禅宗の方法を基本とする仏教式の葬式が国の隅々にまで浸透。こうなると村落内での世間体が気になり、見栄をはる葬式が増えていった。
このような歴史的背景と村社会の名残の下、私たちは金のかかる、贅沢な葬式を続けてきた。しかし、核家族化が地方にまで進んでいる現在、この本がベストセラーになっているように、既成の葬式に対する疑問は高まるばかりだ。その象徴ともいえる戒名については、島田も多くのページを割き、自分でつけるやり方まで紹介している。ただし、減り続ける檀家に悩む多くの寺院にとっては、戒名料は貴重な財源でもある。
急激な変化ではないにしろ、日本の葬儀が簡略化、多様化していくのは間違いないだろう。さて、もう一方の当事者である日本の仏教界は、この時勢にどう対処していくのだろうか。

